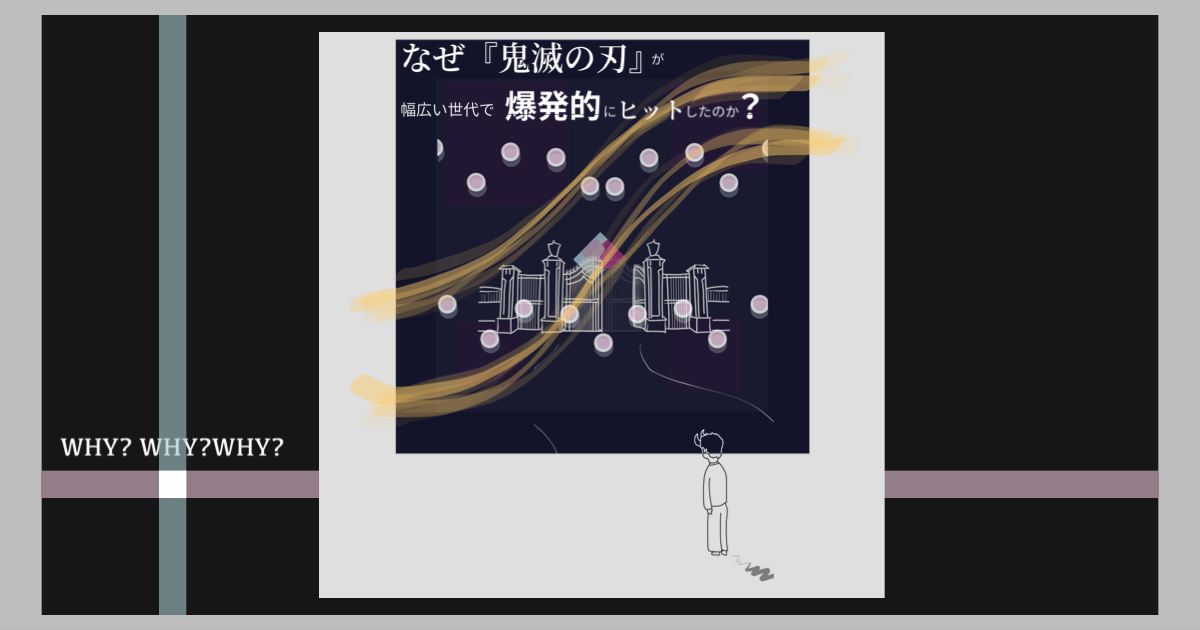
Updated on 4月 18, 2021
なぜ『鬼滅の刃』が幅広い世代で爆発的にヒットしたのか? その6 『鬼滅』炭次郎と無惨からみる力の二つの意味
こんにちは、matsumoto takuya です。今回も前回にひきつづきシリーズ「なぜ『鬼滅の刃』が幅広い世代で爆発的にヒットしたのか?」をおおくりします。
前回の投稿で、『鬼滅の刃』の鬼と現代にいきるわたしたちの意外な共通点をみてきました。そのなかで「内的な繋がり」というキーワードに辿り着きました。『鬼滅の刃』で、この「内的な繋がり」が感じられる人間関係を築ける代表格が主人公、竈戸炭次郎です。
今回は、かれの魅力に近づいていき、この「内的なつながり」の正体を探りながら『鬼滅の刃』の世代を超えた大流行の秘密により深く迫っていきたいと思います。
では、さっそくいってみましょう。
炭次郎の「力」と無惨の「力」
この「内的な繋がりが感じられる関係」を築ける代表格が主人公、竈戸炭次郎です。『鬼滅の刃』の魅力の一つは間違いなく彼の魅力でしょう。ここで、彼について少しみていきたいと思います。
炭次郎は、「鬼」となってしまった妹の禰豆子を人間に戻すために、「鬼」を討伐するための組織である鬼殺隊に入隊することになります。かれは謙虚で優しい少年です。しかし、卑下はしませんし、精神面では決して服従せず、自分の信念のもとに意見を述べ、その結果から返ってくる上からの反発を覚悟で行動できる勇気を持ち合わせています。旧世代の鬼殺隊の倫理を尊重しつつも、そのまま鵜呑みにし自己に取り入れることはせず、自分が経験から感じ取ったものから自らの考えを育みます。同時に、集団の規律自体には従順に従うことができるので、他人や組織と連帯できます。
例えば、「鬼」である妹を同伴すること、「鬼」の人間性への配慮など、時にその考えは鬼殺隊の幹部や多数派にとっては異端であり、敵意を持たれることすらあるにもかかわらず、彼は自ら感じ考えたことや信念に誇りをもち、必要とあれば意見を言うことができます。また、自分の信念も、固執するわけでもなく、他人とのかかわりのなかで気づいたことや発見したことから、必要とあれば修正してバージョンアップさせていきます。
彼は少年という設定ですが、精神的に自立し成熟しています。彼は個性化の先にある「私」を確立しており、自分であることに安心できていると同時に、他の人間を自分とは異なる個をもった存在であるという「自他の区別」の認識ができるに至っています。これは「悩みがない」という意味での安定ではなく、悩みがあっても自分で対応できるのだ、という内面的な強さからくる安心です。別の言い方をすれば、自発的に社会で関係を作り出していける能力を獲得するに至っていることで獲得できる真の自信です。竈戸炭次郎にはそういう能力、力がある。
では、「鬼」のほうはどうでしょうか。一見すると勝手気ままで自由を謳歌しているようにみえる「鬼」の実際は、上位の「鬼」に管理されている中での与えられた自由であり、上位の「鬼」に気にいられている間は自由ですが、上位の「鬼」に見捨てられないかという不安がつきまといます。そのため、上位の「鬼」に気にいられるように上位の「鬼」が喜びそうな力を際限なく求めつづけます。そのトップに君臨するのが鬼舞辻無惨です。トップであるはずの無惨はなぜか「いつもなにかに怯えている」不安定さを胸に隠しつつも、彼には支配力、力がある。
ここで、わたしは力という言葉についての定義の曖昧さに気が付かされます。炭次郎は「力」があるといえる。無残にも「力」があるといえる。とは言っても、この両者は内容が明らかに違うことぐらいは分かります。力とはいったいどういったものなのでしょうか。
力の二つの意味
フロムよるとに「力に」は二つの異なる種類があると述べています。その二つとは、支配力と能力です。
「力」という意味は二様の意味を持っている。第一には、それはなにものかに対する力の所有であり、他人を支配する能力を意味する。第二には、それは何かをする能力を所有すること、能力があること、潜在能力のあることである。後者の意味は支配とは無関係である。それは能力という意味における熟達を意味する。無力というときも、われわれはこの意味で考える。すなわち他人を支配することのできない人間を考えず、したいと思うことのできない人間を考える。こうして力とは、支配か能力かの、二つに一つを意味する。それは同一どころか、お互いに相いれない性質である。無能力という言葉は、たんに性的能力だけでなく、人間能力のあらゆる領域に用いられるが、それは支配へのサディズム的努力を導くものである。個人が能力ある程度に応じて、すなわち、自我の自由と統一性との基礎の上でかれの潜在的能力を実現できる程度に応じて、彼は支配する必要はなくなり、したがって権力のあくなき追求といったことはなくなる。支配という意味における力は逆である、ちょうど性的サディズムが性的愛情の逆であるように。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社:180項
この「力」の定義をまとめ、さきに取り上げた炭次郎と無惨を当てはめてみると、次のようになります。。
- 能力があること(竈戸炭次郎) ・・・何かをする能力があること(潜在能力、能力という意味での熟練)
- 他人を支配する力(鬼舞辻無惨)・・・他人を支配する能力(なにものかに対する力の所有)
炭次郎は、自らの個性を受け入れ、それを発展・成長させ、自らの感覚や、感情、考えを社会の中で表現できます。つまり、「自我の自由と統一性との基礎の上でかれの潜在的能力を実現でき」ているので自らの力を実感できているので、「彼は他人を支配する必要はなくなり、したがって権力のあくなき追求といったこと」をする必要なく、安定できているわけです。
「鬼」は個性にあたる人間の頃の「私」を失っています。「私」が何を本当に求めていたのかさえ忘れてしまった「したいと思うことのできない」存在であり、「自我の自由と統一性との基礎の上でかれの潜在的能力を実現でき」ません。それゆえ、その無力感と弱小感からくる不安を払拭するために、「支配へのサディズム的努力」に追い込まれていることがみえてきます。
注)筆者はアニメ『鬼滅の刃』~『劇場場「鬼滅の刃」無限列車編』までしかみておりませんのであしからず
「無力というときも、われわれはこの意味で考える。すなわち他人を支配することのできない人間を考えず、したいと思うことのできない人間を考える」と指摘している点は重要です。
これは逆から言えば、ランキングが異常に気になったり、他人に干渉したり、コントロール思考に過剰に走っている人間は、何らかの事情で「私」として生きることに挫折し、潜在能力の不全感からくる欲求不満と無力感のようなものを胸に抱えているということです。自分を疎外してでもなんらかの「匿名の権威」に同調・同化した代償といえます。なぜ支配欲が肥大していくのかといえば、問題の本質は、個人的な抑圧からくる欲求不満であり、支配欲はその代理満足にすぎず、満足に質的な隔たりがあるからです。アルコール依存に見られる依存のからくくりと同じです。
ひとは社会、政治、文化的な障害で個性化の成長と発展を妨げられると、炭次郎のように潜在能力を実現できないうえ、「私」として能力を実感できない欲求不満と、孤独の不安と無力感から逃れるために、支配力の飽くなき追求の方向に流されていってしまう弱さをもっているようです。
「したいと思うことのできない人間」をフロムは「無力」もしくは「無能力」と定義したのですが、「自分のしたいことがそもそもない」、という人が社会ではとても多いようなきがします。できない前に、特にしたいと「思う」ことがない。
解剖学者、医師であり東京芸術大学の教授であった三木成夫氏が、「思う」ことについてこう言っています。
ここで皆さん、ひとつ大切なことを申し上げます。私がこれまで教わってきたもののなかで、やはりいちばんずっしりとくるものの一つです。それは「思い」という象形文字の意味―――これはいったいなんだと思いますか?まさに「あたま」が「こころ」の声に耳を傾けている図柄です。上の「田」は・・・脳ミソをうけから見たところ、したの「心」はもちろん・・・心臓の形象です。
三木成夫 「内臓とここと」 河出出版
「思う」こと事態が稀なことになっているとしたら、理性である「頭」が「心」の声にをきこうとする姿勢そのものが稀なことになってしまっているのかもしれません。「したいことがわからない」、「最近、関心がうごかない」という人が日本では多いですが、心の声に耳を傾ける姿勢そのものをとれなくなっていることが一つの原因かもしれません。
とにもかくにも、わたしたちは、「力」を育む段階に入っていることに反論はないでしょう。それは、無惨のもつ「力」というよりは、炭次郎のもつ人間ならでは「力」です。
無力と支配
「能力」を成長させ実現できない場合に、力のもう一つの側面である「支配」を人は求めるようになるのですが、その場合ひとは典型的な性格特性をもちます。この特徴をもった人々に共通するパーソナリティは「権威主義的性格」と名付けられています。
権威主義的性格の本質は、サディスム的衝動とマゾヒズム的衝動の同時存在として述べてきた。サディスムは他人に対して、多かれ少なかれ破壊性と混合した絶対的な支配力をめざすものと理解され、マゾヒズムは自己の一つを圧倒的に強いちからのうちに解消し、その力の強さ栄光に参加することをめざすものと理解される。サディズム的傾向もマゾヒズム的傾向もともに、孤立した個人が独り立ちできない無能力と、この孤独を克服するための共棲的関係を求める欲求とから生ずる。
同上:243頁
「共棲的関係」とは、どちらか一方もしくは両方の個性(独自性・独立性)を犠牲にして成り立つ依存関係のことで、乳児と母親の関係、閉鎖的部落の村人間の関係のような自他融合的な関係をさします。対象は個人に限定されず集団、思想にもあてはまります。サディズムは相手の自由を奪い支配することで、マゾヒズムは不安を感じる自分を消し去り魅力的な人への同化を目指すことで「孤立した個人が独り立ちできない無能力と、この孤独を克服」しようとします。
この二つの性質は一つだけ現れるのではなく、一人の人間の中にどちらもみられるものだとされています。封建的な組織で上限関係をつかって後輩におもねる態度を求める人が、かれが敬愛する人物にたいしては異常なほど謙遜・卑下の態度をとる、というのはよくみられることです。
つまり、人は「能力」の発達が妨げられた場合、つまり「無能力」な場合、人間は孤独の不安から、必ず支配か服従に駆り立てられるということです。個性の別の表現といえる人間性を失った鬼が、例外なくエス・エム関係にあり、支配力に執着するのはそのためなのです。彼らは、エス・エムの関係を取らざるおえない。人をコントロールするための力を求めざるおえない。そこに選択肢はないのです。
では、「無能」な「鬼」が陥ってしまうエス・エム関係、束縛、どちらかの個性(独自性・独立性)が犠牲にならない関係とはどのようなものなのでしょうか。そんなものあるのだろうかという疑問が浮かびます。
力と尊重
支配ではないほうの「能力」の一つに尊重があります。これは、他者を独自性と独立性をもった存在だと認識でき、自発的に価値あるものとして配慮できる能力です。ひらたくいえば、相手の個と自由を喜ぶ気持ち、もしくは、良いものだと思っているので、喜んでいるフリをするということです。
なぜ、こんな当たり前のことを言い出したのかというと、尊重するということをわたしたちが思っているほど、実際、わたしたちができていないと思うからです。ハラスメントの問題も、どちらの個性・自由を犠牲にしてなりたつ(あるいは両方が)支配・服従の依存関係も、この尊重が欠如していることから起こります。
フロムは著書『愛するということ』のなかで、尊重をこう整理しています。
愛の第三の要素である尊重が欠けると、責任は、容易に支配や所有へと堕落してしまう。尊重は恐怖や畏怖とはちがう。尊重とは、その語源(respicere=見る)からも分かるように、人間のあるがままに見て、その人が唯一無二の存在であることを知る能力のことである。尊重とは、他人がその人らしく個性を発展していくように気づかうことである。したがって尊重には、人を利用するという意味はまったくない。私は、愛する人が、私のためにではなく、その人自身のために、その人なりのやり方で成長していってほしいと願う。誰かを愛するとき、わたしはその人と一体感を味わうが、あくまでありのままのその人と一体化するのであって、その人を、私の自由になるようなものにするわけではない。いうまでもなく、自分が自立していなければ、人を尊重することはできない。つまり、松葉杖の助けを借りずに自分の足で歩け、誰か他人を支配したり利用したりせずにすむようでなければ、人を尊重することはできない。自由であってはじめて人を尊重できる。「愛は自由の子」(I’ amour est I’ enfant de la liberte)であり、けっして支配の子ではない。
エーリッヒ・フロム:鈴木 晶訳:『愛するということ』:紀伊國屋書店:50項
尊重するとは、「その人が唯一無二の存在であることを知る能力」です。これは、自分の近くにいる他者が、自分とは異なる独自な世界観をもった未知なる存在で、独立した存在であることを発見できていることを前提としています。でなければ、他者のなかに「その人が唯一無二」である部分があるかもしれない、という興味がわかず、自発的に知りたいとは思えないからです。
また。尊重は、「他人がその人らしく個性を発展していくように気づかうことである」。そのために「誰か他人を支配したり利用したりせずにすむようでなければ、ひとを尊重することはできない。」というところは重要です。つまり、その人自身がまず、自分の不安解消に他人を利用しないですむように、「自分が自立していなければ、人を尊重することはできない」のです。
このように、尊重する能力は、一朝一夕で獲得できる能力ではないことがわかるはずです。
『鬼滅の刃』は、この「能力」を感じとれる名シーンがたくさんみられるところ素敵なところです。そのなかで、とくに尊重するとはどういうことなのか、ということがわかる場面があります。炭次郎と鬼殺隊の幹部・蟲(むし)柱の胡蝶しのぶの継子(後継者候補)のカナヲと炭次郎のシーンです。
カナヲは子供時代の心的外傷(トラウマ)から、彼女にすべてが「どうでもいい」と感じさせるような、無力感や無関心という問題を抱かせていました。本当は、胡蝶姉妹に愛されることで、「自分はどうでもいい存在ではない」と信じられるようになってきてはいるのですが、まだ体にしみ込んだ苦痛の記憶が発する人間への恐怖心や自己否定が根強く、心の声がまだ委縮してしまっているのです。そのため、自分のしたいことを自分で選び決断することに、たまたま運よくそういう環境で育てられなかった人にくらべて、多くの勇気を必要としています。
そんな彼女は、何か選択をするとき場合は、師範の提案に従い、コイン投げの結果にしたがって「する」・「しない」をゆだねてしまうことで、場をしのいできました。
一見、不可解で、融通のきかない頑なさにみえる彼女の「コイン投げ」は、彼女が抱えているヘビーな過去の重荷を抱えながら、なんとか社会で生きるために見出した、苦肉の策だったわけです。つまり、彼女の「コイン投げ」をなかったものとして接することも、その方法を直接否定し「コインなんかに頼っていてはダメ」と「正しい」アドバイスを早急にすることも、どちらも彼女の個性(独自性と独立性)を無視する要素をはらんでしまうのです。
炭次郎は、仕事でのケガを治すために訪れた療養先でカナヲに出会います。彼女にリハビリを手伝ってもらうあいだ、不自然な笑顔をつくる彼女に、炭次郎は心を配ります。そして、なぜ「コイン投げ」をするのか、という理由を聞いた彼は、彼女が彼女自身を「どうでもいい」、といわないで済むようなような粋なはからいをするのです。それは、「コイン投げ」をして、もし表が出たなら、これから「コイン投げ」をせずに、自らの心に沿って自分ですることを決めるのはどうか、という提案でした。
彼女が抱える過去の重荷のために頼らざる負えず、本人だってその方法が最善だとは思っていない方法、同時に傷ついた彼女を守ってきた『コイン投げ』という方法を否定せず、その彼女ならではの方法である「コイン投げ」を肯定したうえで、同時に彼女をしばる「コイン投げ」から解放し彼女を自由にしたわけです。
結果は「表」がでます。まるで自分のことのように喜ぶ炭次郎に、彼女は、「なんで表をだせたの?」という疑問を炭次郎に、さっそく自分で決めて尋ねます。尊重はこのように、人の力を引き出し、自発的な行為を促します。
炭次郎からの「偶然だよ。それに、裏が出ても表がでるまで何度でも投げつづけようと思ってたから」という返答をきいた時の彼女の表情はとっても人間らしくて、観ているこちらまで嬉しくなります。ここには、子どもでもできてしまう「恋におちる」とは次元のひとつ違う感情が訪れているように思えます。
ここには尊重があります。彼女の独自性(個別の事情があり、「コイン投げ」をしている)独立性(その「普通」でない行為をする自由)への配慮を行為で示したのです。もし、炭次郎がカナヲをそのように個性を持った人間として「見る」ことができなければ、このような発想はできませんし、配慮はズレたものとなっていたことでしょう。
与えるのか奪うのか
彼女の自由を縛り縛り上げていたものはなんなのでしょうか。「自分はとるにたりない無力な存在」、「自分なんて無視されて当然」、「私らしさなどどうでもいい」、といった無力感や自己否定です。
無力感と自己否定は、自分で何かを決断する力、表現する力を個人から奪ってしまいます。それに対して、尊重は、それとは反対方向のベクトル、つまり、相手に「あなたは無力ではない」と伝え、相手の決断する「能力」を引き上げる働きがあるのです。
フロムは、尊重を「愛するということ」の要素だといっています。愛することは、与えることしかできないものである、と言われています。炭次郎がカナヲに与えたものとは一体なんでしょうか?
それは自由です。その自由は、彼女が「おれはあなたがあなたらしくいきることが喜しい」という想いを炭次郎の言動から感じ取ったことで、彼女のなかに生まれたものです。サディズム・マゾヒズム的依存との違いはここにあります。愛は自由を与え、支配は自由を許しません。愛であればどちらの個も、つまり、どちらの「心」も縛られずにそこには残っています。フロムは、「愛は自由の子」であるといいました。わたしは、補足として、「自由は平等の子」であると付け足したいと思います。
炭次郎の人間関係のなかで見受けられる「内的つながり」とは、この平等が生んだ自由、そして自由からうまれたものだったわけです。
「鬼」の限界は愛玩
これは、無惨を含め、「鬼」にはできないことです。「松葉杖の助けを借りずに自分の足で歩け、誰か他人を支配したり利用したりせずにすむようでなければ、人を尊重することはできない。」とあるように、自分の存在意義のためであったり、不安を解消することのために相手を求めてしまっては、相手の自由の尊重などできないからです。いつまでも、手元で、手綱がひける位置にキープしておきたくなってしまう。
この意味で、無惨は「無力」であり、炭次郎は「力」があるのです。それは、自分を放置し見失った人にはもてない「力」です。相手の個別性と独立性を喜べる「力」は、自分が自分自身の個別性と独立性を無条件でいいものだと思えていない限り、難しいことだからです。上からそう尊重しなさいと命令されたり、心ある人だと「みられたいから」という動機で尊重をしてみたところで、心に伝わるものがありませんし、人によっては軽薄さを感じるかもしれません。つまり、尊重することは、社交性やマナーといった集団に属する能力ではなく、個人に所属する能力なのです。
わたしたちが誰かと親密な関係を築くとき、互いを独自で独立した存在として見れているだろうか?相手が相手らしく成長していくことを喜べているだろうか?炭次郎の築く関係ではなく、「鬼」のと同じように、愛玩を「愛」と語ってはいないだろうか?
『鬼滅の刃』は、人間関係の中にある喜びとは、本来どういったところからやってくるのだろうか、ということを思い出させてくれます。
今回はここまでです。
お付き合いありがとうございました。
参考文献
[放送局] TOKYO MXほか
「劇場版 鬼滅の刃 無限列車編」
[原作] 吾峠呼世晴
[監督] 外崎春雄
[脚本] ufotable
[キャラクターデザイン] 松島晃
[音楽] 梶浦由記、椎名豪
[制作] ufotable
[製作] アニプレックス,集英社、ufotable
[配給] 東宝,アニプレックス
[封切日] 2020年10月16日
[上映時間 ]117分
その他 PG12指定
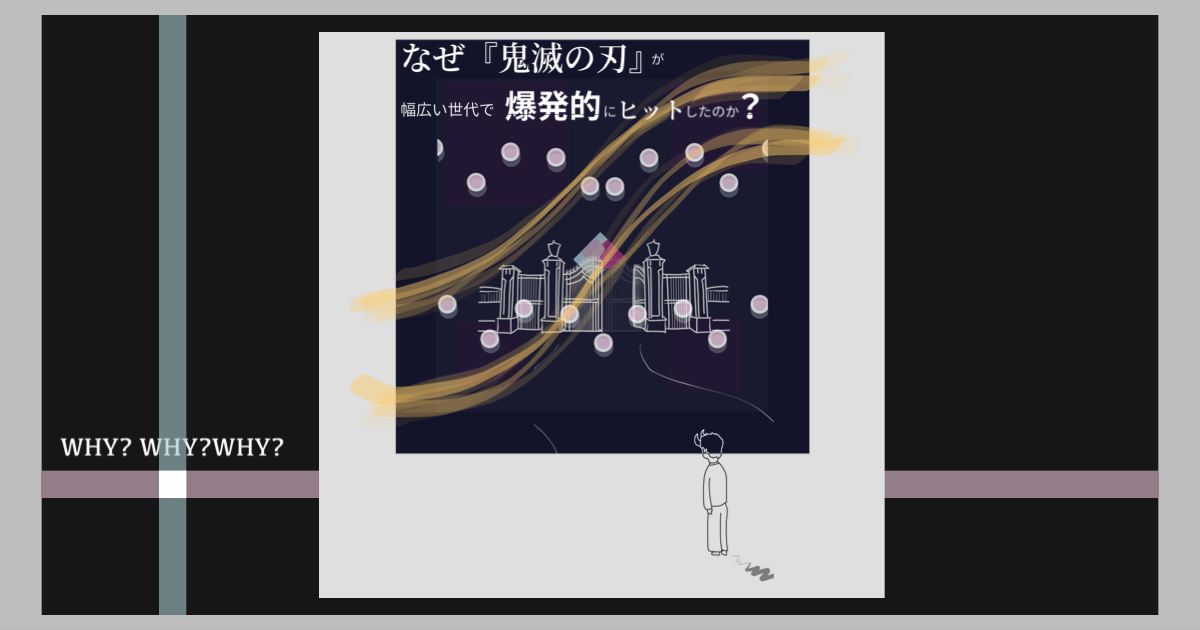
Updated on 4月 19, 2021
なぜ『鬼滅の刃』が幅広い世代で爆発的にヒットしたのか? その7 『鬼滅』の鬼からみる現代人の悲哀
こんにちは、matsumoto takuya です。今回も前回にひきつづきシリーズ「なぜ『鬼滅の刃』が幅広い世代で爆発的にヒットしたのか?」をおおくりします。
前回の投稿で、「力」には「能力」と「支配力」という2種類の意味があり、炭次郎には「能力」が無惨には「支配力」があり、ひとは「能力」をえられない場合に、「支配力」に駆られる傾向があるのだというところに行きつきました。わたしたちは炭次郎がもっている力に惹かれ、無惨のほうの力にはお腹いっぱいでうんざりしている。
今回は、『鬼滅の刃』のカナヲや「鬼」をみながら、鬼とおなじように「支配・服従関係」から逃れられない現代人の姿に迫っていき、『鬼滅の刃』という少年漫画原作の物語が、社会人層である20代、30代そして40代にどうしてハマったのかという理由を探っていきたいと思います。
ではそっそくいってみましょう。
『鬼滅』カナヲからみる無力感の原因
ここで先にとりあげた鬼殺隊のカナヲについて、少し踏み込んでみていきたいと思います。
彼女は、幼少の頃からネグレクトと虐待を受けたあげく、親に売られた孤児でした。親にとって彼女は価値のない、生活を傾かせるだけの役にたたない重荷であり、売ることで初めて役にたつ「モノ」であったのです。
スウェーデンの精神学者で世界的にベストセラーとなった『スマホ能』の著者であるアンデシュ・ハンセンは他人を模倣する仕組みついてこう述べています。
ミラーニューロンは他人を模倣することで学習する脳の神経細胞だ。新生児に舌をだしてみせると真似するのは、このミラーニューロンのおかげだと考えられている。ミラーニューロンは動作を習得するときにだけに活躍するのではなく、脳の複数の領域に存在する。そのひとつが体性感覚野で、「他人がどう感じているか」を理解する領域だ。
―――この領域を刺激するのは痛みだけではない。他人の喜びや悲しみ。恐怖もだ。つまり、自分の身体と心の間、そして自分と他者との間にも橋を架けるようなものだ。他人を理解したいという生来の衝動は、心の理論(theory of mind)とよばれる。
アンデシュ・ハンセン『スマホ脳』:久山葉子:発行所 新潮社
まだ客観能力が未発達で、何も知らない全ての子供と同じように、子どもだった彼女は、親が彼女の感情表現や意思表現した時の態度を模倣し学んでいきます。身近な人が、自分の意思表示を悪いものである、という反応をかえせば、良くないものであるという判断をせざるおえなくります。近くの大人が感情表現に反応してくれなかったり、意思表示にたいして喜んでいない反応をしたりしても、そこから子どもは学んでいきます。
このときに、彼女がそのような大人と共にいきていくことを可能にしてくれたと同時に、後の彼女を縛り上げていくものが、近くの大人から学んだ「どうでもいい」という「私」への軽視と不信の態度です。この態度は、無力感をひとのこころに植えつけ、その語の人生に影響をあたえてきます。自己否定的な態度が親や周囲の大人から影響されたことでみにつけてしまった後天的なものであるとはつゆ知らず、それが自分の生来の性格なのだと錯覚するようになるからです。
虐待やネグレクト(意思の無視も含む)が残酷なのは、ひたすらその子供の肉体的であれ、精神的であれ、その人の意思を無視し続けることで、自分が自分自身の感じたこと、思ったことへの態度を歪めてしまうからです。それが、その後の人生を生きる大きすぎる足かせとなってしまう。カナヲは極端なケースですが、自己肯定感の低さはその人だけの責任ではなく、その親だけや、その親のいる社会の門題でもあり、ひいては、わたしたち一人一人の問題なのです。
毒親と子供の関係も、パワハラ・モラハラをする上司と部下の関係も、DVの関係も、基本的には、意思への無配慮を内容にもち、個人に無力感を植え付けます。文化が、意思表示することをけむたがり、相互理解を試みる経験の場がえられず、内向きな閉じた社会の場合、他者の意思を配慮する能力の発達を妨げてしまうことなります。
かれらが大人となったとき、子どもや、弱い立場の人に影響をあたえてしまうことになるのです。
虚しいアクセサリー的人間関係
人に無力感を植えつけるものは、カナヲのケースのように他人を役に立つかで値踏みする態度でもあるのですが、これは、無惨や「鬼」が他の「鬼」を見る態度と同じです。
そういう場合、だれかと一緒にいる理由がその人らしさではなくなります。「世間体が得られるから」、「友達がいる状態をもつことで安心したいから」「役に立つ」から「ウケがいい」からといった不安解消や見栄、アクセサリー的な動機で対人関係を結ぶことになる。そのひとが興味があるのは、その人自身ではなく、その人から得られる世間体、不安解消といった副次的な利益のみとなってしまいます。そこにはそもそも、その人自身を理解したい、配慮したいという、「こころ」がないのです。
これはあくまで私的な領域のはなしで、商売は利害関係がベースであるビジネス関係のはなしではありません。しかし、『鬼滅の刃』の「鬼」たちの関係をみていると、私的な領域までそうなってしまった場合は、やっぱり虚ろで寒々しいものなのだと改めて実感させられます。
「鬼」は人を「鬼」に変える
その人らしさである意思を重要なものとみて配慮できるか、その人らしさである意思を役に立たないうっとうしいものとして無視するのか、それが炭次郎と無惨のちがいです。人間の人間たる部分へ喜べる能力が育っているか、喜べる能力が育っていないのかという視点からみれば、ここでも炭次郎は「力」があり、無惨は「無力」といえます。
「無力」な人間はより弱い立場の人間を自分と同じように「無力」な存在に捻じ曲げ、既存の権力にたいして無批判に従う「人形」のような存在にかえてしまう影響力をもっています
『鬼滅の刃』の世界では、鬼舞辻無惨が人間に彼の血を直接的に混入させることで、劇的に人間を「私」をうしなった「鬼」にかえます。わたしたちの現実の社会では、「私」を失った人たちの空気感そして、権力がともなう閉じられた組織の中での彼らとのやり取りの中で、ゆっくりと自立力を削がれていき、自覚なく決断するための「私」を失っていくのです。能力の成長・発展を妨げられた人間は支配にはしり、権力は人を保身に走らせます。結果として、社会に日和見主義と閉塞感と鬱々とした空気が漂うことになります。
『鬼滅』の鬼からみる現代人の悲哀

自分を見失っていた人間が、死ぬ直前に、「私」として生きられなかったことに気がつき、そう生きようとしなかったことを後悔する、これほどの後悔はないとわたしは思います。
炭次郎は滅び去る直前の鬼に強烈な悲しみをかぎとり、彼らの死の際に同情を示します。彼が感じ取った悲しみは、「鬼」の後悔です。「鬼」がどういうことに後悔していたかというと、それは、人間を食べ足りなかったというものでもなく、もっと人間や下級の鬼を支配したかったというわけでもなく、「私」らしく生きたかったのにそれができなかった、という後悔です。
無惨から「私」らしく生きるための前提条件を奪われ、代理満足である人間への消費欲、支配欲や優越感を得ることに一生を費やしたあげく、まさに命が尽きる那刹に鬼は人間の頃の自分を思い出し、自分の人生はなんだったのかと後悔する。こんな、つらいことはないでしょう。「鬼」は、そのまま人間性を思い出さなかったほうが苦しまなかっただろうに、という思いと、最後は「鬼」ではなく人間として逝けたのがせめてもの救いだったのかもしれないという思いが、同時におとずれたのを覚えている、『鬼滅の刃』ならではの印象的なシーンでした。
炭次郎は、その人間として残り香のような感情をかぎとり、踏みつけにするものではなく、大切にしてあげたいと思ったわけです。それは悲しみではありますが、「鬼」が忘れてしまった、人間だけがもつ感情、人間としての誇りを思い出したからこそ感じることができる感情だったからです。
「鬼」は、炭次郎に自分さえも忘れていた「私」に気が付いてもらえた安堵により、大粒の涙をこぼしながら塵となります。ほんとうの人間の彼は、自分(自意識)にさえ切り離されてしまい、「鬼」となって人生をつぶしている間も、ずっと人知れずに心の奥のほうで、気が付いてくれることをひたすら待っていたのです。
鬼は炭次郎に自分さえも放置してきた「私」に気が付いてもらえ安堵し大粒の涙をこぼしながら塵となります。ほんとうの人間の彼は、自分(意識)にさえ切り離されてしまい、鬼となって不安にかられ力を強迫的に追い求めることに人生をつぶしている間も、ずっと人知れずに心の奥のほうで気が付いてくれることをひたすら待っていたのです。
この「鬼」の後悔は、多かれすくなかれ、ある程度生きた、すべての人にあるのではないかとわたしは思います。巨大な経済メカニズムに左右される会社、その会社という官僚的機構のもとで賃金労働のもと分業の分業ともいえる細分化された仕事内容、代えがきくことがありきの仕事をさせられている状況で、愛想笑いしている学校で、自分を心の底の底にはなんらかの「後悔や無力感」が多少なりとも溜まっていない人がいるとしたら、むしろ逆の意味で怖さを感じます。そして、この後悔や無力感は心の底のほうに、本人さえも気づかないほどの静けさで、澱のようにしんしんとと積もり溜まっていく。
「鬼」は死に際で、自身さえも忘れていた「私」に、炭次郎から人間としての敬意と配慮を示されたことで、「人間性」が息をふきかえします。「だれからも気づいてもらえなかった「私」に気づいてもらえた、しかも配慮してくれる、そういう人が目の前にいるのだ」ということを実際に感じ、最後は人間として浄化するように朽ちていくシーンは心に残ります。この場面は、日本の伝統芸能の能の魂鎮につうじる美しさがあります。
この「鬼」の悲哀と消滅のシーンは、現代、とりわけ日本の抑圧必死の環境の中でなんとか生き抜く社会人層をも惹きつけた秘密の一つではないでしょうか。
炭次郎の他人のなかに個を見る力、この尊重という能力がどういう力なのか、といのがこのシーンからもよくわかります。このちからは、支配力のように人の人間性を壊す働きではなく、ひとの内側に「なにか」を生み出す働きがあるのです。「私」でいて「これでいいのだ」と腹から思える時にかんじる「なにか」です。それは、人間が他者との関係のなかで経験しうる最も豊な感情です。
一番い痛ましく可哀そう存在は、本当に大事なものを犠牲にし、そのことさえも忘れて代理満足の確保に奔走するうちに、唯一無二の人生が終わってしまった、「私」をうしなった「鬼」なのです。たった一瞬のやり取りですが、このシーンには上辺の関係にはない「人間」と「人間」だけができる「対話」とよべうるものが確かにえ描かれていたとわたしは思います。生きている限り、たとえ「私」を失おうとも、死ぬ最後の最後まで、人の心は消えたわけではなく、そのひとの中で気づいてもらえるのを待っている「鬼」の姿と、自分を放置し、忘れてしまいがちな現代人の姿がわたしにはダブって映ります。
卑屈と合理化と鬼の魘夢(えんむ)
無惨タイプの人が上の立場に立つ集団では、下の立場にあるものがどういう態度をとるにいたるのか、ということがわかりやすくみてとれる場面があります。『アニメ『鬼滅の刃』第二十六話 新たなる任務』で無惨が直属の部下である下弦の「鬼」たちを招集し、出来の悪さへの釈明を求めた場面です。
無惨にたいして下弦の「鬼」がとった態度は4つです。意見をいうか、迎合するか、逃走するか、はじめからあきらめなすがままにされるか、です。このうち、意見をいう、迎合する、逃走するという選択肢を選んだ「鬼」は無惨に惨殺され、下弦の「鬼」のうち生き残ったのは、はじめからあきらめなすがままにされる、を選んだ下弦の「鬼」のトップである魘夢(えんむ)という「鬼」でした。かれは、意見をいう、迎合する、逃走する、何らかの意思を示した「鬼」たちが無惨に蹂躙される様子を傍観しながら、「おろかだなぁ」と優越感にひたりながらそうつぶやきます。
一見、魘夢(えんむ)は生き残れたこともあり、一番賢い選択をしたようにうつります。しかし、はたしてかれは「力」があるといえるのでしょうか?実際かれはそれ以外の選択肢がなかったのだという視点からみたとき、彼の意見はもっとも「無力」な人間がとりうる態度ではないのかとも考えられるのです。
オーストリアの精神科医、心理学者のヴィクトール・E・フランクルはアウシュビッツの被体験を綴った著書『夜と霧』のなかで、こう言っています。
・・・人間の命や人格の尊厳などどこ吹く風という周囲の雰囲気、人間を意思など持たない、絶滅政策の単なる対象としてみなし、個の最終目標に先立って肉体的な労働をとことん利用しつくす搾取政策を適用してくる周囲の雰囲気、こうした雰囲気のなかでは、ついにはみずからの自我までもが無価値のものに思えてくるのだ。
強制収容所の人間は、自ら抵抗して自尊心をふるいたたせないかぎり、自分はまだ主体性を持った存在なのだということを忘れてしまう。内面の自由と独自の価値観を備えた精神的な存在であるという自覚などは論外だ。人は自分を群衆のごく一部としか受けとめず、「わたし」という存在は群れのレベルにまで落ちこむ。きちんと考えることも、なにかを欲することもなく、人々はまるで羊の群れのようにあっちへやられ、こっちへやられ、集められたり散らされたりするのだ。
・・・
強制収容所に入れられた人間が集団の中に「消え」ようとするのは、周囲の雰囲気に影響されるからだけでなく、様々な状況で保身を計ろうとするからだ。被収容者はほどなく、意識されなくても五列横隊の真ん中に「消える」ようになるが、「群衆のなか」にまぎれこむ、つまり、けっして目立たない、どんなにささいなことでも親衛隊員の注意をひかないことは、必死の思いでなされることであって、これこそは収容所で身を守るための要諦であった。
『夜と霧』 ヴィクトール・E・フランクル 池田香代子訳 株式会社みすず書房
強制収容所の人間としての権利、つまり、個の表現をはく奪さた被収容者は、このような「はなから諦める」という「鬼」と同じ精神状態に陥るのです。
このように、「無力」な人間が何らかの地位についたとき、下の立場の人間に実質的に「はなからあきらめなすがままにされる」という選択肢以外をとりあげることで、下の立場の人の人間的な成長を妨げ、その人の主体性を奪い、受動的な存在に変えていきます。
受動的な存在になった人間は、「私」という主体を失ったことからくる自身の存在の弱小感をどうにかするために、半分無自覚な状態で、「合理化」という後付けの理由をこしらえて精神面の安定をはかろうとすることが知られています。魘夢(えんむ)のつぶやきは、この「合理化」の典型ではないかと考えられます。かれは、表面のメッキをはがせば、ただ臆病で無力な存在でしかないのです。
悲哀のチャネル
今の日本社会の組織・会社ではたらく場合はどうでしょうか。ヴィクトール・E・フランクルの強制収容所の被収容者についての文章は、仮に、今の日本の組織で働いている人間がもつようになる特徴を言っているのだ、と言われたとしても違和感がありません。
特に「自ら抵抗して自尊心をふるいたたせないかぎり、自分はまだ主体性を持った存在なのだということを忘れてしまう。内面の自由と独自の価値観を備えた精神的な存在であるという自覚などは論外だ。人は自分を群衆のごく一部としか受けとめず、「わたし」という存在は群れのレベルにまで落ちこむ。」という記述は、日本のあるべき社会人像のデフォルトとなってしまっている印象さえ持ちます。
例えば、自分の業務をこなしたあとも会社に長時間いることや、その後のプライベートの時間をさいて先輩や上司の気分次第の飲み会に参加して、どれだけ上席の人の気分を気持ちよくできるか、といったような、どれだけ私的な時間を会社のために使っているのか、ということが暗んに評価されて、その不文律に従うことが処世術てきに出世しやすい慣習と環境があります。そのような習慣で報奨が伴えばおのずと、懐疑的な精神を持っている自分がバカらしくなるのは当然です。環境も慣習も、いいも悪いも人をかえるものです。
かつては、会社が自分の存在意義や正当性を与えてくれ、「守ってくれている」という信仰のようなものが支えとなっていました。これは、自他の区別が未分化な西洋の中世の精神性に似ています。しかし、中世のような絶対的な身分制度も社会基盤、経済基盤などは近代以降の資本主義のもとにはありません。ついで、日本の終身雇用制はとうに崩壊し、経済はより流動的になっています。もう、会社に自分を犠牲にして尽くしても、「守ってもらえる」という幻想を信じていられるのはごくわずかな人たちだけでしょう。
ここから言えることは、個々人を生きずらくさせる閉塞感や自発的な活動を妨げている日本の鬱々とした雰囲気は、既存の組織で働いている上の立ち場に立っている個々の人間の主体的な成熟度・質に影響されているということです。なぜなら、人が集団でなにかをする以上、権力が伴ってくるからです。主体の確立が不十分なものが上に立ち、下の人は上に影響をうけて日和見主義に陥り、その世代はさらに下の世代へ、、、といった具合に劣化の連鎖が起こっている。
日本の閉塞感の問題はつきつめていくと、わたしたち一人一人の個人的な「能力」の質の問題に行きつきます。そして、これは教育によって新しい世代に上から与える方法だけでは実現せず、実際の社会にいる人間が、「私」として生きる以外には本質的には解決できないことです。これは、政治家の質、メディアの質、文化の質にも言えます。これらのいずれかが酷いといわれているなら、それは、その社会の現役である一人一人の質が酷いのだという厳しい現実を見ないわけにはいかなくなります。政治家は国民が選び、メディアのテーマは視聴率が決めるからです。
そんな日本でも、少数派とはいえ、スポーツやビジネスや研究者、アーティストの中で突き抜けたほんの一握りの人たちは、日本で育ちながら、因習にたいして盲従せず、自分の言葉で話す姿勢をしめし、自他の区別を意識している人がたしかにいます。自分が保身から謙遜を超えた卑下をしたり、密かに見下しマウントをとって優越感にひたるよりも、自分が好きだと思ったことの発展のために、好きになってもらうために信念をもって活動をしています。そういう人を見つけると、わたしはそのジャンルにたいして興味がないにもかかわらず、励まされたような気持になり、応援したくなります。
『鬼滅の刃』にハマった20代、30代、40代の社会人層は、「自分はまだ主体性を持った存在なのだということを忘れ」、「強制収容所に入れられた人間が集団の中に「消え」ようとする」ようになりかけている自分の姿と、「私」であったことさえも忘れ、代理満足で自分をごまかし、意思などはじめからなかった「もの」のように無視され続ける「鬼」の悲哀に、同情というチャネルで共感しているのかもしれません。
とはいえ、、、
とはいえ、いやいや、プライベートではそれはありうるけど、社会人としてそれは青臭い甘えだ、という意見があるかもしれません。たしかに、このあたりは検討に値します。無惨と鬼との関係は、私的な関係ではなく、ビジネス関係なんだと見ることもできます。権力が伴ってくる組織で働く際、私たちはこの問題をどうやって考えて整理していけばいいのでしょうか。社会人になることこは精神の自由、つまり「私」をあきらめることなのでしょうか?
話はこの、自由と服従の問題にうつっていきます。
次回の話は、自由と服従の問題にうつっていきます。
お付き合いありがとうございました。
参考文献
[放送局] TOKYO MXほか
「劇場版 鬼滅の刃 無限列車編」
[原作] 吾峠呼世晴
[監督] 外崎春雄
[脚本] ufotable
[キャラクターデザイン] 松島晃
[音楽] 梶浦由記、椎名豪
[制作] ufotable
[製作] アニプレックス,集英社、ufotable
[配給] 東宝,アニプレックス
[封切日] 2020年10月16日
[上映時間 ]117分
その他 PG12指定
「自由からの逃走」
[作者] ERICH FROMM
[訳者] 日高 六郎
[発行者] 渋谷 健太郎
[発行所] 株式会社 東京創元社
「スマホ脳」
[著者] アンデシュ・ハンセン
[訳者]久山葉子
[発行所] 新潮社
「心を開く対話術」
[著者]泉谷 閑示
[出版社] ソフトバンククリエイティブ
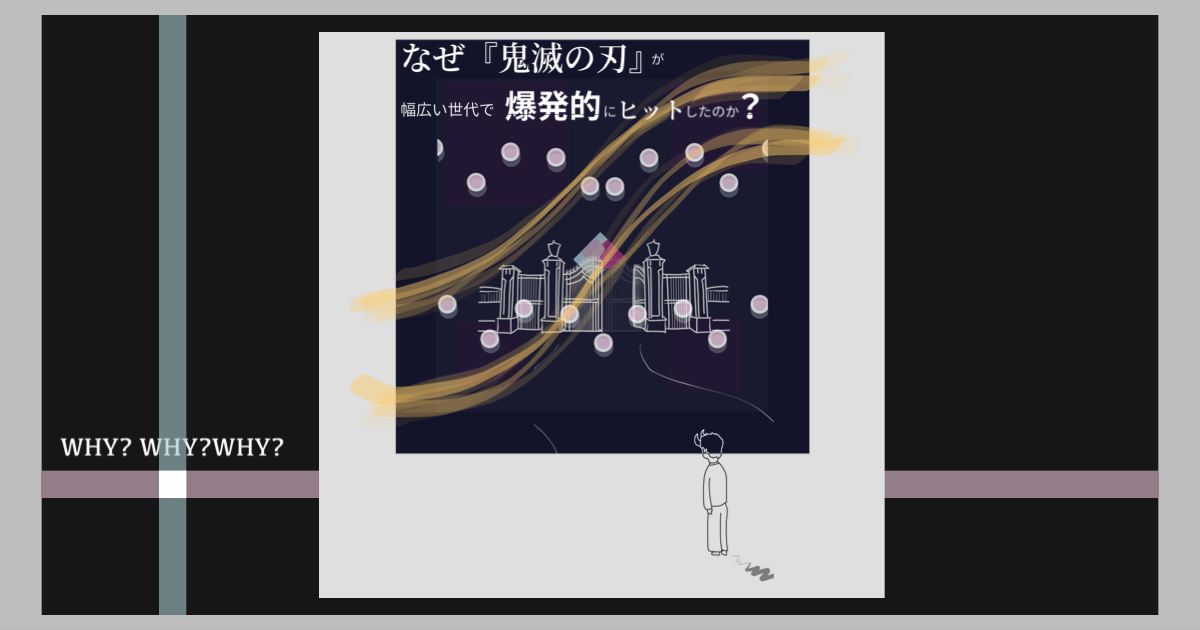
Updated on 4月 16, 2021
なぜ『鬼滅の刃』が幅広い世代で爆発的にヒットしたのか? その5『鬼滅』炭次郎と無惨からみる愛と支配
こんにちは、matsumoto takuya です。今回も前回にひきつづきシリーズ「『鬼滅の刃』が少し引くほど大ヒットした理由とは?」をおおくりします。
前回の投稿までは、歴史・時間という縦の軸と西洋・日本といった地理的な横の軸、そして、それらを社会の下部構造と人々の社会心理の観点から、「『鬼滅の刃』が少し引くほど大ヒットした理由とは?」という理由の答えをマクロの視点でみていきました。
以降の投稿では、『鬼滅の刃』の内容にふみこんで、竈戸炭次郎をはじめとした主要な登場人物と無惨ら鬼たちがそれぞれに築く人間関係にスポットをあてながら、個別具体的なミクロの視点で『鬼滅の刃』が少し引くほど大ヒットした理由を探っていきます。
今回は、普通の漫画やアニメの敵キャラクターのように他人事とはおもえない鬼の秘密をさぐりながら、『鬼滅の刃』が世代をこえて異常なほど大ヒットした秘密に迫っていきたいと思います。
ではそっそくいってみましょう。
『鬼滅』炭次郎と無惨からみる愛と欲望
他人を尊重できるような「大人」は、わたしたちの身近に実際どれくらいいるのでしょうか。
最近は、ひと昔前に比べて露骨な上下関係の押し付けは減ってきたかもしれません。しかし実情は、上の世代はホントのところは納得していないが、外圧が強まったから、我慢するようにしている、というのがリアルなところではないでしょうか。上の立場の人間は表面上はなめらかなようで、実は不満をためこめんでいるような気がします。もしかしたら、他人を尊重するということ、は子供のころ教わったほどには簡単なことではないのかもしれません。
『鬼滅の刃』では、この「大人」ではない状態の人がわんさかでてきます。「鬼」のかたがたと、「鬼」の親玉、鬼舞辻無惨です。この、鬼仏辻無惨の築いていく人間関係(「鬼」ですが)と、主人公の竈戸炭次郎の築いていく人間関係は、とても対照的に描かれています。
わたしは、竈戸炭次郎の築く人間関係よりも、鬼の親玉である鬼舞辻無惨側が築く「鬼」同士の関係のほうが、わたしたちの社会のリアルな人間関係に近いのではないかと考えてしまいます。その理由を述べる前に、炭次郎の築く人間関係と「鬼」の親玉である無惨が築く鬼同士の関係を、少し詳しく見ていきたいと思います。
炭次郎は、自分独自の感覚・感情に耳をすまして、そこから感じたものをもとにして自ら考え、それを信念として活動しています。そして、自分への態度と同じようの、他人の独自性と独立性を尊重し配慮をします。しかし同時に、組織内では基本的に従順ですが、必要とあれば、たとえ立場が弱い場合であっても、はっきり意見を表明します。相手側は、まさにいいも悪いもふくめ多様な反応を示すなかで、すこしずつお互いのペースで関係を深めていきます。
それに対して、鬼舞辻無惨は、個別の「鬼」について独自性(感覚や考え)や独立性(ペース)にまったく配慮するそぶりをみせず、部下の意見をたかが知れたものと決めつけ、逐一相手の「間違い」を指摘し自分のやり方に「鬼」が従うように強制します。その反面、彼が「鬼」にとてもやさしくなる場合があります、それは「鬼」が支配でき自分に役立つ場合です。相手側の「鬼」は無惨の力に圧倒され、無惨に自分の意見や自由の一切を譲りに、かれの望みを自分の望みとし献身しようとします。
わたしたちははたして、どちら側に近いでしょうか。
こう書きだしてみると、ふと、疑問がわきます。はて、一部の「鬼」の鬼舞辻無惨への献身は愛なのではないか、という疑問です。わたしたちの身近な感覚では、この、他人のために自分をすてて尽くすことは絶対的な「愛情」行為だと賞賛されている風潮があるようにさえ感じれるらからです。
他方で、DV(家庭内虐待)を受けている女性(男性も含める)は、しばしばこの「愛情」を暴力をふるうパートナーに示しますし、虐待をうけている子供も、親に対してこのタイプの「愛情」を示すことはよく知られています。それでも、程度の差はあれ、わたしたちの人間関係でも、部分的に「エムっ気」という形でしばしば見かけられるものかもしれません。
このタイプの鬼と無残の関係に愛はあるのでしょうか?そもそも、愛というものが巷でいわれるようになったのは、西洋文化が流入してきたここ150年あまりのことで、捉えどころがいまいちですし、話題に出すだけで滑った空気がながれるので、日本では曖昧なまま放置されているものの一つかもしれません。エーリッヒ・フロムはマゾヒズムが示す行為についてこう述べています。
フロム・・・エーリッヒ・フロム。20世紀を代表する社会心理学者。社会のなかの個人の自由と孤独を専門とする。最近著書『愛するということ』が日本でリバイバルしている。
もし愛とは、ある特定の人物の本質に対する、情熱的な肯定であり、積極的な交渉を意味するのであれば、またもし愛とは当事者二人の独立と統一性とに基づいた人間同士の結合を意味するのであれば、マゾヒズムと愛は対立するものである。愛は平等と自由に基礎づけられる。もし一方の側の服従と統一性の喪失にもとずいているならば、いかにその関係を合理化しようと、それはマゾヒズム的な依存に他ならない。サディズムもまたしばしば愛のよそおいのもとにあらわれる。もし当人のために支配するのだと主張されるならば、支配することも愛の表現だといえよう。しかし、本質的要素は支配の享楽にほかならない。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社:179頁
支配の対岸にあるのが愛であり、それは、お互いの自由という独立性への尊重と、それを可能にする平等を用意できているかが重要なようです。「鬼」に服従を強いることで、相手に依存させ自立する力を奪う無惨と、自らを消し去り無惨への献身をささげ、寄りかかる「鬼」との関係には恋に似た何かはあっても愛ではなく依存に近いようです。同じことが、DV関係の男女や虐待・ネグレクトのある親子のあいだにも言えます。
フロムは、マゾヒズムに対応するサディズムについてこう言っています。
サディズム的人間は、彼が支配していると感じている人間だけをきわめてはっきりと「愛し」ている。妻でも、子でも、助手でも、給仕でも、道行く乞食にも、かれの支配の対象にたいして、彼は愛の感情を、いや感謝の感情さえもっている。彼の生活を支配するのは、彼らを愛しているからだと、かれは考えているかもわからない。事実かれらはかれらを支配していいるから愛しているのだ。彼は、物質的なもので、賞賛で、愛を保証することで、ウィットや才気で、関心を示すことによって、他人を買収している。かれはあらゆるものを与えるかもわからない――――ただ一つのことをのぞいて、すなわち自由独立の権利をのぞいて。・・・かれにとって、愛とは、自由を求めながら、とらえられとじこめられることを意味する。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社:164項
このサディズムとマゾヒズムの傾向は、孤独にたえられないこと、もしくは自分がないことからくる不安・無力感からきており、いずれも、どちらかのもしくは両方の個性と自由が失われていることを特徴としています。
もちろん、人間が完璧でない以上、サディズム・マゾヒズムが関係に入ってこない人はまずいないでしょう。しかし、そちらに偏ってしまうことは、愛とは対岸に位置するものであることは、無惨が築く「鬼」との関係を見ているとよくわかります。
テレビ等で、欧米圏で成功を収めた人へのインタービューを見ていると、「子弟関係であり友人」と紹介されてと恩師に当たる人物が紹介されているのをみかけますが、日本の師弟関係ではめったにそういう表現はみられません。上下関係や暗黙のルールが私的な領域にくいこむので、友人関係の余地をうむ個人間の平等が残らないからかもしれません。
フランス共和国のスローガンが、「自由、平等、友愛」であることは有名です。ここに「自由」があるのは興味深いことです。愛は支配からは生じえないことを再確認するかのように、一番先頭に自由がおかれ、次に自由の側面である平等がつづき、最後にようやく愛がおかれています。これは、偶然の思い付きではなく、長い人間の歴史で繰り返されてきた痛ましい過ちや経験則、キリスト教文化圏の長い歴史のなかで積み重ねられ、導き出された順番であり、歴史の論証に裏打ちされた標語だったわけです。
ちなみに、自由という概念は、150年ほど前の日本にはありませんでした。約150年前の日本には、わたしたちの使っている「自由」という言葉すらなかったのです。福沢諭吉が英単語「freedom」を日本語に訳す時に、「自らが由(よし)とする」という意味から自由という語を造語したそうです。当時の日本人は、自由などという抽象的な内容の言葉を急にあたえられ、実際にそうやって生きている人さえ見たことがない状態で自由と出会いました。その分、混乱と期待、恐さとわくわくが同居する気持ちが人々の胸の内にあったはずです。
『鬼滅の刃』の舞台である大正時代はまさに、自由・平等・愛についての萌芽が、市中にいる個人のなかに芽生えはじめた始まりの時代だったのです。
自分をわすれることで安定をてにいれた元人間
ここで『鬼滅の刃』にでてくる「鬼」についてスポットをあてていきたいと思います。それも雑魚ではなく、力のある「鬼」にスポットを当てていきます。
「鬼」は元々は人間で、個人的な苦悩を持っていました。その苦悩に無惨がつけこみます。無惨は悩んでいる人間に、自分へ服従するかわりに力を与えます。「鬼」となったものは無惨の血を自身に取り込み、力を与えられることで苦悩から解放されます。無惨の血ををりこむたびに、もしくは、人間を食べれば食べるほど「鬼」として強くなっていきますが、それに反比例するかたちで、人間であったころの「私」を忘れていきます。「鬼」は、人間らしい苦悩から解放されたうえに、不死身の肉体を手にしたにもかかわらず、無惨に見捨てられたくないこと、または、いつも自らの力に不足を感じる、といった不安にかられ、力を際限なく求めるようになります。
「鬼」は、力を手にする代わりに人間だった頃の本当の自分を喪失していきますが、抑圧された内面世界では、本当は人を喰らうのではなくて、内実のある人間関係を求めていた、あるいは、人に個性をもった「私」として認めてもらいたかった、という苦悩が後に露わになります。「鬼」となった後も、人間の苦悩は消え去ったのではなく、おおいのようなものによって見えなくしていただけだったのです。「鬼」の精神面では、本来の欲求(人間性)がにせの欲求(無惨の精神性)に置き換えられていたのです。
ここで、先ほど引用したフロムの近代人についての記述をもう一度ひいてみます。
かれは、もし自分が欲し、考え、感ずることを知ることができたならば、自分の意思に従って自由に行動したであろう。しかし、彼はそれ知らないのである。かれは匿名の権威に協調し、自分のものではない自己をとりいれる。このようなことをすればするほど、彼は無力を感じ、ますます同調をしいられる。楽観主義と創意のみせかけにもかかわらず、近代人は深い無力感に打ちひしがれている。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社
この記述にある、「匿名の権威」を「無惨」に、「近代人」を「鬼」に入れ替えると、そのまま「鬼」の記述となることに気がつくはずです。
「鬼」は、力を求めて無惨の価値観である人食や、彼の血にすがればすがるほど、無惨の価値観を自分のものだと思いこむようになり、人間だったころの自分、つまり「私」を忘れていきます。わたしたちはどうでしょうか。孤独の不安から逃れられる代わりに、「匿名の権威(「世間や小集団」)」へ同調を繰り返す結果、「自分のものではないにせの自己(匿名の権威)」が自分だと思いこむようになり、自らの個性、つまり「私」を忘れていきます。
近現代人が典型的に陥りやすい精神状態は、本来の欲求(個人)がにせの欲求(世間・小集団からの評価)に自覚なく置き換えられていくことであり、これはまさに鬼と同じ精神状態にあると言えてしまうのです。
フロムは現代人の胸に抱えた不自然さを、こう鋭く考察しています。
思考や感情や意思について、本来の行為がにせの行為に代置されることは、遂には本来の自己がにせの自己に代置されるところまで進んでいく。本来の自己とは、精神的な活動の創造者である自己である。にせの自己は、実際に他人から期待されている役割を代表し、自己の名のものとにそれをおこなう代理にすぎない。たしかに、ある人間は多くの役割を果たし、主観的には、各々の役割においてかれは「かれ」であると確信することができるであろう。しかしじっさいは、彼らは全ての役割において他人から期待されていると思っているところのものであり、多くの人々は、たとえ大部分のものではないにしても、本来の自己はにせの自己によって、完全におさえられている。
同上:224項
自分では自分で決めた選択の動機が、実は「他人ウケ」のためであること。それが現代人の陥りやすい典型的な特徴ですが、「それは本来の自己がにせの自己に代置され」たものであったわけです。処世術として取り込んだはずの他者の視点が、いつしか、自分の感覚、感情や想い、そして考える力を縮委させてしまい、主人のようにふるまっているということです。
フロムはこう続けます。
自己の喪失とにせの自己の代置は、個人を烈しい不安の状況になげこむ。かれは、本質的には、他人の期待の反映であり、ある程度自己の同一性を失っているので、かれには懐疑がつきまとう。このような同一性の喪失から生まれてくる恐怖を克服するために、かれは順応することを強いられ、他人によって耐えず認められ、承認されることによって、自己の同一性を求めようとする。かれはかれがなにものであるかは知らないが、もし彼が他人の期待通りに行動すれば、少なくとも他人はそれを知ることになるであろう。そしてもし他人が知っているならば、かれらの言葉を借りるならば、かれも知っていることになるであろう。
近代社会において、個人が自動機械になったことは、一般のひとびとの無力感と不安とを増大した。そのために、かれは安定をあたえ、疑いから救ってくれるような新しい権威に、たやすく従属しようとしている。
同上:225項
孤独の不安から逃れようと「私」を放置しなんらかの集団に同調・同化をしていくと、「私」として社会なかで活躍することで実感できる自身の能力の手ごたえを感じられず、無力感と不安を増大させ、それがまた「私」を・・・といった具合に、人は無限ループに閉じこめられます。
この意味で、強力な同調圧力を抱える日本で育った人が、看板にたよらない本当の意味での自信を育みにくいのはしかたないことかもしれません。
SNSで「いいね!」が以上に気になってしまうからくりはここにあります。最近の小中学生が、LINEなどのSNS上で「いいね」を半強制的にに友達からもらえるような遊びに躍起になっている、というニュースをネットでよく見かけますが、わたしは無理もないことだと思っていました。決して少なくない数の子供の身近にいる大人が、子供以上に、そうだからです。大人と子供の違う点は、それを偽装する術を知っているか知らないかの差でしかない。
最近の子どもは、承認欲求が尋常ではない、とよく言われているようですが、そもそも、自分がない人がなぜ「世間」に従うのかといえば、他人からの評価が得られるからです。つまり承認欲求の代理満足がみたされるからです。最近は、「世間」の弊害のほうが目立つようになり、子どもの外的環境は以前にもまして精神的な独立をするように個性を成長させることに肯定的な環境にあります。本当は、他者に個性をもった「私」を認めて欲しいところを、それが日本の環境ではどうも得られず、その代理満足として、SNSを使った表面的な承認で満たしていると考えれば、日本の状況の本質は、変わっていないのではないでhそうか。親の世代とちがうことは、「私」を放置してなんらかの多数派に服従するのはやめましょうというアンチ「世間」の教育を、割とはっきりとうけていることです。
人は「私」を見失えば、自分が何をしたいのかわからなくなり、世界に対して自分らしい関心が動かなくなります。いいかえれば、同調元の価値観にそって人生を「選んで」いくことになります。意思なき人生です。フロムはこの強制的画一化された人間を「自動人形」となずけています。
この「自動人形」化が進んだ結果、行きついた先がナチズムや全体主義です。、わたしたちが「厨二」と馬鹿にしている思春期時代の黒歴史が青空のように感じられるほどの黒歴史を、西洋の先進国の社会適応しているおとなが自覚のないままに自作自演してしまったのです。
『鬼滅の刃』の「鬼」は人間だった頃の自分を忘れていき、代理満足をあたえてくれる無惨の価値観に服従し、人間を欲の対象にしかみれず、傷つけ、むさぼります。「自動人形」となった人間は、自分をわすれていき、代理満足をあたえてくれる同調先の「匿名の権威」に服従し同化していき、そうしない「私」としていきている人の存在が無性に苛立たしいと感じられ、間接的に責任を取らないやりかたで傷つけてしまいます。
「鬼」を「自分をわすれることで安定をてにいれた元人間」と定義すると、それは、フロムが明晰に描写して見せた近代人にも同じ定義があてはまります。そして、その定義はわたしたちの姿とも重なるのです。鬼は、「自由からの逃走」をしているわたしたち現代日本人のメタファーと言えてしまうのです。
埋もれた心がもとめるもの
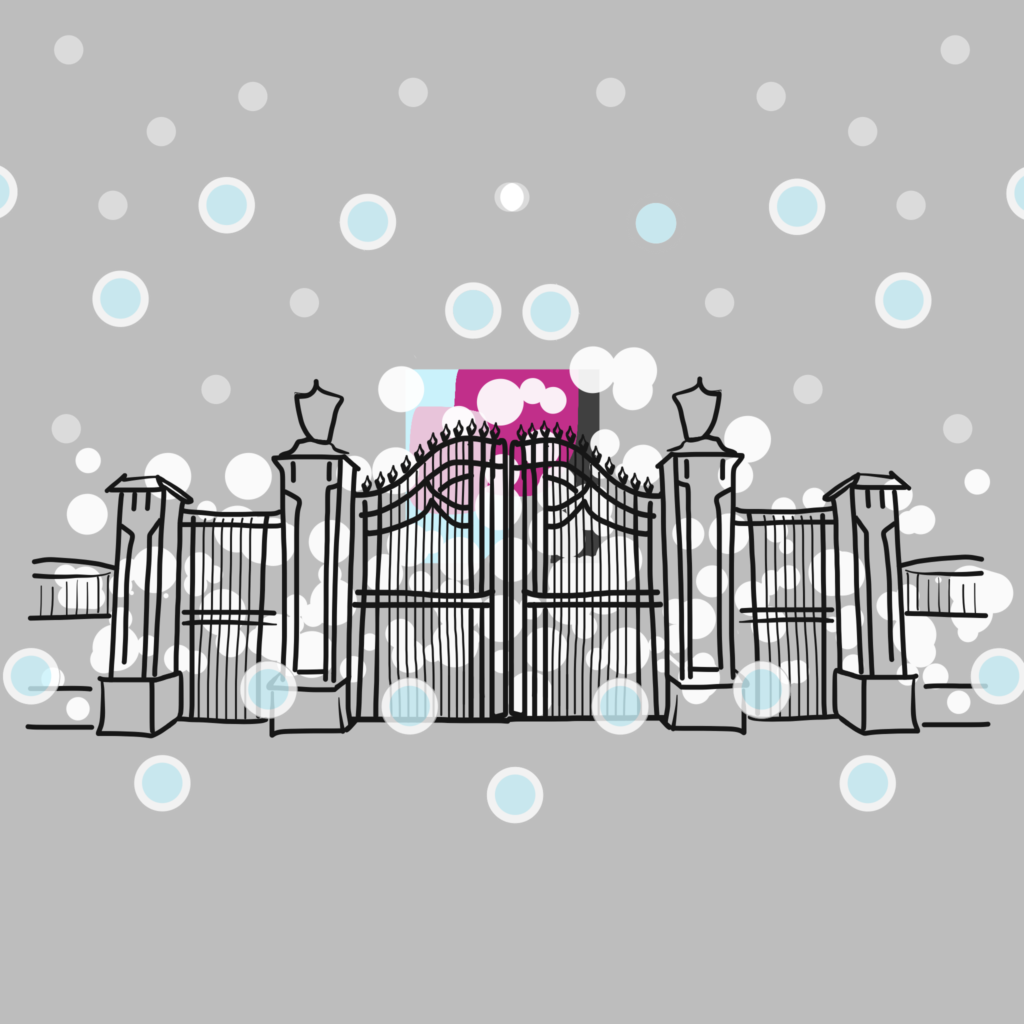
「鬼」は元は人間で心を持った存在として描かれています。わたしは当初「やたらグロテスクな敵キャラだなー」くらいの軽いノリでみていました。しかし、鬼の過去(人間だった時の記憶)か明らかになるにつれて、予期せず揺さぶられるものを感じ、ぐっと物語に惹きつけられたのです。
人を喰らうということは、「人間を自分の欲を満たすための対象にする」ということです。強い「鬼」の欲求はより強く、貪欲になっていきます。しかし、物語をみていくと、それらの欲求の強さは、人間時代の苦悩の大きさに比例し、消費欲や力への欲求は、本当の欲求の代理満足であったことが明るみにでます。
「鬼」の本当の欲求とは何でしょうか。それは、「私(心)」に人が気がついてくれること、気がついて配慮しあう人間関係、他者に心という個性をもった存在として認めてもらうこと、といった「私」として他者と関係を築くなかで得られるタイプの感情経験への欲求です。
「鬼」は、本当は「私」として生きたかった、「私」を放置しないで、同じように「私」を放置していない人との間にあるもの、「内的な繋がり」を感じたかったのです。
かれらは、人間時代に何らかの事情により、自分であることに無力感や不安、寂しさを抱え、鬼舞辻無惨の接近を許してしまいます。それが、「鬼」の不幸の始まりなのですが、これは、2017年におきた座間9人殺害事件の経緯とそっくりであることに気がつかされます。
この事件は衝撃的な事件であったので、大々的に報道されましたが、この事件以外にも、ニュースに出ないだけでSNSを使用した悲しい事件はますます増えています。
被害者はなんらかの事情ににより、自分であることに無力感と不信感、不安、寂しさを抱え、たえられずSNSを利用し、「無惨」よりな人間の接近を許してしまう点で共通しています。そこが悲劇のはじまりです。「無惨」のような人間はもちろん批判されてしかるべき存在ですが、「無惨」よりの人間にとりこまれる余地を作ってしまったその人の周囲の環境のほうが、病んでいるのではないか、病巣があるではないかと考ることもできるのです。
ひとは完璧ではありませんし、生きていく中で、無力感や不安、寂しさをかかえることは誰にでも起こりえます。そういう時期、その人が自分の弱さを見せられるのは、その人の築いた人間関係の中で最も信頼できる人間だけです。そういった人が「無惨」のような人になぜ自ら近づいていかざるおえなかったのか。いいかえれば、なぜそのひとが最もデリケートな悩みを相談できる人間がそのひとの周りにいなかったのか、そのような状況にある人が日本では少なくないというのが問題なのです。周りには、何らかの人が、少なくても、教師や公的機関の人がいたはずなのにです。
デリケートな悩みほど、それを話すには信頼関係を要します。いくら外から「助ける」といわれても、信頼関係を築けてもいないのに、「公的な組織の人間だから信じて悩みを話してよ」というのは、すでに信じて痛い目をみてきている人にとっては、かなり乱暴な話です。相談者にとっては、SNSで出会った人も、支援団体の職員も同じ赤の他人から関係は始まります。この手の信用は、銀行ローンの信用ではないからです。
公的機関で働く人に相談するくらいなら、知らない人にSNSを使って相談したほうがましである、という事実はどういうことを伝えているのか。
もちろん、悩んでいる人を支える支援団体や公的支援は必要です。そのうえで、本当の意味で人を救えるのは、支援団体や役割のまえに、ひとりの人間としていきている人間だけではないかとわたしはつくづく思います。弱者を救うという上から目線の人間ではなく、「正しい」価値判断をいっぽう的に押しつけてくる人間ではなく、耳をかたむけることのできる人間、「私」でいてやっぱりいいんだな、とその態度から感じさせてくれる、実際に公的な役職という属性の前に、「私」として生きている人間です。
世界各地の紛争地を取材しているフリージャーナリスト・学者のカロリン・エムケは、信頼の問題にたいしてこう述べています。
この議論においては、暴力の被害者のほうが、聞き手の信頼に値することを証明せねばならないのではなく、被害の免れた者のほうが、被害者の信頼を勝ち得るために努力をせねばならない。本書冒頭に示した「あなたがこれを言葉にしてくれ?」という問い。または、世界中のあらゆる場所で何度もくり返し口にされる「あなたがこれを書いてくれる?」という問いには、常に希望と同じだけの疑念が含まれている。聞き手が、社会が、話をする相手として信頼に値するだろうかという疑念だ。
カロリン・エムケ 浅井晶子訳 『なぜならそれは言葉にできるから』 みすす書房
エムケは、虐待によって人間全般への信頼と失った人と信頼関係を築く大事なこととして、何らかの傷が生んだ「経験によって作られた人間としての彼ら」のほうも受け容れる覚悟をあげています。つまり、硬直し、時に嘘をつき、沈黙している目の前に実際いるありのままの彼らも、聞き手が受け入れる準備や覚悟をしているかどうか、が聞き手が問われているということです。
『鬼滅の刃』では、虐待とネグレクト(意思の無視)の過去をもつ、カナヲというトラウマをかかえた少女がでてきます。彼女は幸運にも、「無惨」よりの人間ではない胡蝶姉妹に引き取られますが、彼女はそれから十数年たち、処世術をみにつけたものの、明らかにトラウマの後遺症を感じさせるふるまいをとります。幸運にも人情ある人に出会え、十数年かけて関係を築いてようやくここまでこれたのだ、ともいえます。社会的な役割だけでも、生半可な付き合いでも解決ができないこの手の問題のリアルを感じさせられます。
わたしが「鬼」の過去(人間だった時の記憶)が明らかになるにつれて、予期せず揺さぶられるものを感じ、ぐっと物語に惹きつけられたのは、「鬼」となり、破壊性という残念なかたちでの表現となってしまったものの、あれだけの力を秘めていたならば、近くにいた人間が、無惨もしくは「無惨」よりの人間でなかったら、苦悩をのりこえたさきには活躍の可能性があったのではないか、と思うからです。そんな本来力をひえた有望な人間が、下らない代理満足をあてがわれ、あくせく尻をたたかれたうえに、死に際に自分の人生の空っぽさに気がつき、「自分の人生は一体何だったのか」という後悔をする「鬼」に、わたしは同情というか、いたたまれないタイプの親近感を覚えます。
「日本一優しい鬼退治」というキャッチフレーズが『鬼滅の刃』にはつけられているそうですが、人間性を失った鬼とは対照的に、主人公の炭次郎たちが、自分も含め他者の独自性・独立性にしっかり気が付き、その孤独を認めようとする姿勢が垣間見られるところにあるのではないかと思ったりします。「イイヒト」でもできる社交的・表面的なやさしさより、一段深みのある優しさです。
「鬼」と「鬼」が築く利害関係による表面的な関係でもなく、迎合して明るい部分だけしか見せれなくなってしまった表面的な関係でもなく、すぐさま「正しい」答えをおしつけてくる助ける側、助けられる側の上下の関係でもなく、「私」を放置していないひとりの人間とひとりの人間のあいだに生まれる「内的な繋がり」が感じられる人間としての信頼関係、それが、現代にいきるわたしたちの埋もれたこころが求めているものなのではないでしょうか。『鬼滅の刃』はそこに寄り添ってくれていたわけです。
・・・・・・
・・・・
・・
『鬼滅の刃』では、この「内的な繋がりが感じられる関係」を築ける代表格が主人公、竈戸炭次郎です。次回は、かれの魅力の秘密に近づいていきながら「なぜ『鬼滅の刃』は世代をこえて異常なほど大ヒットしたのか?」という謎を別の側面から迫っていきたいと思います。
お付き合いありがとうございました。
参考文献
[放送局] TOKYO MXほか
「劇場版 鬼滅の刃 無限列車編」
[原作] 吾峠呼世晴
[監督] 外崎春雄
[脚本] ufotable
[キャラクターデザイン] 松島晃
[音楽] 梶浦由記、椎名豪
[制作] ufotable
[製作] アニプレックス,集英社、ufotable
[配給] 東宝,アニプレックス
[封切日] 2020年10月16日
[上映時間 ]117分
その他 PG12指定
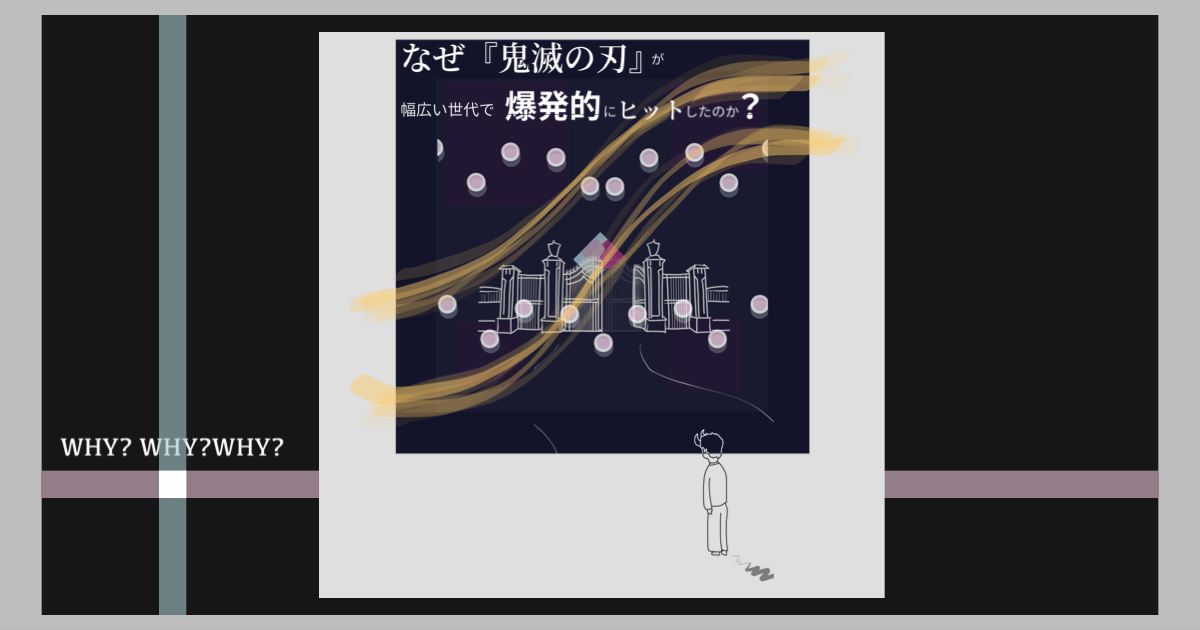
Updated on 4月 15, 2021
なぜ『鬼滅の刃』が幅広い世代で爆発的にヒットしたのか?その4 続、近代史から見る『鬼滅』大ヒットの背景
こんにちは、matsumoto takuya です。2020年1月8日二度目の緊急事態宣言がなされました。今回の宣言が最後となるよう願ってます。今回も前回にひきつづきシリーズ「なぜ『鬼滅の刃』が幅広い世代で爆発的にヒットしたのか?その4」をおおくりします。
前回の投稿で、1977年を軸に孤独という側面をもつ自由のルーツを探っていくなかで、「個性を大事に」といって個性を半ば発達させておきながら、実際に自由や個性を積極的に表現することを許さない社会という「ズレ」が日本に生じ、この「ズレ」が孤独の不安を強め「私」をうしなってでも「匿名の権威」やなんらか権威に同調して不安を解消したいという傾向が増大している今の日本の姿がみえてきました。「私」が窒息しそうな環境であるからこそ余計に「私」の側にたつ『鬼滅の刃』のストーリーが心に響き、世代を超えての大ヒットを生んだのではないか?という理由の背景あったのです。
その延長である2020年代、その「ズレ」はわたしたちにどうのような影響を与えるのか?『鬼滅の刃』が流行した2020年代にいきるわたしたちは日本は「私」として生きることに関してどのような環境に至ったのでしょうか?
圧縮された過渡期
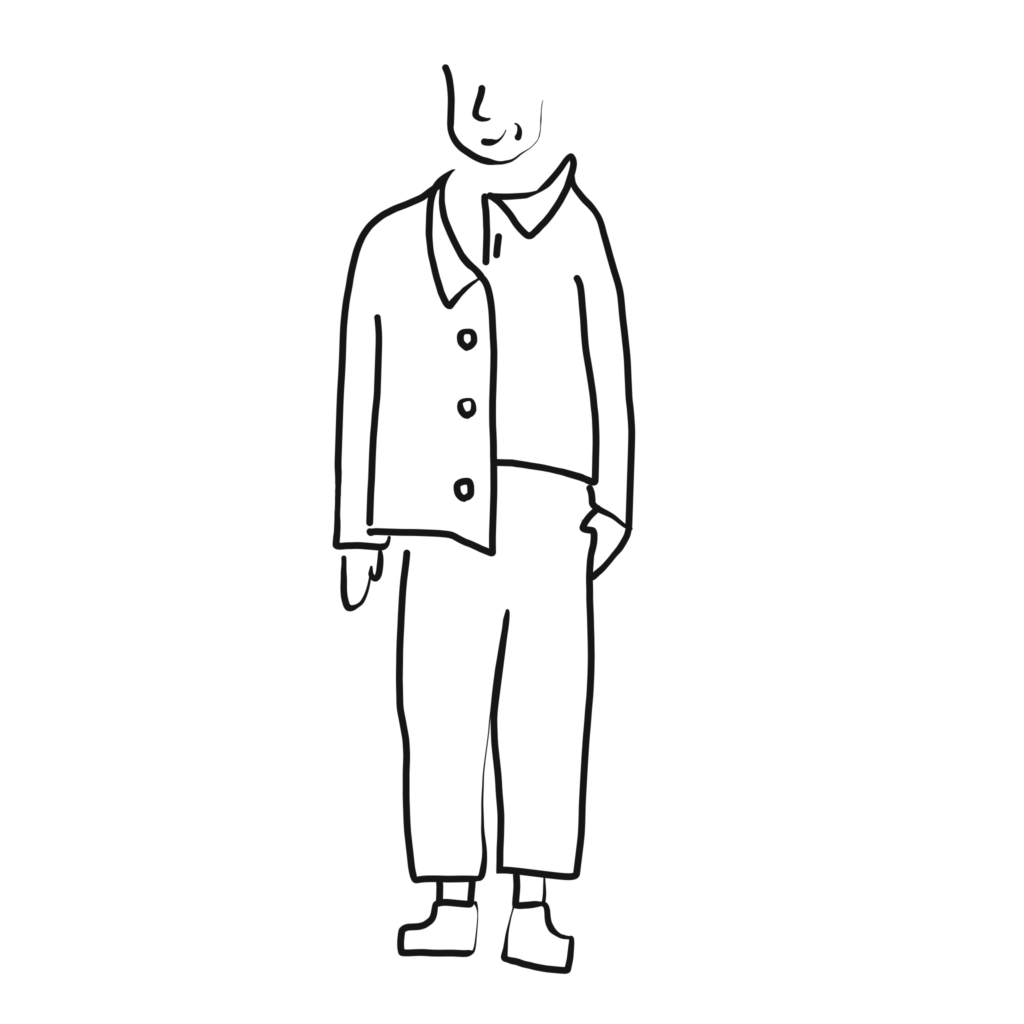
このように、今を生きるわたしたちは、1977年頃のような中世的な価値規範のメリットでが小さくなり、今後さらになくなっていくにもかかわらず、デメリットである公私混同の上下関係をデフォルトとした社会を余儀なくされています。中世的なうまみも近代の自由のうまみも奪われ、デメリットだけしょわされたかっこうです
もう少し踏み込んでいえば、 世代が若くなるにつれて、求めている内容が、「私」としてあること(Be)への肯定から生まれる精神的(精神とは個人的なもの)な喜びへシフトしているのに対して、自分と他人の内面が未分化な人間関係を受容したうえでの安心は、個人を満たすことができる精神的な満足とは質的にかみあいません。そのため、個人の意識下に釈然としないなんとも言えないわだかまりを残すことになるのです。
もう少し踏み込んでいえば、 わたしたちが求めている内容が、個性化の発展にともなって「私」としてあること(Be)への肯定から生まれる精神的(精神とは個人的なもの)な喜びへシフトしているのにたいして、再同調先の旧来の日本の価値規範は同質性を基本とし、意思がどうこうより群れることから得られる安心感に比重がおかれています。自他の区別が未分化であり、よって個人への尊重、配慮の文化が育っていない自分と他人の内面が未分化な人間関係を受容したうえでの安心は、個人を満たすことができる精神的な満足とは質的にことなるため、意識下に釈然としない欲求不満がひそむ余地をうみ、なんとも言えない「ズレ」を感じさせます。
この意識下の欲求不満をかかえた精神のバランスをなんとか取ろうそして、同調先の人間関係に度の超えた承認欲求を求めることや、自分のように再同調しないで生きている人への不寛容、いじめ、もしくは上下関係や属性でのマウンティングというかたちで漏れ出てくることになります。
また、自他の区別のない人の善意は、自他の区別がある価値観にシフトしている人に窮屈さを感じさせます。
例えば、職場の直系ではない先輩が後輩にランチをおごったとします、たまたまその人はお腹の調子がわるかったのですが、先輩に悪いとは思うもののランチを少し残すことになりました。後日、その先輩はその後輩が無礼にも「おごってやった昼食のランチをあいつは残しやがった」と陰口で吹聴します。そのおごる行為は上下関係的に完食しないと失礼にあたるからです。その先輩にとっては先輩からランチをご馳走してもらっておいて残すことは先輩の顔に泥をぬった無礼者となり、よって世間に晒して懲罰を、という発想になる。一方で、後輩からしてみれば、無理して食べたくもないランチを貴重なお昼休みの時間を削って、個人的にとりたて尊敬しておらず、別段、一緒にいたいと思っていない相手と過ごすことになったあげくのはてに、このような陰口を吹聴され、「見返りが欲しいなら、はじめからおごるなよ」という気持ちになるわけです。
この結果が見に見えるので、彼にとっては実質選択肢がなく、相手が善意であることには違いないので、嫌な顔をすことも出来きないまま、無理して完食する以外に選択肢がなくなってきます。ちなみにこの例では、日本の暗黙のルールを破ったのは後輩ですが、日本の社会のルール(パワハラ)を犯しているのは先輩です。
あからさまなパワハラ以外にも、この防御しずらい善意からくる「ズレ」たコミュニケーションから蓄積される窮屈さも、比較的若い世代が上の世代と職場の外で付き合うことを避けるようになった原因だと考えられます。時に善意は、他人に精神的な苦痛を与える最たるものになりえます。
そんなことをいいだしたら、いままでどおり人と気軽にコミュニケーションなどとれなくなる、というような意見をおもちの方がいるかもしれませんが、たしかにその通りです。
この現状をよくよくみていくと、西洋の歴史で中世末期以降の特徴である「主体の確立への模索の時代」に生きた人々の精神状況と、とても似ていることに気がつきます。
この現状をよくよくみていくと、西洋の歴史で中世末期以降の特徴である「主体の確立への模索の時代」に生きた人々の精神状況と、今の日本人が置かれている精神状況がとても似ている境遇に置かれていることに気がつきます。
当時の西洋は、固定的な社会構造が資本主義の発展により流動化し、宗教改革にともなう中世から近現代の価値規範への転換の初期段階にあり、不安な落ち着かない気分が生活をおおっていた時代でした。時計も発明され、「時は金なり」という性格を人々にあたえ、禁欲的かつ経済的に非生産であることに自他ともに憤りを感じるようなった時代でもあります。
この時代を見てみると、かつての絶対的な社会基盤を母体にしていた自他の区別がない価値規範にしたがうことで得られるメリットよりも、デメリットのほうが露呈するようになります。個の目覚めを経験したのにもかかわらず、それを許さない社会という「ズレ」が、かつての封建的なしがらみを断ち切ることで個に目覚め始めた個人に抗いがたい孤独の不安や無力感を感じさせるようになります。西洋では、「私」というせっかく手に入れた自由・個性をすててまで、新興宗教に熱心になる期間を経由して、個人の権利が生み出された後は、「世間」や「みんな」といった「匿名の権威」の同調に駆られ服従にいたる、という歴史を経験しています。
その結果、西洋では全体主義が蔓延したのですが、この状況は、今の日本とかなり似ているのです。
西洋が15世紀末から近代の20世紀にいたる400年という長い年月をかけ、大変な混乱と失敗と試行錯誤をしながら経験した文化様式の変化を、私たちの社会は4,50年で一気に集約・圧縮された形で経験していることになります。いまの日本の生きるわたしたちが、個の確立・自由について社会全体レベルで困惑気味なのは至極当然といえるのです。
『鬼滅』がハマった世代
上の世代は前世代から引き継いだ既得権益・権力があり個の自覚がない人が多数派を占めているため、まだ何とかなりそうです。しかし、中・下の世代の多くは権力を持たず、かつての規範を盲目的に信じられないなかで、多様性を掲げた教育やスマホの普及で個性化はより進んでいます。そのため、中堅以下はより現代のシビアな抑圧に晒されているといえます。
ここに、『鬼滅の刃』がハマった世代が重なります。
ここで回り道をしましたが、ようやく、今の日本をいきる私たちが個性化の発展を妨げている「何らかの障害」が説明できます。
それは、個性をなかば発展させながら、「私」として生きることを許さない社会の「ズレ」であり、「私」という個性をすててまで「匿名の権威」に同調・同化してしまった人間の同調圧力と逆恨み的な排他性です。「ズレ」と、その結果である同調圧力と排他性は負のシナジーです。
「私」という人間性を失い、そのことを考えることさえできなくなり、人間をひたすら物のよう扱い消費する存在、同時に、意識下に無力感と虚しさを抱える存在が『鬼滅の刃』の「鬼」です。いまの日本は、「私」を失った「鬼」にするための土壌にはもってこいの環境にあります。
西洋の人々は、「自由からの逃走」の結果、ナチズム、ファシズム、といった全体主義におちいり衰退・自滅の道へすすみ、愚かで悲惨なアウシュビッツを生み出しました。内側から、人々が人間性を鈍化させていき、狡猾なロボットのような冷たい存在に変わっていったわけです。わたしたちは、もうそれを歴史で知ってしまってます。
後ろにはもう戻れない、今のぬるま湯状態から抜け出せずはまっていると衰退と悲惨が待っていることをもう知っているし、そのぬるま湯は身体から熱を奪って気分が悪くなってきている、となると、わたしたちは旧来の中世的規範から近代的な精神への過渡期を個々人が先に進むしかないわけです。『鬼滅の刃』にはまった世代の一人一人置かれた境遇と『鬼滅の刃』の炭次郎たちの境遇が重なってきます。
映画『ショーシャ ンクの空に』でこんなセリフがあります。「必死に生きるか必死に死ぬか」です。シェークスピアの『ハムレット』のなかでも「生きるべきか、死ぬべきか」というセリフがあります。わたしたちは生きるべきだし、どうせもらった一回ぽっきりの命なら「私」を忘れ、自身の言動で無自覚に人を傷つける「鬼」ではなく、「鬼」の侵害に立ち向かい必死に生きる「生きている人間」のほうを選びたいものです。
「鬼」化が完成された世界
自分を疎外する、忘れる、見失うということは、服従している世間体の他に「自分のしたいことが分からなくなる」「興味、関心が動かなくなる」ということであり、単語でいえば無関心です。自分を忘れた人は同調先の価値観に同化するにいたります。
中世末期(15世紀末)から近代(19世中ごろ)までの間の、個の目覚めによって自由と孤独を自覚した人間の精神史をまとめたものが次に引用した文章です。
個性化が一歩一歩進んでいくごとに、ひとたび人は新しい不安ににおびやかされた。第一次的絆は、ひとたびたちきられると、二度と結ぶことはできない。ひとたび楽園を失えば、人間は再びそこに帰ることはできない。個別化した人間を世界に結びつけるのに、ただ一つ有効な解決方法がある。すなわちすべての人間との積極的な連帯と、愛情や仕事という自発的な行為である。それらは第一次的絆とはちがって、人間的自由な独立した個人として、再び世界に結びつける。しかし、個性化の過程をおし進めていく経済的、社会的、政治的諸条件が、いま述べたような意味での個性の実現を妨げるならば、一方でひとびとはかつて安定をあたえてくれた絆はすでに失われているから、このズレは自由をたえがたい重荷にかえる。そうなると、自由は疑惑そのものとなり、意味と方向を失った生活となる。こうして、たとえこのような自由を失っても、このような自由から逃れ、不安から救いだしてくれるような人間や外界に服従し、それらと関係を結ぼうとする、強力な傾向が生まれてくる。
・・・どのような絆からも自由であるということと、自由や個性を積極的に実現する可能性をもっていないということとのズレの結果、ヨーロッパでは、自由から新しい絆への、あるいはすくなくとも完全な無関心への、恐るべき逃避がおこった。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社:46項
フロムの近代人の描写は最後には当時の現代(1940年代)につうじていきます。その結果、無関心が社会に蔓延し、ナチズムをはじめとした全体主義が勃興することになったのは周知のとおりです。
『鬼滅の刃』の世界でいう鬼舞辻無惨と同レベルの非情な行為を、表上はとち狂った「鬼」ではなく、自分は「普通」であるという自覚のもと社会適応をしていた規律にかたくなに厳しい人間の集団がおこなったという点で、より残念なかたちで全体主義に陥った人間の無能さや愚かさ、不気味さを歴史は証明してしまいました。
思考停止し、上から「正しさ」をあたえられて多数派に盲従する人々を多数派にかかえた民主主義は少なくとも、わたしたちにとって重要で大切なことを暮らしから失う道を約束されているのです。
道具を使う人間と使われる「鬼」
フロムが活躍していた20世紀初頭と違う点は、この自分を見失うプロセスのテンポの速さです。現代の私たちの生活は、資本主義、都市化、科学技術・情報化といったものが爆発的に発展し、もはやほとんどの業界は1947年代よりいっそう流動化しています。そんな不安定な中で、わたしたちは巨大な会社にこき使われ、もしくはあおられ、会社は株主にこき使われ、国家は株主はグローバル金融市場にあおられ翻弄され崇拝し、その圧倒的な機構のまえで個人はますます無力感を痛感させられ圧倒されています。
また、個人の視点からみると、スマホなどの常時ネット接続環境とSNSの登場は、かつての日本では一枚岩の「匿名の権威」として君臨してしていた世間をどんどん分散させている印象をうけます。これにより、わたしたちはより同調・同化がしやすいのですが、かつての日本人が同調してきた一枚岩の「世間」に比べ、はるかに規模的に安定性が欠けるので、より食い込んだ同調をせざるおえないか、上辺の関係性しかえられない環境下にあります。
脳科学、心理学等を駆使して承認欲求をくすぐるように設計されたSNS、そのコントロールされた適度な間隔をおいた通知が「不安」→「同調」→「不安」→「同調」というループを促します。個人をここまで依存させた道具は、今までの歴史には見られなかったものです。
デジタルは個人の表現の場を世界に広げた点でとても有益ですし、双方のやりとりを可能にするものであり、連絡手段として便利なものです。しかし、デジタルが手段ではなく目的になってしまった場合、それは「私」を見失わせる最も効果的な悪手に変わります。
「川」をわたるための「筏」として
西洋人が中世末期から近現代にいたるまでの間、個の目覚めにあたり、どういう過程をたどったのか、どういう試みをしどういう失敗をし、どうやったら成功するのかといった諸条件についての情報は、本質的に近い状況にある今日のわたしたちにとって有益です。
『鬼滅の刃』の大ヒットと、フロムの著書『愛するということ』のリバイバルが時を同じくしているのは偶然ではないのです。フロムの残した仕事は以前として有効どころか、ますます、、、というより、今にしてようやく、日本にいきるわたしたちの姿と合致した真実を描き出しているとわたしは思います。
科学や経済は、最新であることが重要ですが、人間の本質が問題となる場合、新しさは絶対ではなくなります。人間存在の本質は、人間が人間を辞めない限り変わらないからです。それは、2000年前に西洋にあらわれた青年(キリスト)の教えや、2500年前にアジアで活動していた青年(ブッダ・仏)の思想が未だに、現代社会で生きていることを見ればわかります。
わたしたちがかかえる人間らしさの悩みや問題については、すでに過去の誰かが悩んでいて、傑出した人がなんらかの問題解決のヒントを創出しています。そう考えた時、フロムの残した仕事は、今の日本の社会の「圧縮された過渡期」という激流を渡るための貴重な筏となってくれるはずです。
『鬼滅の刃』に共感する人が多いのは、この意味での「筏」を『鬼滅の刃』の中に見出しているからではないでしょうか。それは、逆境のなか「私」として生きる者同士が築き上げる社会に生きるときに模範となる規範です。
・・・・・・・
・・・・
・・
ここまでは、時間という縦の軸と西洋・日本といった地理的な横の軸、そして、それらを社会の下部構造と人々の社会心理の観点から、『鬼滅の刃』が爆発的に幅広い年齢層に大ヒットした理由をマクロの視点で探っていきました。
ここからは、『鬼滅の刃』の物語の個別の内容面を除いて言い「鬼」化しているわたしたちの社会の姿を明らかにしていきます。
次回は題して「『鬼滅』炭次郎と無惨からみる愛と支配」です。
お付き合いありがとうございました。
参考文献
[放送局] TOKYO MXほか
「劇場版 鬼滅の刃 無限列車編」
[原作] 吾峠呼世晴
[監督] 外崎春雄
[脚本] ufotable
[キャラクターデザイン] 松島晃
[音楽] 梶浦由記、椎名豪
[制作] ufotable
[製作] アニプレックス,集英社、ufotable
[配給] 東宝,アニプレックス
[封切日] 2020年10月16日
[上映時間 ]117分
その他 PG12指定
「自由からの逃走」
[作者] ERICH FROMM
[訳者] 日高 六郎
[発行者] 渋谷 健太郎
[発行所] 株式会社 東京創元社
シェイクスピア 『ハムレット』福田/恒存訳 新潮社
監督 フランク・ダラボン『ショーシャンクの空に』キャッスル・ロック・エンターテインメント
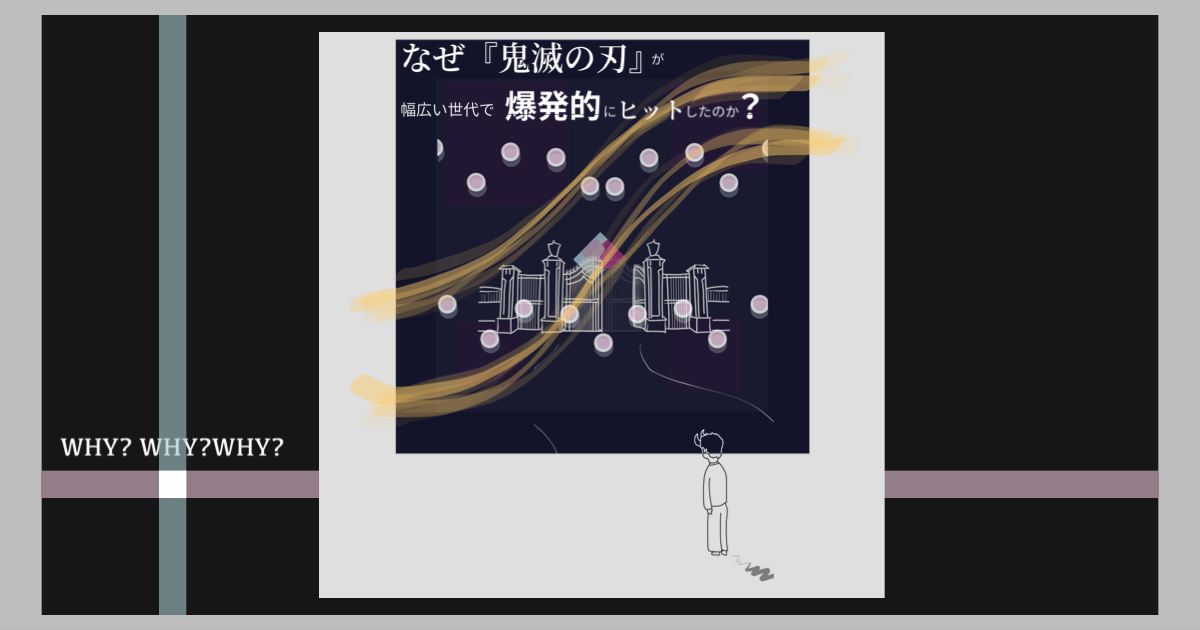
Updated on 4月 18, 2021
なぜ『鬼滅の刃』が幅広い世代で爆発的にヒットしたのか?その3 近代史からみる『鬼滅』大ヒットの背景
こんにちは、matsumoto takuya です。今回も前回にひきつづきシリーズ「『鬼滅の刃』が少し引くほど大ヒットした理由とは?」をおおくりします。
前回の投稿で、わたしたちが「私」を放置し「鬼」化する傾向にあり、「私」が窒息気味であるから、「私」を失った鬼から人間をまもり、鬼となった大切な存在を人間にもどす物語である『鬼滅の刃』に共感したのではないか、というところまで行きつきました。
多様化がすすんでいるはずの日本でどうして、相変わらずわたしたちが「鬼」化しやすい環境になっているのだろうか。それが、「なぜ『鬼滅の刃』が幅広い年齢層に爆発的にヒットしたのか?」の理由にふさわしいような気がします。これが今回は、この「日本の生きずらさ」のルーツを近代史から探っていきます。
自由が無かった時代とは
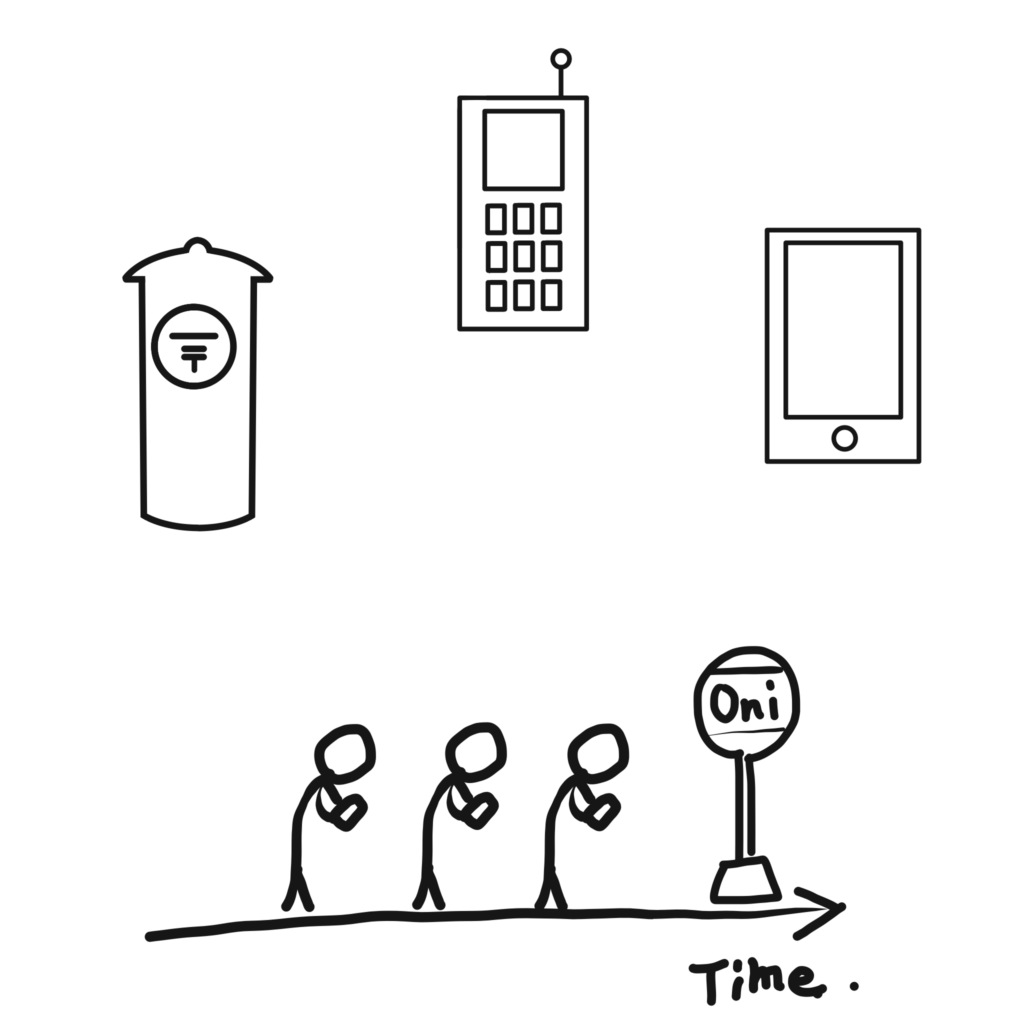
今の日本社会の生きずらさを理解するには、個人の自由が生まれた背景から遡ってみていくのが一番です。
西洋史によれば、個人の自由は、中世末期(15世紀末)のキリスト教宗教改革と資本主義の発達によって人類の歴史に登場したものです。人々は、それまでの個人を縛る封建的共同体(中世12世紀から)のしがらみから解放されていった結果、自由を獲得したと同時に、孤独の不安も自覚するに至りました。個の自覚から始まる自由にはこのような両義性があったのです。
日本でこの「封建的」という言葉を耳にするとき、否定的なニュアンスで使われることが多いようです。自由を知らなかった時代に生きていた人々、中世の封建時代の人々はいったいどのような精神状態だったんでしょうか。
フロムは中世(12世紀~15世紀末)の人々について、こう述べています。
もちろん社会はこのように構造的であり、人間に安定感を与えていたが、しかも社会は個人を束縛していた。しかしその束縛は、のちの世紀における権威主義や圧迫がおこなったものとは違っている。中世社会は個人からその自由をはく奪しなかった。というのは、「個人」はまだ存在しなかったからである。人間はまだ第一次的なきずなによって世界に結ばれていた。かれはまだ自己を個人としては認めず、ただ社会的役割(それは当時においては自然的役割でもあった。)という点でのみ、自分の存在を意識していた。また他人も「個人」としては考えなかった。街へやってきた百姓は異国人であり、同じ町のなかでさえ、階級の違う人間は互いに異国人と考えられていた。自分自身は他人や世界について、それを分離した存在として考えるような意識はまだ十分に発達していなかった。
同上:56項
(注)フロムは近代的な意味での個人主義は存在しなかったが、中世の実際生活における具体的な個人主義は、社会的な枠組みを壊さないという条件で、大いに存在していたと述べています。
中世の世界では、不変と信じられる経済構造・社会的共同体があり、生まれついての社会的身分・特権が決められていました。構成員はその枠組みの中で生きることを条件で、経済的欲求と精神的欲求の満足を得ていました。不変でゆるぎない教会の権威は、人々の世界への見方・生き方の規範となり、固定された経済構造や社会共同体があることは、疑う必要のない安定感・絶対的な帰属感を人々にあたえていました。そのため、自由をそこまでもとめる必要もなく、現代のような意味をもった孤独の不安が自覚されることはなかったそうです。
ギルド内(今でいう職人組合、会社)では過剰な競争は御法度で、時計もまだ発明されておらずゆっくりとした時間がながれており、人間の仕事の目的となっていました。仕事のために人生があるのではなく、人生のために仕事がある。そういう時代です。
どうやら思っていたよりは悲惨でもないし、かといって戻りたいとも思えない、といった印象です。生まれた時からすでに固定した地位が約束され、全体の構造の中に根を下ろしていた人々、自他の区別がまだできていない人々、今でいう自由はないけど枠組みのなかでは個人主義が大いにあった人々、これらが近代前の中世にいきた人々の特徴です。かれらの安定や自由は、不変と信じられる経済構造・社会共同体からあたえられる安心に支えられ、家父長制をはじめとした少なくない人々の抑圧を含んだ枠組みをこわさないかぎりで実現したものでした。
日本史と西洋史は、全く同じではありませんが、似通った点は多くみられます。近代的社会制度導入前といえば、日本は士農工商の身分制度をしいていた江戸時代です。「世間」というものが著しく発達したのもこの時代だそうです。中世の人間の描写は江戸時代の民衆の描写に近いだろうと類推できます。
ここで私は、「まてよ、なんかしっくりこないな」とひっかかります。
わたしがひっかかるものを感じたのは、中世の人々の「かれはまだ自己を個人としては認めず、ただ社会的役割という点でのみ、自分の存在を意識していた。また他人も「個人」としては考えなかった。」という部分の描写が、なぜか現代にいきるわたしたちの描写としてもありうるとわたしには思われたからです。最近では会社のためにプライベートを犠牲にする人を社畜と批判的に表現する人が少なくないですが、ほんの少し前は会社人間であることは「普通」だったからです。
1977年の現役世代の精神性は中世人
次に引用した公演集を読んだとき、このもやもやを解く糸口がみつかりました。20世紀を代表する思想家・文化人類学者で、構造主義の祖であったクロード・レヴィ=ストロースは、国際交流基金の招きにより、1977年に来日し、当時の京都大学の学者たちとのシンポジウムを開催し、「何のために働くか」というテーマの討論をしています。
働くことの意味という問題は、国立民族博物館を訪れたときも、もっともレヴィ=ストロースの関心を呼んだ話題である。梅棹忠夫氏、米山俊直氏、谷泰氏、石毛直道氏などが、日本では労働は売るという観念はなじみがうすく、むしろ仕事・労働と人間形成とを結びつけて考えることを、大工の社会やお手伝いなどの例をあげて詳し説明し、その精神が近代的な大社会にも生きていることを述べた。この話はレヴィ=ストロースには大変おもしろかったらしく、それが日本人の伝統的な労働観であるならば、日本の経済発展に西洋は絶対にたちうちできないだろうと応じて、皆を笑わせた。
『構造・神話・労働 クロード・レヴィ=ストロース日本公演集』 大橋保夫編 三好郁郎・松本カヨ子・大橋寿美子訳:株式会社みすず書房:105項
注)梅棹忠夫氏(元国立民族学博物館館長)、米山俊直氏(文化人類学)、谷泰氏(社会人類学)、レヴィ=ストロース
レヴィ=ストロースが「むしろ仕事・労働と人間形成とを結びつけて考えることを、――――その精神が近代的な大社会にも生きている」という個所と、フロムが中世の人々について述べた「かれはまだ自己を個人としては認めず、ただ社会的役割――――という点でのみ、自分の存在を意識していた。」という個所の内容は、自分の自分自身への認識と社会と関わる仕事への認識とが未分化である、という点で同じ内容です。これは中世の人々の主要な特徴です。
つまり、少なくとも、1977年の現役世代における共通認識として、個人の精神のありかたは、民主主義の前提となる近代的精神ではなく、自他の区別を必要としない中世以前の精神のありかたに近かったということです。
レヴィ=ストロースはなぜ「それが日本人の伝統的な労働観であるならば、日本の経済発展に西洋は絶対にたちうちできないだろう」と冗談を言ったのでしょうか?なぜ、権力が命令を押しつけてきた場合に、異議申し立てをする個人や多様性を認めない中世的な価値観でいながら、どうして1977年の日本社会は、今ほど閉塞感や鬱屈して雰囲気にならないでいられたのでしょうか?
ここを詳しく見ていけば、日本の閉塞感についての全体像が見わたせそうです。
戦前戦後から1977年までの日本人の精神史
西洋の中世の人々は、教会を介して世界全体と結びついていました。教会が個人の価値観、人間としての徳の規範や世界への見方を教え、人々の精神的な支えと苦悩への慰めをひきうけ、労働は原罪をおった人間の罪滅ぼしの手段としていました。
1977年の日本人の多数派は、日本の中世にあたる江戸時代の人々とはまた違った意味で、「仕事・労働と人間形成とを結びつけて考え」る、という中世的な精神性を維持していました。つまり、1977年の日本人の多数派は、ひとりひとりは会社をかいして世界全体と結びついていたということです。会社が個人の価値観、生き方の規範を教え、世界への見方、ひとりひとりの精神的な支えと苦悩への慰めを引き受けていたということです。会社とは抽象的な概念なので、実際には会社の中にいる人によって行われていたことになります。
これは考えてみれば驚くことです。江戸時代は身分制度による経済の保証、寺請制度による仏教と身分制度を支持する儒教(朱子学)の価値規範の土台のもと、仕事・労働と人間形成とが結びついていました。1977年の現役世代は、価値規範を支える土台がないなかで、経済の保証をにぎる会社内にいる、聖人君子ともかぎらない人間が、一手に生活の糧と内的価値観という人間形成をひきうけていたからです。下の世代には拒否する選択肢は実質なかったでしょう。
会社とはそもそも、利害関係者の集まりで経済と組織の秩序に服しています。会社が個人の人間形成を引き受けていた、個人の価値観である尊重、寛容といったモラルが抜け落ちたような、利害と集団の決定を優先した価値観をもったロボットのような人ができあがることになります。会社原理教みたいなものです。ここからわかることは、会社原理教に陥らないたためには、その会社の指導的な立場にいる人がとても重要になっていた、ということです。つまり、その人の人間形成はその会社内で上に立つ人の質に左右されていたのです。
しかし、戦争経験世代が荒廃した日本を復興していく過程は、かなり生き生きしたイメージがあります。映像をみていても、活力にみなぎっていて、むしろ人情が溢れているような印象をうけます。会社原理教などといった非人間的な様子は感じられませし、レヴィ=ストロースの発言は肯定的です。この世代はそれ以降の世代に比べて、従来の儒教道徳を母体とする家父長的な厳しさはあるものの明らかに失敗に寛容であり、どこかほのぼのしていて、新しいことに挑戦している人、独立心の強い人、場合によっては反骨精神をしめす勇気のある人を面白いと肯定したり、敬意を示すような個人主義の精神が生きていたのではないかという印象さえうけます。
フジテレビ系の人気シリーズ『ドリフ大爆笑』が放送開始されたのも1977年ですし、お笑い関連でいえば、後ろ盾のない無所属にして芸歴のない森田一義(タモさんでおなじみの)が、媚びる様子もなく、腕一本で芸能界に現れたのもこの少し前です。
これは一体どういったことなのでしょうか。
戦争経験世代のまなざし
1977年、現役世代で指導的な立場にいたのは戦争経験世代です。かれらは、第二次世界大戦の敗戦で、おおきな、そして数えきれない死、喪失そして失敗を経験しました。同時に、権力についていた政界・財界のお偉い方がしきっていた「普通」が完全に崩壊し、ひっくり返る価値観の大転換を経験をしています。
その喪失経験は、同じように喪失・失敗の痛手に苦しんでいる他者への同情や理解の方向へ、失敗経験は人間のおごりや盲目に権威に服従することへの自戒や、寛容をもった眼差しの方向へへ、個人を成熟に導いていたのではないかと考えられます。
この世代の全ての人がそうであった、などと言うつもりはありません。しかし、知識と感情経験が結びついたとき人は内的に成長します。そして人を本質的に成長させる経験とは、成功よりも失敗や喪失経験のほうであることが多いこともまた事実です。通常であれば、人がそれぞれの人生の節目で別々のタイミングで数回経験するまれな経験を、国民が同時に一斉に、そして、何度も経験したのです。
一概にこの世代の世界や人間へのまなざしの深さについて、懐古趣味と片付けることはできません。戦争の悲惨さ、そして、敗戦や価値観の大転換の経験が、個々の人の人間性の成熟に影響しなかったと考えるほうが不自然です。
また、この世代は、おそらく敬意をともなって仏教の教えを日常の生活で実践していた(もしくは、それを見て育った)最後の世代ではないかと考えられます。家には仏壇があり、毎朝、先祖と仏様に供物をそえ、チンとりんをならし、手を合わせたあとに、朝の支度にかかったり、仕事にでかける。歳時は仏教行事によっていろどられる。酒の席では「坊主はなまぐさ」という冗談があるほど、生活に結び付いていた世代です。
お上に盲従した結果、手痛いしっぺ返しを骨身に染みて経験したことから、世間の雰囲気も「上下定分の理」といった、上下の社会的な身分・役職で他人の人となりを決めつける儒教道徳が弱まり、相対的に、明治維新から進んだ廃仏毀釈の反動で仏教道徳の平等の精神が優位になったのではないかと考えられます。いずれにせよ、人々の精神的価値規範には伝統的な仏教の教えが2020年代のわたしたちと比べてはるかに生きていたことは明白です。
同時に、戦後直後は、とにもかくにも衣食住の確保が最優先の非常事態からのスタートでした。そのため、個人の目的は、衣食住のためのお金であり、個人的な我慢をしてでもお金を稼ぐための組織を優先できたわけです。また、切実に住むところ、食べるもの、着るものを必要としていたので、それらを作る仕事に今よりはるかに簡単に志がみいだしやすかったはずです。
当時の若者にとっては、戦争で有力な上の世代をほぼすべて失っていたうえに、全てが新しい白紙状態からの再出発で先例がない状態でした。しかし、1945年の人口が7千万人で現役世代がすっぽり抜け落ちていたこと、平均年齢が20代だったことは、かえって上からの不要な封建的圧力をかける頭数が少ないために、苦労がある分、精神的に仕事がしやすかったのではないかと考えられます。
白紙の状態からなにかに挑戦することに失敗はつきものであり、日常茶飯事のはずです。社会の様々な場所で挑戦や試行錯誤をしている人が山ほどいれば、失敗することに今ほど恐怖を感じる必要がなかったはずです。
試行錯誤するゆとりも、新しい西洋の科学技術を使った創造の喜びも、今よりはるかにあったのではないかとも推測できます。挑戦を縛る先例がないといっても、欧米をみれば大枠があり、法整備もゆるくいろいろな向け道があり、ペットの首輪のごときIT管理ツールがなかった時代には現代日本のサラリーマンでは考えられない程の「あそび」と自由が仕事にあったはずです。
実際の景色も、たとえば渋谷にさえ雑木林やただっぴろい空き地が点々とあった時代。息抜きにぶらっと会社を抜け出し、河川敷の土手や空き地の木陰で一服できる時代。それが戦争経験世代の置かれていた戦後の環境です。
このように、敗戦、国土の荒廃という特殊な環境は、人々に個人的な成長と、自然に手を取り合う環境を用意していました。そのため、会社が個人の人間形成をになっても、レビィ=ストロースが驚いて関心をいだくほど、非人間的な会社原理教には陥らず、人情も経済もあり、近代化と同時に日本的な文化も生きている不思議なバランスが保てていたのです。
会社が個人の人間形成をになっていても、個性をおもしろがって尊重し、そのうえ手をとりあう条件が整っていたということです。 言い換えれば、「世間」そのものが、奇跡的に個人の気持ちへの尊重、配慮といった個人主義の要素を含んでいたのです。
1977年以降~「ズレ」の蓄積~
それが、焼け野原や土がむきだしになっただだっ広い空き地が建物でびっしりと埋められ、毎日食材が大量破棄され、洋服が2、3年の流行によって捨てられるようになってくると事態は変わってきます。衣食住は確保されていくにつれて、それにともなってそこまで必死にお金を稼ぐ目的がなくなっていきます。そこまで、我慢して会社に、上司の無茶ぶりに我慢して従う理由がうすれていくのです。
かつて、実際に多くの人に不足していた住宅や建造物は、空間を飽和させるに至った以降は、復興のシンボルから、むしろ空を狭めた閉塞感と土地ころがしのシンボルへ。洋服もファッションへ移行し大量に生産され大量の在庫をかかえるようになり、食材は毎日大量に捨てられるほど余りに余っている。このような状況では、若者が、かつてのような衣食住を生み出す仕事に切実さから志を見出すのは、かつてにくらべてはるかに難しくなってきます。
同時に、戦争経験世代から2世3世と下に世代がくだるにつれて、他者の内面に気を配れるようなまなざし、他者を同志とみるまなざしの深さは浅くなっていきます。なぜでしょうか?
ひとの精神的な成長に伴う認識は、「死」の認識と同じように、知識だけでは不十分で、感情経験とむすびつけられてはじめて得られるものだからです。下の世代は、親が経験した歴史上最大レベルの喪失・失敗・権威の失墜を実体験としてもっていません。 権力は絶対ではなく、ある日ひっくり返るものと分かったうえで服従することと、その認識がないままに権力に服従することの違い。人はいずれみな死ぬという自覚があるうえで生きる世代と、その自覚がないままに生きる世代との違い。喪失・失敗の痛手を痛感した世代が喪失・失敗を経験している人へむけるまなざしと、ただ知識でしかしらない人が喪失・失敗を経験している者へ向けるまなざしの違い。そして何より、共有する喪失、失敗経験がないことは、助け合う動機を薄めます。
また、戦争経験世代が敬意をもって規範として従ってきた仏の教えは、もはや個人の生活に根付いておらずの儀礼的になっていったことも理由の一つと考えられます。
若手にとっては実績とマニュアルをつくった先輩がわんさかいます。できるのが当たり前となり、創作の余地はへり、法整備や先例に拘束されていきます。つまらないが失敗ができないストレスのたまる業務の割合が増えて、創作の余地に反比例するように、失敗への恐れがあらわれます。世代が下るにつれて、失敗や挑戦に不寛容になり、効率至上主義、費用対効果が幅をきかせるようになります。つまり、人間のために仕事をしていた状態から、利益をだす企業体のために人間を変えの利く道具として使う傾向が強まっていくのです。
たとえば、 白紙のキャンバスのうえに大まかなルールの中で自発的に絵を描く場合と、すでにびっしりと誰かが余白を埋め尽くされた狭い隙間に、その誰かが決めた厳格なルールにそって、「絵を描きなさい」と命令されて描きたくもないのに描いているとき、その人は、うんざりすることでしょうし。
この傾向が、世代を下るたびに加速していきます。会社のなかの個人は、主体としての能力を育み、発展させ社会死活で表現できる「あそび」をうしなっていくのです。自発的な表現、寛容、個人への配慮といった「私」を会社で表現できる度合いが減っていき、儒教的な上下関係と流されやすい日和見主義だけが残ります。ゆとり教育を導入しておいて、「ゆとり」世代を嘲笑する年配のひとが多いですが、すでに彼らの世代が、戦争経験者世代がもてていた精神的な「ゆとり」を失っていたわけです。
シンプルに、政教分離がはたされた民主主義社会にある会社が個人の人間形成を担うとどうなるのか。
さきほども触れたように、資本主義における会社はそれ自体は利害集団です。会社が服するのは経済と組織の領域であり、マナー・ルール以上の人間性の規範はありません。会社がいい顔をするのは少なくとも利害のためであり、株価のためであり、株主のためで、それは愛でも道徳でもありません。会社で出世するのは、仕事ができない魅力的な人徳者ではなくて、人徳がなくても仕事で数字が残せる人です。これは、非難しているのではなく、経済そのものには人間ができているかどうかの尺度がそもそもないということです。
その会社に道徳的な要素があるとすれば、会社ではなく、その会社のなかに働く個々人のなかにあるということです。道徳主体は人間にしかありませんし、妥当もしません。会社が服しているのは、経済と組織の秩序であり、そこに正当性についての責任をはたす個人という歯止めのような存在がいなくなれば、必然的に、会社のなかに「私」という個人性が現れる場は消えていくことになります。
経済原理主義化と総官僚主義化
すわわち、お金を稼ぐためにある会社は、会社のため他者は熾烈な競争をするライバルとなり、進んで歯車となり、人間性など金にならないものへの配慮は無駄なものとみなさるおえず、人は会社のためにモノとしてあつかわれることは当然という価値観になり、それを踏まえたうえで会社に貢献することが美徳である、という価値観が優勢になってきます。
現在は、ESG(環境・社会・ガバナンス)が株価に影響を与えるようになってきており、改善は見られるものの、基本的には、私的な領域への責任をとれる人間が上の立場にいない会社が人間形成を一手に引き受けるということはこういう傾向を必ずもちます。これは、西洋が近代に入って経験した歴史と同じです。
1977年に指導的な立場にいた世代ほど我慢する動機がない環境の中で、表面的に同水準の我慢をもとめられる下の世代は、上の世代よりも自虐的な我慢をしなければならなくなります。上の世代への規範に従順で、かつ、優秀であるほど、会社の利益に尽くすために私的な領域をささげることに美徳を求める傾向を生み出します。
同時に、会社が服するもうひとつの秩序である組織の秩序により、個人への尊重を犠牲にしてでも「集団」から見た和を保つことが優先されていきます。「私」を認めない上下関係を絶対としたトップダウンが重宝され、したからの過去のやり方の変更をともなう革新的な取り組や、意見をだすことすら邪見なものとされ、過去の慣習が優先されていきます。これは官僚主義と呼ばれるものです。
集団はただ漫然としていると官僚主義に必ず傾いていきます。また、官僚主義は保身という感情をうみ、試行錯誤など、コスパの悪いのわるいものより結果がすぐに出せるようなもの、リスクをとって成功をとるよりは、結果が分かっている現状維持を求めるようになります。どの国も、どのような宗教も、どのような集団も例外なく、集団は下降していく重力に服しています。
民間の場合、「集団」は会社です。つまり、お金を稼ぐこと、集団のためであれば個人の領域を犯しても妥当であるという雰囲気と、新しいことを拒絶する閉塞感がガスのように当人たちが気づかない間に充満しています。。全体的な傾向としては、このような「私」を締め出すことを前提とした社会の空気感は、「世間」という実体のない「匿名の権威」によって強化され、維持されていくことになるのです。
もちろん、会社によっても、会社の部署によても、そして部署内の一人一人によっても事情はそれぞれ違うことでしょう。しかし、問題を捉え理解するために概念化することも時には有効です
サイレント化の源流
この頃に個人が実社会のなかで「サイレント化」してしまう傾向を生んだ出来事がありました。学生運動の挫折と三島由紀夫の自決です。
当時、敗戦した上の世代への懐疑心と、依然として残る封建的な雰囲気への鬱憤は、安保闘争(1960年代)や全共闘(全学共闘会議)(1970年代初期)などの学生運動、市民運動によって定期的に吐き出す機会がありました。
しかし、その運動は実ることはなく、集団内で「内ゲバ」とよばれる暴力が発生するまで過激化するに至り、「若者のエネルギーの発露」といった当初にはあった若者の自発的な活動へのおおらかな態度や支持を、世間から失うことで衰退してきましした。閉じられた環境で一部の権力者が決めた内容を押し付けられることへの異議申し立てであるデモが、話し合いのもとでの合意といったステージへ発展することなく、ただの破壊行為や一方的な主張のステージで止まってしまったのです。
この挫折により、個人の行動や思想またはその活動や連携といったものにたいして、ある種の拒絶反応のような空気感ができあがり、個々人のエネルギーの向いさきが会社や既存体制に向かうこととなったと考えられるのです。
この挫折により、個人の意見や思想または、その活動や連携といったものにたいして、ある種の拒絶反応のような空気感ができあがりました。
その後に起こった三島由紀夫の自決によって、社会内での個人の「サイレント」化は決定的になったのではないかとも考えられます。当時の日本人の節操の無さにたいして、彼の身体をはった異議申したは、世代のまったく違うわたしからみても見ても強烈な印象をうけます。かれの行動は結果として、大多数の人にたいして理解しがたいものに映り、学生運動から鞍替えした多数派は、かえって自身の黒歴史を合理化しやすく、結果としてみれば、個人の意思表示がしづらい社会環境を黙殺し、社会で「私」を表現することへの委縮した日本社会の傾向に拍車がかかったのではないかと考えられるのです。
もちろん、こうした時代背景や個別の出来事が、今の社会を息苦しくさせた原因であるかどうかは断言出来ません。しかし、そういう歴史があったから、今の日本の状況があることは明白な事実です。
いずれにしても、自分の自分自身への認識が、何らかの権威や社会的役割と未分化となってしまう中世的な精神性から、個性化を成長させたのちにある自他の区別を前提とした、近代的精神性へ移行することなく、日本人の精神史は時代を下っていくことになったことがわかります。
「成功」と個人の質の劣化
これらの傾向が、 1977年以降から進行していき、プライベート犠牲にする会社人間、企業戦士が誕生することになります。永遠に続くように見える経済成長にともなう物質的な繁栄にささえられた消費によって、個々人の個人的な無力感の穴埋めやプライドの確保ができていたのではないかと考えられます。ちょうど、今の中国の成金にあたる新興富裕層が世界でやっていることに似ています。
こうして、会社と消費へ生活をささげる馬車馬のような経済への貢献により、日本は「ジャパン アズ ナンバーワン」と呼ばれるほどの経済大国におどります。この富により、個人の自由の余地が一億総中流の個人にもたらされたのですが、同時に、社会では「私」を表現する場が時代が下るにつれてますます減っていき、鬱憤の穴埋めとしての消費を使った憂さ晴らしはバブル崩壊にともない、下火になっていきます。
こうして、日本人は命のすべてを会社と消費へささげる馬車馬のような貢献をするようになります。これにより、日本は一時は「ジャパン アズ ナンバーワン」と呼ばれるほどの経済大国におどりでたのです。この富により、個人の自由の余地が一億総中流の個人にもたらされたのですが、同時に社会では「私」を表現する場が時代が下るにつれてますます減っていき、鬱憤の穴埋めとしての消費を支えた経済はバブル崩壊を迎え成長は停滞し、「失われた20年」へつながっていきます。
近年、パワハラ・過労等が原因でおきた不幸で遺族が会社を訴えるケースが増え、会社のトップが謝罪会見を開くことが増えてきました。とりあえずは謝罪はするものの、トップのなかには、内心ではその異議申し立ての内容にたいして、腑に落ちていない人も多いのではないかと考えられます。なぜなら、従来の中世的な精神性のもとにある日本の社会的環境が、そのひとに、会社と自分自身の認識が未分化で一体となるように迫り、かれはそれに適応しその地位にいるからです。
当時トップが入社したときに、かれの元には選択肢はなく、それに我慢して適応してきた分、むしろ逆恨み的な不満が残る。その人は、根本的に、主体性、多様化、意思の尊重という「私」にかかわる「本質」と呼ばれるテーマに精神的な価値を見出せていない場合も多いでしょう。会社に同調・同化するためには、むしろ「私」という主体を棚上げして、上下関係に服従することが美徳として上の世代から重宝され、それが効果的な処世術でもあったからです。
「欲しがりません、勝つまでは」
このスローガンは、終戦間際の全体主義体制下の日本では、権力が国民を「一億玉砕」に動員するための統制につかたスローガンです。経済的「成功」の陰で、いつしか日本は、かつての大失敗と同じ轍をふんでいたといえます。「欲しがりません、勝つまでは」と踏ん張って「成功」した結果、「本当に守るべき大切なものは何だったのか」という人間として大事な部分が分からなくなるなるのだとすれば、それは、個々人の「質」 の劣化とよばざるおえないでしょう。
多様性の意味がわかっていない、もしくは、ある種の「アクセサリー」程度にしか価値を見出せていない人が団体のトップに就いていることは、日本では珍しくありません。そのような人の言動によって、その組織や団体、会社のなかにいる個人や活動そのものに、白けたムードを生じさせてしまっていることがあるとすれば、それは残念なことです。
このように、日本社会は、表面上は「私」という個人の権利を基礎においた社会制度をとっていますが、実社会にでてみると「私」を表現することも「私」として社会につながる場もないという、「ズレ」が生じているのです。
そもそも「ズレ」とは
そもそも、なぜ「ズレ」が問題なのかといえば、その社会にいる個々人に無力感をいだかせ、鬱屈させていき、閉塞させてしまうからです。その社会から活気が失われてしまうから問題なのです。
「ズレ」がある社会で「私」として生きようとした場合、周囲からの同調圧力で消耗しやすく、また、その社会に適応したひとからみれば鼻につくので、その人は孤立しやすくなります。その孤立感はだれだって耐え難い不安を感じるもので、「私」をごまかしてでも「世間」」への同調かりたてられます。しかし、半ば「私」という個性が発達しているので、わだかまりを内に抱え込みます。このわだかまりが、自分らしく社会で生きている人に対して逆恨みてきな苛立ちをうむわけです。この苛立ちが、さらに社会から「私」を表現する度合いを奪います。閉塞の無限ループです。
今の日本がこれほど閉塞的で外の世界への無関心と、当事者以外、個人の権利への白けたムードが漂っているのは無理もないことだといえます。
こうして、やっとのことで、1977年を経由して、戦後直後から、「鬼」化しているわたしたちが暮らす日本とへつながるわけです。その延長である2020年代に生きているわたしたちをとりまく環境をみてみましょう。「ズレ」ははたしてどうなっているのでしょうか?
2020年代からみるレヴィ=ストロースの冗談
もう一つの側面からみてみると、1977年あたりには、彼らを安心させるにたる中世のような固定的な社会構造が、まだ割と残っていたという側面があります。経済発展と血縁、地縁、そして、お見合いの仲介といった社会的な縁がまだ存在し、ある程度の絶対感と安定感を個人は感じることが出来ていたのではないかということです。また、同じテレビ番組、ラジオ、雑誌を読んでいた時代でもあります。これが、同調圧力だけでなく安心感・帰属感のようなものも用意していたのではないかと考えられます。
現代の社会を1977年当時と比べてどう変化したのかをざっと挙げてみますと次のようになります。
- 経 済 ・・・発展の停滞・協働ではなく競争の激化、終身雇用の崩壊・グローバル化による新興国 台頭への危惧、組織内の保守化、産業の流動化、経済的機械へのサラリーマンの歯車化・分業の徹底
- 血 縁 ・・・家父長的態度の幼稚性への自覚、機能不全家族の増加、毒親、DV、虐待・ネグレクト
- 地 縁 ・・・都市化、匿名性嗜好、過疎化、祭りの形骸化、仏教の疎遠化、EC市場の影響による街の過疎化
- 社会的縁 ・・・プライバシーの自覚、スマホ・SNSの登場・発展、バイトなど「労働は売るという観念」・契約の概念の定着化、女性軽視への懐疑、結婚への懐疑、ハラスメントの告発 などなど
わたしたちの経済・社会構造からは、1977年の現役世代が得られていた安定感はもう期待できず、むしろ、歴史的な流動状態にあります。個性化の成長を促すスマホの登場や、多様性の認知が進む一方で、個人としての表現できる許容範囲はあいかわらず狭いままなのは、イジメやネットの誹謗中傷をみれば分かることです。
現代のわたしたちが、かつての「私」を放置することを前提とする規範に、模範的にふるまうように努力を重ねたとしても、かつてのような十分な安定感・帰属感を得られません。にもかかわらず、自他の区別を許さない儒教的な上下関係を強いられる状況を約束されます。後進国とは違い、すでに衣食住、社会インフラが整っているので、「物質的な豊かさが幸せである」という素朴な夢からもすでに覚めています。
比較的若い世代が、上の世代の生き方をなぞることで得られるものに魅力を感じられないのは、それなりのわけがあったのです。
今のわたしたちの置かれた現状を知ったうえ、先に引用した、レヴィ=ストロースがいった冗談を今一度読み返してみると、中世的な社会・経済構造はもう西洋にはないし、経済は大切ではあるが、個人を犠牲にして、全体主義化する西洋が犯した失敗は繰り返せない、という皮肉が強調されて感じ取れてしまいます。
注)レヴィ=ストロース・・・20世紀を代表する社会文化人類学者、1977年に来日し、京都大学関係者と「労働」についてのシンポジウムを開く※気になる方は『鬼滅の刃』が少し引くほど大ヒットした理由とは?その2をご覧ください。
日本の「多様性」に感じるモヤモヤ
かつては一枚岩であった「世間」は、ネットとスマホ。SNSの普及により分散化し、土地の制約や、ひとつの世間から逃れる選択肢ふえ、窮屈さが少し解消できるようになりました。
しかし、実際の生活で閉塞感やストレスが減ったのかと聞かれれば疑問です。もちろん全てのコミュニティーがそうではありませんが、「村」に似た小「世間」が増えただけで、「内」と「外」で区分けする排他性、グループ内では同調圧といった、閉鎖的で排他的な環境はあまり変わってないような気がします。同調圧の抜け道として、複数のグループに所属することが可能ですが、その分関係が表面的で刹那的になりがりです。
これは、多様な視点をもった個人意見をしめし、が相互理解をめざして対話し、共通の価値観を見出せる人がふえたという意味での多様性とは異なります。「うち」以外の人との話し合いでは他の意見の存在価値を見出せないために、一方的な言い合いで終始し、創造性や革新的なアイデアや対話による考えのバージョンアップは期待できません。「うち」か「そと」かの二択の世界は多様性ではなく一元的な世界観です。
社会の多様性とは、違いが出会うことで新たなアイデアを生む可能性を用意し、連携しながらも、同時に精神的に自立し、自他の区別のもとの違いの尊重ができている人がどれだけいるのか、という話であって、個人を精神的に依存させ、思考停止させるセクトが多様化するという意味ではないはずです。
他方で、「私」の人生に責任をもって生きようと決意した少数派にとっては、自由と孤独について、どう取り組んだらいいのか、個人はその先に進めばどういう状態になるのか、といったイメージを学べる生きている人が、西洋の先進国のように身近にいない状況にあります。そのため、多様性を実質的に許さない日本社会のなかで、戸惑い孤立し、挫折しやすい環境にあります。
誤解を恐れずいうとしたら、主体や意思、尊重、多様性、精神の自由といったテーマについて、口で言っている内容と実際の行動が一致していない場合が多いのが日本の実情でしょう。
単純に比較することの罠
よく、年配のある程度成功した方が、同じ役職の現役の人を過去の同じ役職の人とくらべ、物質的に豊かになり楽になったくせして「小粒」になったというような意見を見聞きします。戦争経験した世代にくらべその下の世代ときたら、、、経済発展させた団塊の世代に比べその下の世代ときたら、、、ゆとり世代は、、、といった意見です。この意見はこのように、前提となっている構造の下部にある条件がおおきく異なっているということを考慮すれば的外れです。
たしかに、表にあらわれている部分はそうでしょう。しかし、その下の土台の部分で、今を生きるわたしたちは、過去の人よりもはるかに精神的に厳しい条件のなかにおり、しかもはるかに複雑なうえに様々なことを混同し、問題が自覚できず、悪いことに、その意見とおなじ批判を自分に向けてしまっているなかで仕事しています。前提条件が違うにもかかわらず。上の世代と下の世代を単純比較するほど間抜けなことはありません。
違う分母を持つ二つの分数を、分子の部分だけ見て大小を決めているようなものです。同じことは、表面的に日本の若者と欧米の先進国の国々の若者を比べることにもいえます。
次回は、マクロからみた『鬼滅の刃』が少し引くほど大ヒットした理由を総括します。
お付き合いありがとうございました。
参考文献
「三島由紀夫最後の1400日」
[著者] 本田 清
[発行所] 株式会社 毎日ワンズ
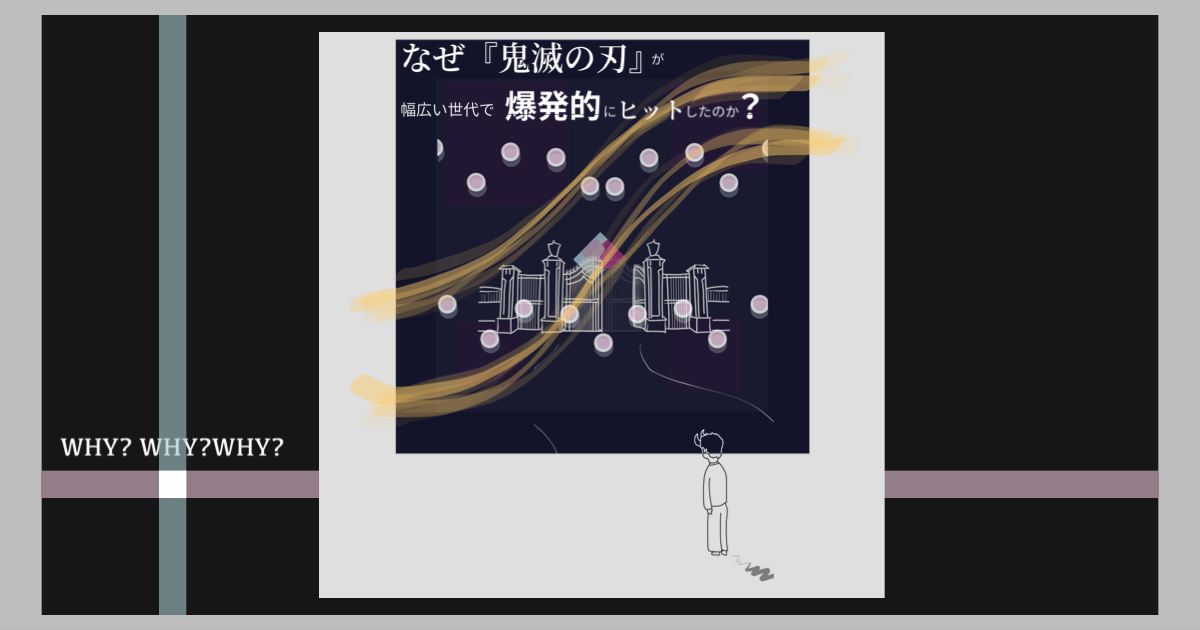
Updated on 4月 12, 2021
なぜ『鬼滅の刃』が幅広い世代で爆発的にヒットしたのか?その2「鬼」化するワタシ
こんにちは、matsumoto takuya です。今回も前回にひきつづきシリーズ「なぜ『鬼滅の刃』が幅広い年齢層に爆発的にヒットしたのか?」をおおくりします。
前回の投稿で、現代にいきるわたしたちは、今・ここにある心・身体、つまり生きている「私」となはれてしまっている傾向があり、わたしたちは『鬼滅の刃』の中に、日常で切り離してしまいがちな「生」の部分をみて、こころ惹かれているのではないか、というところまで行き着きました。
それではどうして私たちは日常で「生」の部分を切り離してしまいがちな状態になってしまっているのかという疑問が浮かびます。この理由のほうが、『鬼滅の刃』が大ヒットしたことの理由としてふさわしそうな気がします。
今回は第2回「「鬼」化するワタシ」です。
では、さっそくいってみましょう。
能動にみせかけた受動
一人でいる時とは、だれかに気を配ったりしなくていい状態であり、言い換えれば、あるがままの自分である時です。そして、あるがままの自分とは肉体であり、心・身体です。
わたしたちは、コロナ禍により、一人でいる時間が増えたわけですが、あるあるがままの自分でいる時間が長くなってくると、あることが問題になってきます。コロナ禍により「みんな」と足並みをそろえる圧力が一時的になくなると、かえって何をしていいのか分からない自分に直面するのです。自分自身に「何がしたいの?」と問いかけてもなかなか返答がかえってこない。なぜ、こんなことになるのでしょうか?
近代以降の人々の特徴について述べているのが、次に引用した文章です。
―――真実―すなわち近代人は自分の欲することを知っているとというまぼろしのもとに生きているが、実際に欲すると予想されるものを欲しているに過ぎないという真実ーを漠然ながら理解できる。このことを認めるためには、ひとが本当になにを欲しているかを知るのは多くの人が考えるほど容易なことではないこと、それは人間がだれしも解決しなければならないもっとも困難な問題の一つであることを理解することが必要である。しかし、それがレディ・メイドの目標を、あたかも自分の目標と考えることによって、遮二無二避けようとしている事柄である。---もちろん我々は、それが俳優や催眠術にかかった人間の行動と同じように自発的なものではないことを知っている。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社
注)「近代人」は現代人とほぼ同義です
わたしたちが日常でなにか選択をするとき、もちろん自分で決めています。しかし、その動機をすこしほりさげてみると、「~したい」よいうよりも「ウケがいいから」といったものや、「みんながそうだから」といった理由である場合が意外と多いことに気が付くはずです。「〇〇歳までに~するべき」というのもそうでしょう。
わたしたちの「~したい」の中には、この「ウケがいいから」や「~すべき」というものが偽装するかたちで紛れ込んでいます。フロムのいう「レディ・メイドの目標」とは、「他人からどう見られるか」という他者評価が「~したい」に巧妙に偽装されてできたものです。
近代人(現代も含む)は、自分で何かを選んでいるとき、二種類の動機を内にもっており、多くは「自分の目標」を動機にしているのではなく、「実際に欲すると予想されるもの」、つまり、他人が評価しそうなものを動機にしている傾向が強いのだと、フロムは言っているのです。その場合、その動機をもとにした行為は、能動にみせかけてはいるが、本質的な意味では受動であると指摘しています。
「レディ・メイドの目標を、あたかも自分の目標と考えることによって、遮二無二避け」てきた「自分の目標」を失っている事実、自分で思っていたより自分が「空っぽ」だった事実を、コロナ禍が暴露したわけです
悩みがない人間とは
もし、他人の目線にそって自分の人生を選んでいけば、悩む必要がなくなっていきます。特にしたいことがわからなくても、何らかのみんなが従う「あるべき姿」に従い、みんなにウケがよさそうなものに従うか、みんながやっているもの、もしくはランキングにしたがえばいいからです。現にわたしたちの周りには、「あるべき姿」やランキングを内容にした情報であふれています。
スマホをのぞけば、手っ取り早い「レディ・メイド」の目標や解決方法を最短で知ることができる環境化では、むしろ、自分が悩みをもっていることが「普通」じゃないような気がしてくるほどです。
しかし、わたしたちに個性のあらわれである心というものがあり、人間は完璧な人などいないということを考えれば、「悩めない」という状態は少し不気味です。この悩むことへの態度について、養老孟子氏はこういっています。
しかしそもそも人間、悩むのが当たり前なのです。今では京都大学の教授になった私の後輩が若い頃、解剖学をやろうかどうしようか迷っていた。それで先生に相談した。すると、その先生は一言、「悩むのも才能のうち」と言ったそうです。それで彼はホッとした。そもそも悩めない人間だってたくさんいます。そういう人がバカと呼ばれるわけです。悩むのも当たり前だと思っていれば、少なくともそんな辛い思いをすることはない。
養老孟司『死の壁』:株式会社 新潮社:173項
「悩めない人間 」を「「バカ」と断言しているところは痛快ですが、養老孟司氏が言うように、人は悩みをもっているのが当たり前です。『鬼滅の刃』では、登場人物の苦悩が繊細にえがかれていて、そういう部分を見ているとついつい引き込まれます。ああ、悩みがあるのはわたしだけじゃないのね、とほっとできて、その登場人物に人間味を感じるからです。
現代に生きるわたしたちは、この悩むこと、悩みをもっていることが苦手です。そしてわたしたちの動機が他者評価に染まってしまっている。悩みを持っていることが苦手で、自分の気持ちを放置してでも、多数派の評価しているものに合わたくなる衝動を内にかかえているのです。
デフォルト化したマザコンと閉塞感
どうしてこのような状態にわたしたちが置かれてしまっているのでしょうか。それは、わたしたち人間に個性がある、ということ関係しています。この理由を述べた文章が次に引用した文章です。少し長いですがここには、重要なことが書かれています。
個性化の過程の他の面は、孤独が増大していくことである。第一次的絆は安定性をもたらし、外界との根本的な統一性をあたえてくれる。子どもはその外界から抜け出すにつれて、自分が孤独であること、全ての他人から引き離された存在であることを自覚するようになる。この外界からの分離は、無力と不安との感情を生み出す。外界はこじんてきな存在と比較すれば、圧倒的に強力であって、往々にして脅威と危険に満ちたものである。人間は外界の一構成部分であるかぎり、個人の行動の可能性や責任を知らなくても、外界を恐れる必要はない。人間は個人になると、独りで、外界の全ての恐ろしい圧倒的な面に抵抗するのである。
ここに、個性をなげすてて外界に完全に没入し、個人と無力の感情を克服しようとする衝動が生まれる。しかしそれらの衝動やそれから生まれる新しい絆は、成長の過程でたちきられた第一次的絆と同一のものではない。ちょうど肉体的に母親の胎内に二度と帰ることができないのと同じように、子どもは精神的にも個性化の過程を逆行することはできない。もしあえてそうしようとすれば、それはどうしても服従の性質をおびることになる。しかもそのような服従においては、権威とそれに服従する子どもとのあいだの根本的な矛盾は、けっして除かれない。子どもは意識的には安定と満足とを感じるかもわからないが、無意識的には、自分の払っていく代償が自分自身の強さと統一性の放棄であることを知っている。このようにして、服従の結果はかつてのものとは正反対である。服従は子どもの不安を増大し、同時に敵意と反抗を生みだす。そしてその敵意と反抗は、子どもが依存しているーーー依存するようになったーーーまさにその人に向けられるので、それだけいっそう恐ろしいものになる。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社:29
第一次的絆とは、母親と乳児の関係や、閉鎖部落内で人と人を結びつけ自他の区別を必要としない絆を指します。個性があるとは、人はそれそれ独自であり独立性を持つということです。完全に自分と重なり合う人は現実には一人もいない、自分の選択が正しいということを測れる指標が外にはないし、マニュアルもないということです。ひとは精神的に成長するにつれ、同時に孤独も自覚する。不安を感じるものなのです。
フロムは、自らの個を自覚し、自由なったと同時に孤独を自覚するにいたった人間がとる選択肢は、二つにわかれるとしてこう述べています。
すなわち他人や自然との原始的な一体性からぬけでるといいう意味で、人間は自由となればなるほど、そしてかれがまたますます「個人」となればなるほど、人間に残された道は、愛や生産的な仕事の自発性のなかで外界と結ばれるか、でなければ、自由や個人的自我の統一性を破壊するような絆によって一種の安定感を求めるか、どちらかということである。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社:29項
「他人や自然との原始的な一体性」とは先に挙げた「第一次的絆」のことです。この関係は依存的であり、強い安定はありますが個の抑圧を前提にします。人はそのまま個性を成長させ、自発性によって社会(人間)と結びつくか、依存ベースの「絆」に服従する形で戻っていくかの二通りとなり、前者が挫折された時に後者が選ばれます。フロムは、自発性によって社会とむすびつけない場合に、依存ベースの「絆」に服従する形で戻っていった人間に多くみられる精神状態を、こう解説しています。
かれは、もし自分が欲し、考え、感ずることを知ることができたならば、自分の意思に従って自由に行動したであろう。しかし、彼はそれを知らないのである。かれは匿名の権威に協調し、自分のものではない自己をとりいれる。このようなことをすればするほど、彼は無力を感じ、ますます同調をしいられる。楽観主義と創意のみせかけにもかかわらず、近代人は深い無力感に打ちひしがれている。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社
なんらかの障害によって、ひとの個性化の発展が妨げられ、内面的な強さや関係を作り出していく力が十分発達できない場合、ひとは無力感と孤独の不安に耐えられず、自分の個性を犠牲にしてまで何らかの「匿名の権威」への同調に駆り立てられる。そして、「匿名の権威に協調し、自分のものではない自己をとりいれ」た人間は、自らの人生の選択を自分でしているようにみえるが実際は、自己にとりいれた「匿名の権威」に従い選択するようになるのです。
「匿名の権威」とは、日本では「世間」、「みんな」、「普通」とか言ったときにさす実態はないが個人の選択に影響を与えてくるものです。「レディメイド」の目標が自分の目標ではなく、「能動にみせかけた受動」であるというフロムの指摘は、取り込んだ「匿名の権威」が用意した目標に自分を従わせているからです。親が「世間」に服従するタイプであれば、そのこどもが個性化を妨げられ、自発的に社会とつながっていけない場合、子どもは親のしたがう「世間」の価値観に服従しなおすことになります。通称マザコンです。
ひとりでいる時の無力感、「他人ウケ」や「世間体」以外にしたいことがわからない状態、そして日本社会にただよう息が詰まようなる閉塞感の出どころは、「匿名の権威」に同調することで今・ここに生きている心・身体をもった「私」を放置していまい、「私」がすっかり委縮している状況から副次的にでてきたものだったのです。
「鬼」化するワタシ
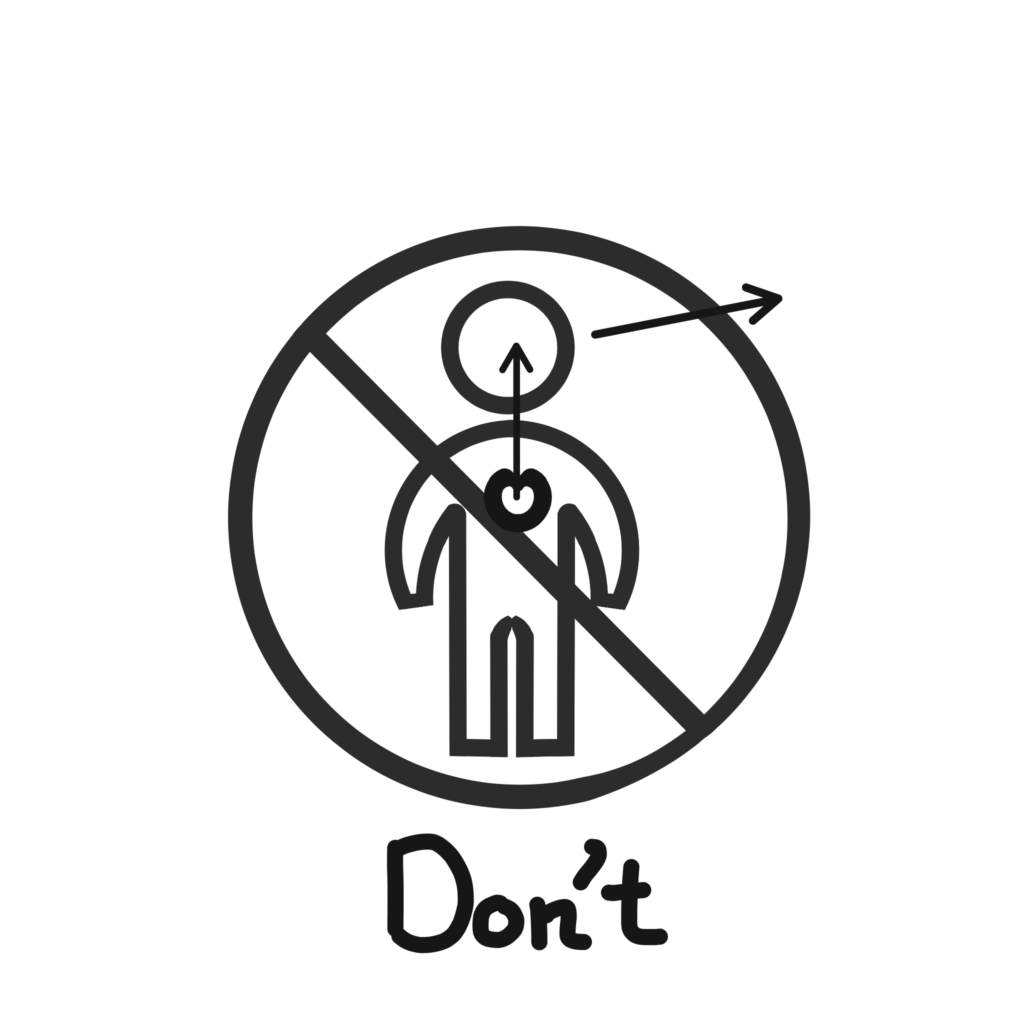
ここであることに気が付きます。「私」を放置しわすれてしまった存在が『鬼滅の刃』の世界にも登場しているのです。それは、「鬼」と呼ばれる存在です。
人間を喰らう存在である「鬼」は、元々は人間でした。かれらは、鬼となることで不死身の肉体を持つ代わりに人間の頃の記憶を失います。人間の頃の価値観を失うかわりに、人を食べたいという消費欲と他を支配できる力への渇望を持つようになりますが、それは自分を「鬼」にした鬼舞辻無惨の価値観です。腕がちぎれてもすぐ再生するので、身体の声である苦しみや痛みに関しておそろしく鈍感です。
いまの日本に生きるわたしたちは、「私」という心・身体という個性が放置されて切り離されてしまっている点、自分の目標の動機が外から用意されてしまっている点、そして、それを自分だと思い込んでいる点でまさに共通しています。そして、心身の声を大事にできず、身体が悲鳴を上げるまで気がつかないか、我慢してしまいます。わたしたちはどうやら「鬼」化しているといえてしまうのです。
その「私」を諦めたことの代償の一つが、フラストレーションです。
早稲田大学名誉教授の池田晴彦氏はこう言っています。
ただ、いくら日本人が不思議な感性をしているといっても、あきらめてばかりいたらフラストレーションがたまる。そこで、いじめてもいい相手を見つけ出して攻撃し、うさ晴らししようとなるわけだ。それが自粛期間中のパチンコ叩きであり、自粛警察であり、コロナ患者や医療従事者への嫌がらせであり、亡くなったった女子プロレスラーの木村はなさんへの誹謗中傷であったわけだ。
池田晴彦 『自粛バカ-リスクゼロ症候群に罹った日本人への処方箋-』宝島社新書
この時に、ストレスをぶつける対象にされれやすいのは多くの人と違うことをするマイノリティなんだけど、実は日本人が一番気に入らないのは、自分が我慢ているのに、楽しそうにしていたり、上手くやっていたりするやつなんだよ。
自由の権利や、多様性を制度としては認めているのに、「私」をお預けされている状態と、その状態をせまる同調圧力は、このようなフラストレーションや無力感をわたしたちの内にため込ませます。そのため込まれて腐敗したストレスの憂さ晴らしとして、自分が窮屈な思いをして服従している同調先に同調しないマイノリティーがやり玉にあげやすく、度を越えてバッシングしてしまう衝動にかられてしまうのです。「悩めない」状態は、このように極端になりやすく、また自身の考えを顧みることが難しくなります。
『鬼滅の刃』は主人公の竈戸炭次郎が、鬼となった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼の侵害にあいながらも大切な人を人間に戻す方法を探していく物語です。この物語は、こうもいいかえれます。心・身体をもった「私」としての生きている主人公たちが、人間としての心・身体をうしない「私」をわすれた存在である「鬼」の侵害に屈せず立ち向かい、大切な人の人間としての性質である「私」を取り戻す戦いの物語である。
日本の環境は、わたしたちに「私」を放置するよう迫る、目にみえない同調圧力をもっています。この圧力は、「多様性のある社会」を掲げているのにもかかわらず、なぜか以前として強力で、わたしたちの内にフラストレーションを潜在的にため込ませます。知らず知らずに「私」が窒息しそうになり「鬼」化していくワタシに、「私」の側にたって戦うストーリーはハマるべくしてハマったといえます。
もちろん、漫画、アニメの技術的な構造や日本古来の物語への相関といったヒット要因がいろいろ考えられるしょうが、社会現象ともよべる爆発的ヒットを可能にした説明ができません。幅広い年齢層に心・身体を持った「私」として生きることへの飢えに近い需要がなければ、少年漫画・アニメの枠内でのヒットで終わっていたはずです。
ところで、どうして今の日本は、多くの人が閉塞感をいだくほど、息苦しい状態にますますなってきているのでしょうか?
最近はスマホの登場で海外の欧米の情報が個人レベルで自由に手に入る環境があり、多様性のもった社会の必要性は周知されています。そして、ご存じの通り日本は個人の自由を前提とした社会制度をとっている民主主義国家です。社会の成熟につれて同調圧力も減り、閉塞感が打破されていてもいいはずです。わたしちを「鬼」化させる日本の環境はいつからはじまったのだろうか?それはどうしてなのか?どのようないきさつで今の環境がつくられてきたのだろうか?という疑問が浮かびます。
次回では、「鬼」化のルーツを、近代史をさかのぼりながら探っていきます。
お付き合いありがとうございました。
参考文献
「構造・神話・労働 クロード・レヴィ=ストロース日本公演集」
[作者] 大橋保夫編 三好郁郎・松本カヨ子・大橋寿美子訳
[発行所]株式会社みすず書房
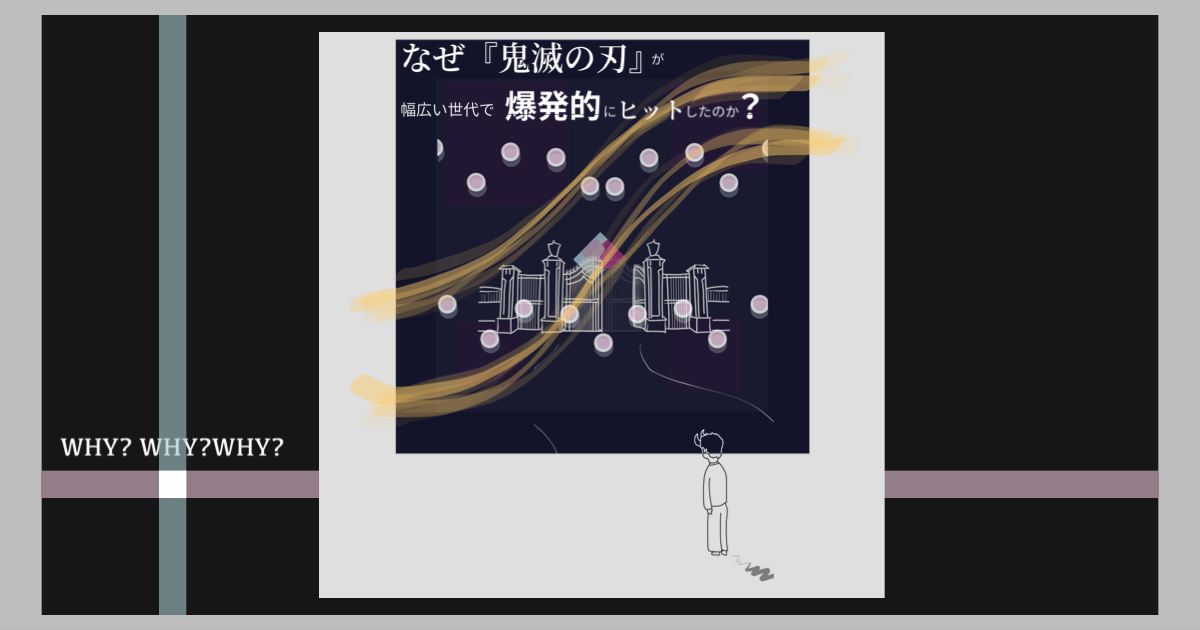
Updated on 4月 11, 2021
なぜ『鬼滅の刃』が幅広い世代で爆発的にヒットしたのか? その1『鬼滅』にあって日常にないもの
こんにちは、そして、明けましておめでとうございます。matsumoto takuya です。今年の初空はとても気持ちがよいものでほっとしました。コロナ禍中ではありますが、今年もよろしくお願いします。
今、日本中で大ヒットしている吾峠呼世晴による『鬼滅の刃』。2020年に公開された『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』は歴代興行収入の新記録となり、2020年に公開された『千と千尋の神隠し』の興行収入を超え歴代1位になりました。『鬼滅の刃』もはや社会現象と言えでしょう。
ただ、この短期間での幅広い年齢層を捉えた爆発的な大ヒットは、わたしにはすこし不可解でした。
『鬼滅』はたしかにおもしろい。しかし、原作は少年漫画である。
もちろん、わたしは少年漫画だから世代をこえてヒットすることがありえないと言いたいのではありません。ただ、読み手に少年を想定している少年漫画は、表現の範囲がある程度限定されるので、射程範囲となる人の範囲も必然的に万人ではなくなるはずです。たとえば、演劇の場合はリアルを重視するひとには少し引いてしまう部分があったりします。それなのに、幅広い年齢層に、しかも、短期間に多くの人にハマったというのは考えてみれば不思議なのです
社会現象とは、その社会に生きる多くの人々が抱いていると同時に、言語化できないために問題をや願望を把握できないことを、代弁しているものだと考えられます。つまり、社会現象はなんらかの”訴え”であるということができるのです。
『鬼滅の刃』には、わたしたちの日常で必要なのに不足しているものが、それもジャンルや年齢層の想定の枠さえもすっ飛ばしてしまうほど、欠乏しているもの、もしくは、本当は切実に困っているのだが言えないような日本社会への問題提起が描かれているのかもしれない。そういう着想がなんとなく浮かんだのでした。
『鬼滅の刃』には、わたしたちの日常で必要なのに不足しているものが、それもジャンルや年齢層の想定の枠さえもすっ飛ばしてしまうほど、欠乏しているものが描かれているのかもしれない。そういう着想がなんとなく浮かんだのでした。
ところで、今、書店で売れている一冊に、エーリッヒ・フロムの『愛するということ』という本があります。著者であるエーリッヒ・フロムは20世紀を代表するドイツ・アメリカの社会心理学者、精神分析家で、『愛するということ』は、1956年に出版されて以来、世界的なロングセラーとして知られています。
日本でも、1959年に邦訳が出版されて以来、新訳版も併せて50万部も発行されており、いま売れているものはその新訳・新装版です。私の感覚では、「愛するということ」なんて直接的なタイトルの本は、今の感覚では引いちゃうか、人目が気になちゃって売れないだろうな、とたかをくくってしまっていたので、世代をこえて売れつづけていること、それが新訳として今改めて多くの日本人に読まれているということは意外でした。
フロムの残した仕事の中にも、世代をこえて今のわたしたちを引き付ける何かがあるようです。そして、『鬼滅の刃』が異常なまでに大ヒットしたこのタイミングでまた売れ始めているのです。
フロムの伝えたいことと、『鬼滅の刃』の世代を超えた大ヒットとの間には、今の日本に生きる、わたしたちが求める重要だがモヤモヤして捉えきれないでいる大事ことが隠れているかもしれない。
このシリーズは、『アニメ『鬼滅の刃』』から『劇場版『鬼滅の刃』無限列車編』までの内容を、エーリッヒ・フロムの代表作である『愛するということ』・『自由からの逃走』の内容をメインに関連づけながら、なぜ『鬼滅の刃』がこれほどまで、メディア媒体が多様化した今の日本で幅広い年齢層で大ヒットしたのか?それが意味することはいったいなんなのか?その秘密を明るみにだそうという試みです。
ではそっそく、シリーズ、「なぜ『鬼滅の刃』が幅広い世代で爆発的にヒットしたのか?」をはじめていきたいと思います。
以下、「アニメ『鬼滅の刃』」~『劇場版『鬼滅の刃』無限列車編』の内容を一部含みます。
『鬼滅』にあって日常にないもの
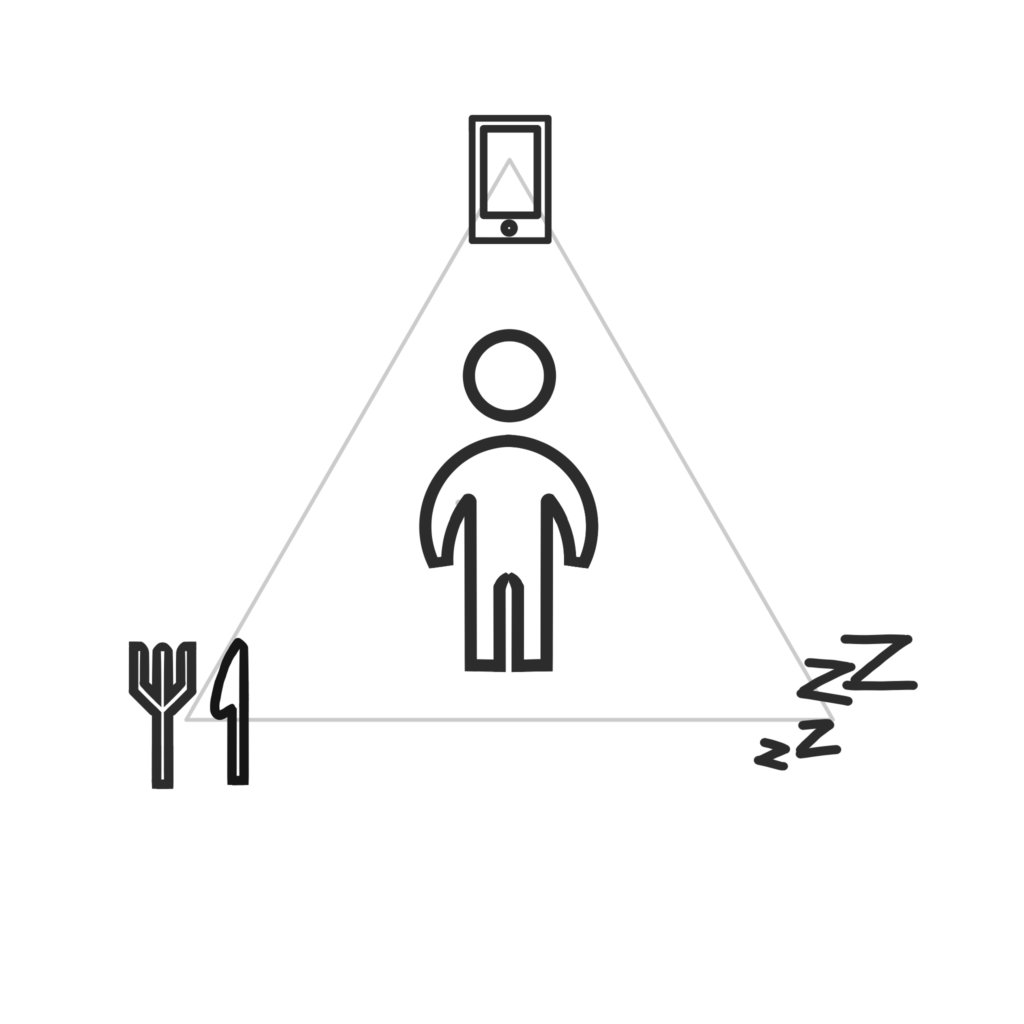
人が何かにハマったりするのは、面白いからという理由だからなのですが、同時に、その「ハマった」ものが普段の生活ではあまりみられない珍しものだからである、と見ることもできます。特別な関心がある場合を除いて、見慣れたもの、ありきたりなものであったらいちいち見向きもしないはずです。
『鬼滅の刃』の大ヒットから読みとれることは、少なくとも、日常ではあまり経験できない内容が含まれている、ということになります。そして、その内容が、日本人の割と多くの人に共通していた、ということです。
また、大ヒットは「不足しているもの」が得られる時にも起こりえます。もし、大きな都市でお茶をする場所一つもなかったところに、カフェができれば、そのカフェはきっと繁盛するはずです。
『鬼滅の刃』に「ハマった」人の属する世代が10代という少年漫画の対象としている世代を大きくこえて、社会人の20代、30代。40代と幅広い世代に、しかも多くの人が「ハマった」ことからいえることは、日常ではあまりみられず、同時に、日頃の暮らしのなかで「不足している」何かを『鬼滅の刃』という作品が、そっと差し出してくれたということです。
そして、メディアが多様化した昨今、それが短期間に、爆発的にヒットしたということは、『鬼滅の刃』で追体験できるものが、わたしたちの日常ではかなり珍しく、同時に、多くの人が切実に欲しているものである、とみることができるわけです。
コロナ禍がふっとばした臭いものにしていた蓋
2020年、コロナウイルスが世界規模のパンデミックを引き起こし、世界規模でわたしたちは感染防止のための自粛生活を強いられました。
コロナ禍の生活で一体何が変わったのでしょうか。いろいろ考えられると思いますが、物理的な側面からは、集まる機会が減り一人でいる時間が増えたこと、精神的な側面からいえば、「普通」や「常識」というものが絶対的でも永続的なものでもないことが自覚できてしまったことだと思います。
わたしたちの生活スタイルの劇的な変化は、いままでは見ないようにしてきた問題を浮き彫りにしました。今までよりかかってきた不変で絶対だと思っていた「普通」が揺らぐ中で、みんなと一緒にいることができなくなることで浮上してくる問題とは、「自分ってはなんなんだ」というタイプの問題です。一人でいる時間が増えて、いい機会だから何かしようと思っても、自分のしたいことが実はわからないという現実の自分に、強制的に直面したわけです。
「me too」運動、パワハラ等のハラスメントについての下からの告発、「毒親」という言葉、組織内の個人の保守・画一化による成長の停滞といった、先が見通せないタイプのニュースが明らかに増えていくにつれ、かつての慣習や生活スタイル、規範といったようなものに影を落とすようになりました。それでも、大きなビル群、同じ制服に身を包んだおなじ組織の身内と、決まったペースで決まった時間に、繰り返し顔をつきあわせてたことで、「なんだかんだ変わらないよ」とその不安に蓋をすることができていた。それと同時に、現代の日常が個々人に要求するテンポがあまりに息つく間をあたえないので、せわしなく、疲れ切っており、「自分を知る・自分と向き合う」という実存的なテーマは向き合うだけ時間の無駄であり、そんなことを考える時間もなかった。それでも、世の中がいいもわるいも、なんやかんや回っていたのです。
それがコロナ禍により、経済的な不安ももちろんありますが、わたしたちは半ば強制的に今までごまかし続けてきた「自分についての問題」に向き合わざるおえなくなってしまったわけです。それが、コロナ禍にみられる私たちの不安の増大の背景の一つといえます。
今までどおりの全幅の信頼で「普通」によりかかるもどうもしっくりとはまらず、かといって、方向転換し自らの人生を充実させて安らぎとハリを得ようと思っても、いままで見ないようにしてきた自分の空っぽさや、予期せぬ無力感や無意味感や不安といったものがとぐろを巻いている。このように、いままで見ないようにしていた「臭いもの」への蓋がコロナウイルスのパンデミックにより吹っ飛ばされてあらわになり、わたしたちを戸惑わせているのが、コロナ禍の特徴の一つといえます。
そんな中『鬼滅の刃』ブームが日本中を一気に駆け巡りました。
かつての「普通」が絶対的なものではないという自覚、一人でいる時の無力感・無意味感、時には焦燥感そして不安。このあたりに『鬼滅の刃』が世代をこえた異常なほどの大ヒットと無視できない関係が隠れていそうなのです。
死は「生きてるか」と問いかける
ここでいったん、話を『鬼滅の刃』の内容にうつします。
死や苦悩という一見ダークなものが『鬼滅の刃』を通奏低音のように流れています。
主人公の竈戸炭次郎をはじめ、主要な登場人物のほとんどは、親しい人をなんらかの事情で失っています。ほとんどの登場人物が身近な人の死を経験しているという前提は、通常では「いきんなや」とか「真面目すぎ」と、つい言ってしまいがちな言動にたいして、真にせまる迫力を登場人物にあたえ、これが『鬼滅の刃』の世界観に説得力をあたえています。
死はいくら富豪になろうと、どんなに権力をにぎろうと、例外なくわたしたちに訪れるものです。もちろん、わたしたちは知識でそれを知っています。でも、それは本当でしょうか?この物語の登場人物が経験したような深さの認識と同じ深さで死の認識をわたしたちはできているのでしょうか?
東京大学名誉教授の養老孟司氏は、こんなことを言っています。
人は自分のことを死なないと勘違いするようになりました。そんなことはない、と仰るかもしれません。でも、現に高層団地から死は排除されていました。人間は死ぬということが知識としてわかっていても、実際にはわからないのです。
養老孟司『死の壁』:株式会社 新潮社:26項
養老孟司氏は、解剖学の献体(生前に自分の遺体を医学の発展のために利用承諾した人の遺体)を都会の高層団地に引き取りに行った時に、高層団地の作りが棺を運搬することを全く想定していない造りであったために棺の搬出に苦労したことで、そういう考えが腑に落ちたそうです。
現代に生きるわたしたちは、死からキレイにきりはなされた生活のなかにいて、構造上、リアルな死と向き合う必要がなくなっています。これは衛生観念が発達した近代以降は当たり前のことように感じられますが、歴史を見れば、ながらく死は人の生活の身近にあったようなのです。
人類の歴史を見ると、生活のなかの実際の身近な死と接することでその知識を認識まで深めていました。しかし、現代に近づいていくにつれて、その傾向が変わります。
20世紀を代表する社会心理学者のエーリッヒ・フロムは現代人と死との関係をこのようにいっています。
我々の現代は単純に死を否定し、そのことによって、生の根本的な一つの面を否定している。死や苦悩の自覚が、生の最も強力な刺激の一つとなり、人類の連帯性の基礎となり、また歓喜や激しさや深さをもつためにかくことのできない経験となることを認めるかわりに、個人はそれを抑圧することを強いられている。しかし抑圧が常にそうであるように、抑圧された要素は、視界から消えても存在することをやめない。こうして、死の恐怖はわれわれのあいだに不条理な存在として生きている。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社
「死や苦悩の自覚が、生の最も強力な刺激の一つとなり、人類の連帯性の基礎となり」とはどういうことでしょうか。これは、実際に身近な人の死に接すると、人はその反対である「生」がどのようなものであるのかということに気がつくということです。人間はみな唯一無二であり、同じ人間は二度と生まれてこないこと、等々を喪失の痛手のなかで認識していき、それが、生きていることの貴重さの自覚や、まだ「生きている」人の尊さへの気づきを与えてくれます。喪失はほんとうに辛いことですが、その経験はより深い眼差しで他者見ることを可能になり、世界との結びつきを改めて強めてくれます。失ってはじめて自分にとって何が重要であったのかということを痛みを通して学んでいく、それが人間なのです。
また、わたしたはやはり自然に服する生き物なのだということを実感させられます。生きているということは変化する心・身体をもった存在であるということ。生き物は生まれ変化を繰り返しやがて死ぬ存在であること。その生き物の環の中に、わたしたちも含まれているのだ、という腑に落ちた理解を、「死」に触れた経験はもたらしてくれるのです。
このように「死」は、人々に「生」の側面をあらためて気がつかせてくれる働きを持っていたのですが、現代のリアルな「死」から切り離された環境は、衛生と引き換えに、わたしたから「わたしたちも生き物なのだ」という気づきの機会までなくしてしまっていたようです。
それが、コロナ禍により死が突如他人事となくなり、日本のみならず世界中で『鬼滅の刃』と似たような雰囲気がうまれています。いままでは、辛気臭いこと言わないで、なるだけ楽観的にいこうというような態度が支配的であった雰囲気に変化がうまれ、「真面目」と一蹴されてきた内容についても、それはそれで「あり」だという空気感が広がってきたのです。
「今・ここ」と全集中
『鬼滅の刃』の世界では、主人公の炭次郎をはじめ、自身の身体の声を大切にし、みずからの感性を有効に役立てて活躍する人物がメインにすえられています。例えば、炭次郎は嗅覚が、我妻善一は聴覚の鋭敏さが特徴です。みな異なった感受性を持っていて、それぞれの登場人物に特別な魅力を与えています。
また、特殊な呼吸法である「全集中の呼吸」も身体への尊重がみてとれます。かれらが、集中している先は「今・ここ」です。そして、生きている身体の声を聞き取れるのも「今・ここ」だけです。かれらは、「いま・ここ」にある心・身体に意識を集中して耳をすますことで「生」の力を引きだしているのです。身体の中にあるものが心であり気持ちです。かれらは心・身体をとても大切にしていることがわかります。
これに対して、現代に生きるわたしたちはどうでしょうか。今・ここにある身体の声や感覚・自分の気持ちや想いに集中できているでしょうか。養老孟司氏は、こう言っています。
人間は変化しつづけるものだし、情報はかわらないものである、というのが本来の性質です。ところがこれを逆に考えるようになったのが近代です。
これがわたしが言うところの「情報化社会」です。「私」はかわらない。変わっていくのは世の中の情報である、という考え方の社会です。脳中心の社会といってもいい。
養老孟司『死の壁』:株式会社 新潮社:28項
注)近代は現代も含みます
近代以降のわたしたちの意識は、「全集中」とは反対の方向に向いてしまっている。むしろ、変化する「心・身体」の声から離れてしまい、変化しない「情報」として自分自身を認識してしまっていると、養老孟司氏は言っています。
現代の都市生活は、身体が開放的になれる自然環境は、ごくわずかでほとんどが人工物です。さらに、せわしなく急き立てられてうごく人の流れのなかで、スマホという便利な情報入手ができるツールの登場により、人と直接かかわらない状況で、頭のなかが常にデジタルな情報で溢れかえっています。
筋力とおなじように使われなかった能力は衰えていきます。自信の身体の感受性やそれを聞き取る能力も衰えていきます。すると、どういうことが起こるのかといえば、『鬼滅の刃』の全集中とは逆の結果がおこります。つまり、身体に秘められた力がなえ萎んでいくのに対して、意識が「今・ここ」にはないデジタル化された情報でいっぱいになり、常に過剰にはたらいてしまうため今、余計に身体の声をうけとる容量が埋まってしまうということです。
これは人が何か行動をする際の動機にも関係してきます。自身の心・身体から生まれる気持ちや感覚から切り離されてしまえば、その人の行動の動機は、外から得られる他者評価や損得勘定といったものに置き換わっていくことになります。
自分のしたいことがわからない、関心がうごかない、元気がない、生活に生きている実感がない、といったことは現代の特徴だといわれて久しいですが、身体の声との親密な関係から、それからきりはなされた「脳中心」のライフスタイルに変化したことと密接な関係があるのです。
身体の飢え~脳中心の生活~
一人でいる時とは、だれかに気を配ったりしなくていい状態であり、言い換えれば、あるがままの自分である時です。そして、あるがままの自分とは肉体であり、心・身体です。
わたしたちは、コロナ禍により、一人でいる時間が増えたわけですが、あるあるがままの自分でいる時間が長くなってくると、あることが問題になってきます。コロナ禍により「みんな」と足並みをそろえる圧力が一時的になくなると、かえって何をしていいのか分からない自分に直面するという問題です。自分自身に「何がしたいの?」と問いかけても返答がかえってこないわけです。
現代人について養老孟司氏が「脳中心」といったのは、自意識が自身の心・身体をきりはなしてしまっていて、自意識が独裁者のように心・身体を無視して見下すようにふるまっているということです。 『鬼滅の刃』が舞台とする大正時代に比べ、現代の都市生活では、土や自然に触れる機会そのものが、ほんの100年あまりで激減しました。日本特有の季節の風土や風情に根差しして生きるある種の安定感が失われ、「脳中心」の「今・ここ」はない心配事や脳内でつくられた「あるべき姿」ばかりがあくせく空回りしつづける環境下にあるのです。
そんな現代の反響のように『鬼滅の刃』の世界では死は日常的にでてきます。その背景のなかでいま・ここにある心・身体を尊重し信じ引き立てることで、「生」を全力で生きている炭次郎たちが浮かび上がり輝かしく映る。わたしたちは、『鬼滅の刃』の中に、日常で切り離してしまっている、人間の生きている心・身体、つまり、日常で切り離してしまっている「私」自身をみいだして、「生」への飢えを満たしているのではないでしょうか。
一人でいる時とは、だれかに気を配ったりしなくていい状態であり、言い換えれば、あるがままの自分である時です。そして、あるがままの自分とは肉体であり、心・身体です。
わたしたちは、コロナ禍により、一人でいる時間が増えたわけですが、あるあるがままの自分でいる時間が長くなってくると、あることが問題になってきます。コロナ禍により「みんな」と足並みをそろえる圧力が一時的になくなると、かえって何をしていいのか分からない自分に直面するという問題です。自分自身に「何がしたいの?」と問いかけても返答がかえってこないわけです。なぜ、こんなことになるのでしょうか?
次回は、このあたりから探っていきたいと思います。
お付き合いありがとうございました。
参考文献
「死の壁」
[作者] 養老 孟司
[発行者] 佐藤 隆信
[発行所] 株式会社 新潮社
「自由からの逃走」
[作者] ERICH FROMM
[訳者] 日高 六郎
[発行者] 渋谷 健太郎
[発行所] 株式会社 東京創元社
Updated on 1月 9, 2021
『寺山修司とポスター貼りと。』ブックレビュー
BOOK REVIEW
こんにちは、matsumoto takuya です。今回は笹目浩之さんの著書『寺山修司とポスター貼りと。』のブックレビューです。
この本との出会いは偶然で、たまたま見つけた寺山修司さんのイベントぶらっと立ち寄った際に陳列されていたのを見つけて、なんともなく手に取ったというものでした。それまでは笹目浩二氏も、さらには寺山修司氏のことも全く知りませんでした。
こういう時に、わたしの頭の中で軽く葛藤が巻き起こります。全く世間に知られてない人、別に興味があってきたイベントでもない、全然おしゃれじゃないし、ポスター貼りなんてわたしの人生になんの役にもたたなさそうだし、なによりお金がかかる、という考えと、偶然にみつけてなんか気になるなーという心がかるく対立するのです。
こういう時、わたしはできるだけ後者を選ぶようにしています。わたしは人様に自慢できるほど成功体験は恐ろしいまでにないのですが、失敗経験は豊富なので、こういう時どちらを選ぶとつまらない結果となるということは分かります。わたしは、少年時代からほとんど前者を選んできました。その結果は、他の人たちと同調するのには効果的だったのですが、自分の世界が全く育ちませんでした。虚しい。
そんなこともあって、できる範囲で、ささやくようにか細いほうの心の意見をとるようにしています。この本は、そうして手に取った一冊です。
笹目浩之氏は主に演劇のポスターを貼る仕事を創出し、今では寺山修司記念館の副館長であり、寺山修司関連のイベントや、演劇のプロデュースなど多岐にわたる活躍をなされている方でした。そんな彼は、今のあなたの仕事は何ですかと質問されたたら胸を張って「ポスター貼りです」と答えるそうです。権威に媚びる癖があるわたしだったら、寺山修司記念館副館長や演劇プロデューサーという響きがよさげな肩書を言ってしまいそうです。
この本は、そんな彼がどうしてポスター貼りなどという特殊な仕事を創出するにいたったのか、そもそもポスター貼りは何なのか、そして、どうして権威がありそうな肩書を差し置いてはっきりと「仕事はポスター貼りです。」と言う個とができるに至ったか、といった内容が書かれています。全く「普通」ではない匂いがプンプンします。自分と社会の折り合いをつけて生きているひと、自発的に社会に突っ込んで活動している人のにおいです。
この本は、自分として生きたい人と思う方には是非おすすめの一冊にはお勧めの一冊です。
ここでは、彼がなぜ、主体的に活躍できるにいたったのかという点を少し探っていきます。
以下、少しだけ内容を含みます。
ポスター貼りの男の誕生 笹目浩之
なぜ、彼が主体的に活躍できているのか、という点を探っていくまえに笹目浩之氏の経歴をざっと紹介したいと思います。
彼は田舎の出身で、浪人生活に専念するために安い下宿を見つけ東京に出てきて一人暮らしをしながら早稲田大学を目指すも落ちてしまいます。他に受かった大学に通うも気持ちが全くのらず、通うのを辞めてしまいます。親に内緒で仮面浪人という形でもう一度早稲田を目指すもも、仮面浪人するためのバイトに時間をとられ、早稲田へのあこがれもドラマの影響程度だったので次第に熱が冷めていき、お金がかからない行きつけの喫茶店で過ごしたり、ぶらぶらするようになります。
その喫茶店で顔なじみとなった人が演劇好きで、その人に演劇に連れていかれて出会ったのが寺山修司の劇『レミング 壁抜け男』でした。それに感動し、演劇に熱中し、演劇に関係したことをしたいと思った心に沿うかたちで、寺山修司の関係者と出会っていき、劇のポスター貼りの仕事を頼まれて、紆余曲折を得て本業となったのでした。
ざっと、彼の経歴を眺めると、劇に感動し、劇が好きになり、好きなことに関わるように仕事を選んだというよくある筋書きで、ああこのパターンね、かれはラッキーだったね、とつい先走って思いがちです。
しかし、そこには大事な見落としがあります。彼はそもそも、わざわざ浪人のために東京で一人暮らしをするために安下宿を探したり、両親を説得したりと、自分の心に耳を澄ませそれに沿うようにしてその時にできることを実際に行為してきた点です。仮面浪人をしようと思い立ったりしている点も見逃せません。
確かに、彼の人生を決定的に方向付けたものは熱中できる演劇に出合えたからなのですが、そのような人生を左右する感動的な出会いをキャッチできる前段階のようなものを用意できる力が十分育まれていたこそ、その出会いが本物の出会いになったといえるのです。そんな前段階のようなものがもう一つあります。
追い立てられない暇な時間と無駄なこと
感動的な出会いをキャッチできる前段階のようなものの一つに、追い立てられない暇な時間と無駄なことを自分自身に用意できるかどうかというものが挙げられます。これは、世間でいう狭い「成功」を求めるタイプの人の努力をしない努力が必要です。
なぜこんな変な言いまわしになるかといえば、ここでいう世間でいう狭い意味での「成功」はそうしないといけないんだという無根拠な恐れからでてきたもので、その手の努力はしないではいられない駆り立てられた努力だからです。
ではその努力の中身は何なのかといえば、自分の感じ方、思い、考えまでをみんな同じになるようにすることです。人間の標準化とも呼べそうなものです。が、そうしないとなにか罪悪感と不安を感じ、逃げるように「何かしなきゃ」と駆り立てられてしまう。しかも、これは結構時間を取られます。
わたしたちは、この狭い意味での「成功」にとって役にたたないことをすることに、罪悪感を仕込まれているように思えます。この罪悪感のなかで、追い立てられない暇な時間と無駄な時間を自分自身に用意することは、ある意味努力がいるのです。
さて、自分を標準化するために、みんながやっていることを追い求めてしまうとそれだけで時間がつぶれてしまいます。そのうえ、「働かざる者食うべからず」という日本ではおなじみの世間体に脅されて仕事をしはじめると、ひたすら与えられた要求をこなすことに時間をつぶされます。世間から認められている、同調しているという安心感は得られますし、やることは増えていくので、まっとうな悩みにさえ感じないで過ごせるかもしれません。
それはそれでいいではないか、と思われる方がいるかもしれませんが、そうやって得られる「成功」に虚しさを感じる人もいるのです。なぜなら、その成功には「私の心」がないからです。
わたしたちはモノではなく人間なんですから。江戸時代の儒学者、貝原益軒は”志とは己によりて有するところ、別人に管するにあらず”(辻本雅史『「学び」の復権 模倣と習熟』岩波現代文庫)といっています。これは学びについてのスタート地点のことを言っているのですが、これは生きること全般に言えることだと私は思います。まず、精神的に自立した1人の人間にならなければなりません。
それに、そうこうしていくうちに、いろいろな責任だけが増えるので時間はあっという間に過ぎていきます。これでは、感動的な出会いには永遠に出会えませんし、自分の世界観が育ちません。自分の世界観とは自分の世界に対する何かへの関心であり興味であり愛です。自分の世界観が育たないとは、世界に関する無関心と同じことです。
世界観を広げていくこと、関心を広げて深めていくことで、感動できる出会いにつながるし、その出会いに気が付くことができる。そして大事に思えるようになってそれが自分の方向性となる。というような流れの起点が世間的に無駄だと思われていることや暇な時間を自分に用意することなのです。
そういうわけで、笹目さんに動機を与えた演劇『レミング 壁抜け男』という運命的な出会いの前の、おもろいものはないかと自信の完成のアンテナをはってブラブラしていたことは大きな意味があったのではないかとわたしは思うのです。
しかし、これはなぜか異常な罪悪感を覚えます。もちろん誰にも迷惑をかけていなので罪ではないのですが、日本育つとこの価値観が以上に膨れ上がって自分に迫ってくるように感じてしまうのは私だけではないと思います。
人間を信じる勇気
この恐れが、わたしたちに、「あるべき姿」を次から次へと押し付けてきて駆り立ててきます。『鬼滅の刃』的にいえば「心の無限ラットレース編」状態です。
そのうえ、この恐れは主体的に生きたいと思い立ち、いざどうしようか右往左往している時にも容赦なく襲ってきます。ここではそれに負けない信念をもつ必要があります。それは人間の人間性を信じる勇気です。人間には自分も含まれます。人間の成長できる可能性を信じられる勇気を持つこと、それが、感動的な出会いの前段階に必要なもう一つの重要なことです。以下この人間への信用を信念と呼ぶことにします。
そうやって生きることはある種の心もとなさがつきものです。なんせ同調していたからこそ得られる孤独への鎮痛剤が得られないのに、肝心の信念が全くもって頼りない。だからこの信念を育てて大きくする必要があるということです。どうやって信念を深めることができるかは、実際にそうやって生きている人と出会い実際に目の当たりにするのが一番説得力があるように私には思えます。笹目さんの場合は寺山修司でした。
「人間」を信じていると「人間」と出会える
自分の人間としての成長を信じ生きようとする人は、社会で孤立してまうというような先入観がわたしたちにあります。しかし、笹目さんのエピソードは、そういう人は、同じように人間を信じて勇気を持って生きてる人の存在に気が付き、気が付かれ、そして惹きつけられる繋がっていくという事実を教えてくれます。自分を標準化しみんながいいと思っていることに同調しなくても孤立はせず、自分として社会のなかで自発的に活動している志を持った他の人に出会えるのです。
そうゆう自発的なつながりによって信念を持てた人は社会と再び結び付けらるということです。ロボット的人間関係、利害関係者だけではなく内実がある関係がそこにはあるんですね。
別の角度から見れば、心もとなさを背負っていきているからこそ、同じように人間を信じて生きている先人や言葉に気が付けます。笹目浩之さんは、寺山修司の劇『レミング 壁抜け男』に感動したそうですが、若き日の笹目青年が自分を信じて勇気をもって試行錯誤をしてきて、自分なりの問題意識を育んだからこそ寺山修司の内実あるメッセージが響いたのではないでしょうか。このメッセージが偽物か本物かは心がなければ判断できないものです。
なぜ彼の本がおすすめなのか
話を信念に戻します。信念を深めるには、実際にそうやって活動している人と出会い見習うというほかに、いろいろな方法があると思います。その中の一つが、そうやって生きてきた人の何らかの創作物に触れるということがあります。本はその中でも代表格です。
信念をもって社会と折り合いをつけて実際に生きている、もしく生きた人が人が自分と同じように悩み、時に弱気になったりしたのだということが分かるとほっとしますし、その後の展開を読むことで、お先真っ暗のようにしかみえなかったその先のイメージが自分の中に「痕跡」として残ります。
自分が弱気になりやっぱ同調欲に駆られている時、「世間」に服従するのが正しいという刷り込みを信じるのか、(自分)人間の可能性を信じる信念の二つの考えが綱引きしているような心の状況にあるということができます。そういうときにこの「痕跡」は信念をもつ味方となってくれるのです。
笹目浩之さんの著書『寺山修司とポスター貼りと。」は、まさにその「痕跡」得られる内容のある一冊でした。冒頭でわたしが、自分として生きたい人と思う方には是非おすすめの一冊といったのはそういうわけがあったのです。
以上、「『寺山修司とポスター貼りと。』ブックレビュー」でした。おつきあいありがとうございました。
参考文献
『寺山修司とポスター貼りと。』
[著者] 笹目浩之
[発行者] 角川文庫
Updated on 1月 18, 2021
ルドン・ルートレック展
三菱一号館美術館に現れたルドンの花
@三菱一号館美術館
こんにちは、matsumoto takuya です。今回は三菱一号館美術館で開催されている「ルドン・ルートレック展」について取り上げます。
ルドンとルートレックは共に19世紀後期から20世紀初期にかけて活動したフランス人画家です。ルドンは同世代の印象派とは違い幻想の世界を描き。一方ルートレックも印象派とは違うスタイルで娼婦や踊り子のような夜の世界の女たちを多く描いています。
一方は内向的、もう一方は外向的な作風でメリハリあるキュレートのほか、近い世代に活躍した他の画家、ミレー、ゴーギャン、ボナール、セザンヌ等の名画も鑑賞でき、良質の絵画を堪能できる贅沢な内容でした。
仕事が良質であったかの一つの見方として、創作物が時間の重圧に耐えて残るかどうかという見方があると思います。今回は、この展覧会で紹介されている画家がなぜ後世に残る絵を残せたのか、「時代を超えてつながるもの」になりえたその秘密をすこし探っていきたいと思います。
ミレーの農夫とイギリス王朝の肖像画
この展覧会でわたしが「一番いいものをみた」と感じたのルドンでもロートレックでもなく、ミレーの<<ミルク缶にみずをそそぐ農夫>>でした。一見すると地味です。描かれているのも農村の一風景です。しかしこの絵は観れば見るほど、不思議な存在感を感じるのです。そこには現代アートにみられる奇抜な斬新さはみられないのですが、確かに心打つものがある。
絵画表現の面白しろさは、スタイルに関わらず真実・美を表現できれば、モデルやスタイル、流行に左右されず名画になりうるところにあるのかもしれません。わたしはちょうど、上野の森美術館で開催されているイギリス王朝の肖像画の展覧会「KING&QUEEN展」を最近見たので見比べることができるのですが、イギリス王室の肖像画に描かれる王族をモデルにした一枚と、ミレーの描く農村の農夫をモデルにした一枚は絵画としての存在感でいえば差はないように感じられました。ミレーの描く絵画には、ただ「ある」ということへの肯定を感じます。観る人がみれば宮殿の王族も農村の農夫も人間存在としては同じように価値のあるものなのかもしれません。
農夫の絵を描くことから、ミレーはきっと真面目で暗い人間であったのだろうと考えがちです。私もそうでした。しかし、実際はかれは、最初から農村を描いていたわけではなく、美しい女性たちや裸婦像や都会といった華やかな主題を描いていたそうです。それが、当時全く世間的に評価されいなかった、それゆえ誰も見向きもしなかった農村を主題に描き始めます。これは、当時の画家の世界において流行に反するようなものでした。うけがよくない。しかし流行とはすぐに流れゆくものです。彼は、流行に便乗し自分をごまかすことではなく、自分が感動したもの、いいと思っているものを描く対象にする決断をしたのです。そして、のちの世に残った名作がどちらのタイプの作品だったかというと、農村をモデルにした作品でした。
セザンヌとミレー
セザンヌはミレーと同じ主題も描いていてこの展覧会で鑑賞もできます。<<座る農夫>>という絵画です。わたしは、セザンヌが描く花や果物を主題にした絵画よりも、すこし弱い印象をうけました。もしかしたら、ミレーの<<ミルク缶にみずをそそぐ農夫>>を先に観てしまったからかもしれません。セザンヌの農夫がダメだったというより、ミレーの農夫がすごすぎたのです。
世界について人が感動するとき多くは記憶が関係し、その記憶の中でも子供時代の記憶はよくもわるくも大きなウェイトがあると私はよく思います。ミレーは農家の出身で、セザンヌは銀行家の出身です。人を主題に描くとき、とりわけ内面が十分育った大人を描くとき画家のモデルの人間性への尊敬や愛情がカギとなりそれをいかに表現できるか、が重要になっているようにわたしは思います。
一方で、彼の<<リンゴとテーブルクロス>>はやはり素晴らしかったです。
ところで、セザンヌは今日では印象派に影響を与えた芸術界の巨匠という位置づけですが、かれが画家として名声を得たのは彼の人生後半ですです。30代では展覧会で落選し続け、40台にしてようやくちらほら、評価されはじめた遅咲きです。ただでさえ、画家という仕事は孤独な厳しさがあるのに、なかなか評価さない、評価される確証もない中で、落選し続けた30代を乗り切った彼の折れない信念には驚かされます。
ゴーギャンの覚悟
興味深い経歴をもっているのは、ミレーやスザンヌだけではありません。印象派が興隆した少しあと、ゴッホや他の多く巨匠に影響を与えた巨匠ゴーギャンは、実は芸術とは正反対の分野である金融業界に身をおく証券マンでした。彼は35歳にして画家になる覚悟をきめ画家へ転身したのです。
彼は営業マンのままいれば生活は安定していたことでしょう。しかしかれは自らの信じるのものに従い画家になる挑戦をしました。そこには覚悟のようなものがあります。新しいことをすることにつきものの苦痛や、失望を受け入れる覚悟です。
ましてや30代半ばの頭の回転がはやい、言い換えれば、愛よりコスパに偏りやすい証券マンであった彼がコスパとは対岸に位置する画家になる決断したことに驚きを感じます。
ここにきてどうやら彼らが「時代を超えてつながるもの」を残せた理由として共通するものが見て取れます。それは、信念と勇気です。
信念と服従
ドイツの心理社会学者エーリッヒ・フロムは著書『愛するということ』のなかで、信念を論じています。彼によると信念には二種類ああり信念と根拠なき信念の二つに分けて考えました。
フロムは’人間には可能性があるので、適当な条件さえ与えれば、平等・正義・愛という原理に基づいた社会秩序を打ち立てることができる’という信念を人が持てなければ、人は権力に服従してしまうと論じています。この手の人が権力に対していだいているものを「根拠なき信念」としています。一見すると権力のほうが根拠がありそうにみえますが、歴史をみれば権力はいつの時代も案外不確かなものであるという事実からこのような表現になっています。肝心な点は人間への信念のなかに自分自身も含まれていることです。
彼らが画家として表現しているものは彼らが見出した世界(人間を含む)への感動であり、絵画は彼らが世界を「愛すること」をした結果生まれたものです。しかし、それができたのは自分自身の可能性をまずは彼らが信じていたからです。これは、相当に勇気がいるはずです。苦痛や失望を受け入れる覚悟です。
ミレーもセザンヌもゴーギャンも各々が人間存在の可能性への確信の信念を持っていたのであり、それをもつにたる勇気をもっていたからこそ、流行や世間体、安定やお金、権力への服従への誘惑に屈することなく名作を生む仕事ができたのです。
今回の投稿で「なぜ、巨匠は名画を残せたのか」という問いにを戻します。彼らは、人間存在の可能性を信じ、勇気をもっていたからというのが私の答えです。「時代をこえてつなぐもの」が残った秘密には画家の人間の本質への信頼と心構え、勇気があったのです。
どこかの少年漫画雑誌のスローガン、もしくはアニメのテーマのようですが、本当にいいものを創る「仕事」に従事するために、もしくはそこに至るためには、人間として必要な気質や能力も、実は、同じなのかもしれません。
ルドンのグランブーケ
最後に、ルドンの<<グランブーケ>> を紹介して締めくくりたいと思います。この絵をを見たとき、人間はこんな美を生み出せるのかと改めて驚きました。彼も画家としての評価は40代後半あたりからでセザンヌ同様遅咲きです。その間、信念を捨てる誘惑、自分への信頼をすて権力に服従し生活するという誘惑がどれほどあったことでしょうか。
しかし彼は、信念を勇気で支え仕事をしてきたわけです。この絵をみながら彼の乗り越えてきた苦痛、失望、を思うと、この絵の美しさの奥行が増す気がするのは私だけでしょうか。(これは展覧会出口にあったコピーです。実物はもっと美しいので興味があるかたは是非ご自身の目で味わうことをお勧めします)
以上、「時代を超えてつながるもの」になりえたその秘密についての拙い考察でした。お付き合いありがとうございました。

「1894version ルドン・ルートレック展][開催期間]2020/10/24(土)~2021/1/17(日)[日時]開館時間10:00〜18:00主催 : 三菱一号館美術館、日本経済新聞社後援 : 在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本協賛 : 大日本印刷 企画協

Updated on 1月 9, 2021
琳派と印象派
東西と都市文化が生んだ美術
@ARTIZON MUSEUM
こんにちは、matsumoto takuya です。今回はアーディゾン美術館で開催されている「琳派とし印象派 東西と都市文化が生んだ美術」展をとりあげます。
琳派とは江戸時代に琳派とし印象派絵画を創作していた人たちが個人的な尊敬によって引き継がれていった装飾的な美術が特徴とされてる人たちのことです。一方で印象はヨーロッパ(18世紀前後)における古典的な絵画表現からより個人の感動をメインに絵画創作を行っていた人たちのことで、こちらは装飾的な要素より、個人の感情や感動に主軸が置かれている点で琳派の装飾的な特養とは対照的です。どちらのグループも活動していた当事者は「琳派」とも「印象派」とも自称していたわけではなく、のちに学者によって名付けられたようです。
近い時間軸と都市という環境の中で、東西という地理的視点を持ちながら比較でき、東西の名画をより深く鑑賞できるとっても贅沢な展覧会となっていました。
「展覧会名琳派と印象派 東⻄都市文化が生んだ美術」展公式サイト
今回は、東の果て、江戸時代に活躍した「琳派」という、謎めいた集団を少しだけ探っていきます。
以下内容を少し含みます。
不思議なグループ「琳派」
興味深い点は、彼らが琳派と呼ばれるにいたった経緯です。江戸時代後期の絵師、酒井抱一が尾形光琳の絵画にほれ込み私淑し、親炙すること「琳派」の系譜は歴史に姿を現すのですが、琳派の始まりはこうやって共感と尊敬によって自発性によって繋がっていたことに少し驚きました。酒井抱一がほれ込んだ尾形光琳は俵屋宗達の作品にほれ込み、俵屋宗達は本阿弥光悦の作品にほれ込みといった具合に、共感と自らが価値ありと認めたものを支持する活動の結果として「琳派」とのちに呼ばれるわけです。
江戸時代といえば、自発的な関係より士農工商にはじまる身分制が徹底された受動的な関係の時代です。新しい価値を創出する活動は体制を揺るがしかねない目で見られる環境下にあった。そういう環境だと芸術表現も創作というより与えられた型の反復といった「お勉強」の産物で死んだものになりやすいものです。そんな時代背景のなか自発的に関係を築いていった日本人がいたというのは少し嬉しくもあります。
同時に、琳派と呼ばれる人たちの作品がなぜ今を生きるわたしたちに国を超えて支持されいるのか納得できました。心とは自発性によって現れるものです。自発性なくして心とはよべない。彼らの作品には自の心が動機となり、それが作品に込められているから時代も国もこえて観る人に何かしらを感じさせるのだろうとわたしは思います
例えば、尾形光琳<<孔雀立葵図屏風>>からは尾形光琳がの孔雀への眼差し、が見事に表現されていました。描く対象になんの感動も愛も抱いていなかったら、このような高貴さ、品、生き物の持もつ秘められたエネルギーなどは表現できませんし、心でとらえた主題が生きるような絶妙な余白や色彩の構図を決定できなかったと思うからです。
ここには愛があります。内実といってもいいし、誠実さとも呼べるかもしれません。酒井抱一は周りに評価されているから尾形光琳の絵をいいと思ったのでなく、自分が喜んだから尾形光琳の絵は良いのだという精神的な価値に基いていて、その自らが良いと思った絵のエッセンスを引き継ぎ発展させていった
個人の共感によって結び付けられ引き継がれたものが「琳派」と呼ばれるに至ったわけです。
琳派とロック
私はロックが好きで、とりわけUKロックと呼ばれるジャンルが好きです。UKとはイギリスのことで、ビートルズが有名ですね。このロックは、誰からの強制もなく、自発的に引き継がれています。好きな曲を好きだから知りたいと思い、最初はまねることから創作していく。そしてその人が作った曲に、誰かが感動しまた、、、といった具合に引き継がれていく。個であるのに、確かな絆がある。茶番ではないそういう関係で引き継がれたものをわたしは本物の文化だと思います。
そこにはロボットのような表面的な人間関係でなく人間ならではのつながりを感じます。個人の精神など御法度の江戸時代という時代背景のなか琳派のひとたちはまさに「ロック」な存在だったといえます。
絵画の働き
絵画の場合、描き手の「眼差し」が表現に反映されます。それは心に起因し、唯一無二です。完全に誰かの眼差しと一致することはないので孤独なのですが、画家にその絵を描かせようとした動機は世界の何らかのものへの感動であり共感です。鑑賞者がその名画をいいと思うのはその絵に程度はあれど感動しているからです。作家の心と鑑賞者の心の共感です。
琳派のエピソードは、本物の絵画とは何なのかということを教えてくれます。絵画は自己完結的なものではなく実は人と世界(その中にひとがいます)との繋がりなのだということが分かります。わたしはこのことは絵画のみならず芸術全般にいえることだと思います。
現代はロボットのような利害関係や表面的なつながりが多くなっていて、そもそも自分自身さえ物(商品)のように扱いがちです。外から見て価値のあるように人格をパッケージ化し感情を標準化し、相手もそのように選びがちです。それがビジネスのみならず私的な領域に蔓延している。婚活市場が煽ってくる広告をみていると特にそれを感じます。そこには「心」がありません。まるで人からどう見られたいかという、幼いナルシシズム、さもしいビジネスライクがデフォルトのようです。
今の日本では特に下火の芸術は、実はそんな私たちへの処方箋といえるかもしれません。
今回はこの辺で、お付き合いありがとうございました。
「展覧会名琳派と印象派 東⻄都市文化が生んだ美術」展
[会期]2020年11月14日[土] – 2021年1月24日[日]*本展では展示替えがあります。展示期間をご確認のうえ、ご来館ください。
[開館時間]10:00 – 18:00 (毎週金曜日の20:00までの夜間開館は、当面の間休止を予定しています。最新情報は本サイトをご確認ください)*入館は閉館の30分前まで
[休館]日月曜日(11月23日、1月11日は開館)、11月24日、年末年始(12月28日 – 1月4日)、1月12日

