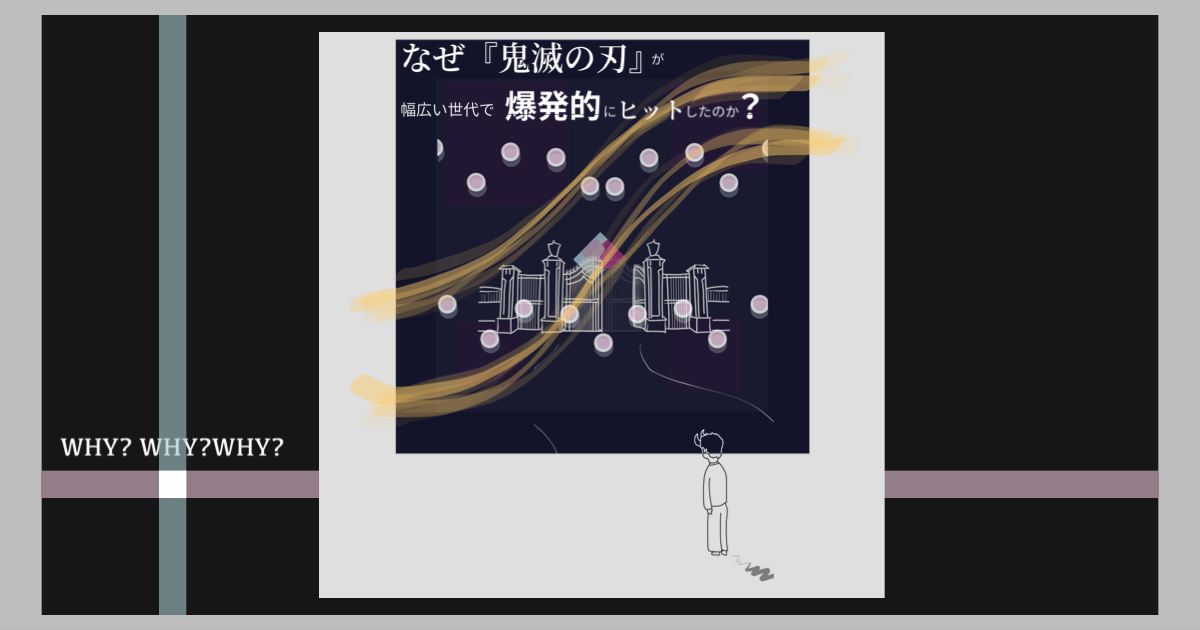こんにちは、matsumoto takuya です。今回も前回にひきつづきシリーズ「『鬼滅の刃』が少し引くほど大ヒットした理由とは?」をおおくりします。
前回の投稿までは、歴史・時間という縦の軸と西洋・日本といった地理的な横の軸、そして、それらを社会の下部構造と人々の社会心理の観点から、「『鬼滅の刃』が少し引くほど大ヒットした理由とは?」という理由の答えをマクロの視点でみていきました。
以降の投稿では、『鬼滅の刃』の内容にふみこんで、竈戸炭次郎をはじめとした主要な登場人物と無惨ら鬼たちがそれぞれに築く人間関係にスポットをあてながら、個別具体的なミクロの視点で『鬼滅の刃』が少し引くほど大ヒットした理由を探っていきます。
今回は、普通の漫画やアニメの敵キャラクターのように他人事とはおもえない鬼の秘密をさぐりながら、『鬼滅の刃』が世代をこえて異常なほど大ヒットした秘密に迫っていきたいと思います。
ではそっそくいってみましょう。
目次
『鬼滅』炭次郎と無惨からみる愛と欲望
他人を尊重できるような「大人」は、わたしたちの身近に実際どれくらいいるのでしょうか。
最近は、ひと昔前に比べて露骨な上下関係の押し付けは減ってきたかもしれません。しかし実情は、上の世代はホントのところは納得していないが、外圧が強まったから、我慢するようにしている、というのがリアルなところではないでしょうか。上の立場の人間は表面上はなめらかなようで、実は不満をためこめんでいるような気がします。もしかしたら、他人を尊重するということ、は子供のころ教わったほどには簡単なことではないのかもしれません。
『鬼滅の刃』では、この「大人」ではない状態の人がわんさかでてきます。「鬼」のかたがたと、「鬼」の親玉、鬼舞辻無惨です。この、鬼仏辻無惨の築いていく人間関係(「鬼」ですが)と、主人公の竈戸炭次郎の築いていく人間関係は、とても対照的に描かれています。
わたしは、竈戸炭次郎の築く人間関係よりも、鬼の親玉である鬼舞辻無惨側が築く「鬼」同士の関係のほうが、わたしたちの社会のリアルな人間関係に近いのではないかと考えてしまいます。その理由を述べる前に、炭次郎の築く人間関係と「鬼」の親玉である無惨が築く鬼同士の関係を、少し詳しく見ていきたいと思います。
炭次郎は、自分独自の感覚・感情に耳をすまして、そこから感じたものをもとにして自ら考え、それを信念として活動しています。そして、自分への態度と同じようの、他人の独自性と独立性を尊重し配慮をします。しかし同時に、組織内では基本的に従順ですが、必要とあれば、たとえ立場が弱い場合であっても、はっきり意見を表明します。相手側は、まさにいいも悪いもふくめ多様な反応を示すなかで、すこしずつお互いのペースで関係を深めていきます。
それに対して、鬼舞辻無惨は、個別の「鬼」について独自性(感覚や考え)や独立性(ペース)にまったく配慮するそぶりをみせず、部下の意見をたかが知れたものと決めつけ、逐一相手の「間違い」を指摘し自分のやり方に「鬼」が従うように強制します。その反面、彼が「鬼」にとてもやさしくなる場合があります、それは「鬼」が支配でき自分に役立つ場合です。相手側の「鬼」は無惨の力に圧倒され、無惨に自分の意見や自由の一切を譲りに、かれの望みを自分の望みとし献身しようとします。
わたしたちははたして、どちら側に近いでしょうか。
こう書きだしてみると、ふと、疑問がわきます。はて、一部の「鬼」の鬼舞辻無惨への献身は愛なのではないか、という疑問です。わたしたちの身近な感覚では、この、他人のために自分をすてて尽くすことは絶対的な「愛情」行為だと賞賛されている風潮があるようにさえ感じれるらからです。
他方で、DV(家庭内虐待)を受けている女性(男性も含める)は、しばしばこの「愛情」を暴力をふるうパートナーに示しますし、虐待をうけている子供も、親に対してこのタイプの「愛情」を示すことはよく知られています。それでも、程度の差はあれ、わたしたちの人間関係でも、部分的に「エムっ気」という形でしばしば見かけられるものかもしれません。
このタイプの鬼と無残の関係に愛はあるのでしょうか?そもそも、愛というものが巷でいわれるようになったのは、西洋文化が流入してきたここ150年あまりのことで、捉えどころがいまいちですし、話題に出すだけで滑った空気がながれるので、日本では曖昧なまま放置されているものの一つかもしれません。エーリッヒ・フロムはマゾヒズムが示す行為についてこう述べています。
フロム・・・エーリッヒ・フロム。20世紀を代表する社会心理学者。社会のなかの個人の自由と孤独を専門とする。最近著書『愛するということ』が日本でリバイバルしている。
もし愛とは、ある特定の人物の本質に対する、情熱的な肯定であり、積極的な交渉を意味するのであれば、またもし愛とは当事者二人の独立と統一性とに基づいた人間同士の結合を意味するのであれば、マゾヒズムと愛は対立するものである。愛は平等と自由に基礎づけられる。もし一方の側の服従と統一性の喪失にもとずいているならば、いかにその関係を合理化しようと、それはマゾヒズム的な依存に他ならない。サディズムもまたしばしば愛のよそおいのもとにあらわれる。もし当人のために支配するのだと主張されるならば、支配することも愛の表現だといえよう。しかし、本質的要素は支配の享楽にほかならない。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社:179頁
支配の対岸にあるのが愛であり、それは、お互いの自由という独立性への尊重と、それを可能にする平等を用意できているかが重要なようです。「鬼」に服従を強いることで、相手に依存させ自立する力を奪う無惨と、自らを消し去り無惨への献身をささげ、寄りかかる「鬼」との関係には恋に似た何かはあっても愛ではなく依存に近いようです。同じことが、DV関係の男女や虐待・ネグレクトのある親子のあいだにも言えます。
フロムは、マゾヒズムに対応するサディズムについてこう言っています。
サディズム的人間は、彼が支配していると感じている人間だけをきわめてはっきりと「愛し」ている。妻でも、子でも、助手でも、給仕でも、道行く乞食にも、かれの支配の対象にたいして、彼は愛の感情を、いや感謝の感情さえもっている。彼の生活を支配するのは、彼らを愛しているからだと、かれは考えているかもわからない。事実かれらはかれらを支配していいるから愛しているのだ。彼は、物質的なもので、賞賛で、愛を保証することで、ウィットや才気で、関心を示すことによって、他人を買収している。かれはあらゆるものを与えるかもわからない――――ただ一つのことをのぞいて、すなわち自由独立の権利をのぞいて。・・・かれにとって、愛とは、自由を求めながら、とらえられとじこめられることを意味する。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社:164項
このサディズムとマゾヒズムの傾向は、孤独にたえられないこと、もしくは自分がないことからくる不安・無力感からきており、いずれも、どちらかのもしくは両方の個性と自由が失われていることを特徴としています。
もちろん、人間が完璧でない以上、サディズム・マゾヒズムが関係に入ってこない人はまずいないでしょう。しかし、そちらに偏ってしまうことは、愛とは対岸に位置するものであることは、無惨が築く「鬼」との関係を見ているとよくわかります。
テレビ等で、欧米圏で成功を収めた人へのインタービューを見ていると、「子弟関係であり友人」と紹介されてと恩師に当たる人物が紹介されているのをみかけますが、日本の師弟関係ではめったにそういう表現はみられません。上下関係や暗黙のルールが私的な領域にくいこむので、友人関係の余地をうむ個人間の平等が残らないからかもしれません。
フランス共和国のスローガンが、「自由、平等、友愛」であることは有名です。ここに「自由」があるのは興味深いことです。愛は支配からは生じえないことを再確認するかのように、一番先頭に自由がおかれ、次に自由の側面である平等がつづき、最後にようやく愛がおかれています。これは、偶然の思い付きではなく、長い人間の歴史で繰り返されてきた痛ましい過ちや経験則、キリスト教文化圏の長い歴史のなかで積み重ねられ、導き出された順番であり、歴史の論証に裏打ちされた標語だったわけです。
ちなみに、自由という概念は、150年ほど前の日本にはありませんでした。約150年前の日本には、わたしたちの使っている「自由」という言葉すらなかったのです。福沢諭吉が英単語「freedom」を日本語に訳す時に、「自らが由(よし)とする」という意味から自由という語を造語したそうです。当時の日本人は、自由などという抽象的な内容の言葉を急にあたえられ、実際にそうやって生きている人さえ見たことがない状態で自由と出会いました。その分、混乱と期待、恐さとわくわくが同居する気持ちが人々の胸の内にあったはずです。
『鬼滅の刃』の舞台である大正時代はまさに、自由・平等・愛についての萌芽が、市中にいる個人のなかに芽生えはじめた始まりの時代だったのです。
自分をわすれることで安定をてにいれた元人間
ここで『鬼滅の刃』にでてくる「鬼」についてスポットをあてていきたいと思います。それも雑魚ではなく、力のある「鬼」にスポットを当てていきます。
「鬼」は元々は人間で、個人的な苦悩を持っていました。その苦悩に無惨がつけこみます。無惨は悩んでいる人間に、自分へ服従するかわりに力を与えます。「鬼」となったものは無惨の血を自身に取り込み、力を与えられることで苦悩から解放されます。無惨の血ををりこむたびに、もしくは、人間を食べれば食べるほど「鬼」として強くなっていきますが、それに反比例するかたちで、人間であったころの「私」を忘れていきます。「鬼」は、人間らしい苦悩から解放されたうえに、不死身の肉体を手にしたにもかかわらず、無惨に見捨てられたくないこと、または、いつも自らの力に不足を感じる、といった不安にかられ、力を際限なく求めるようになります。
「鬼」は、力を手にする代わりに人間だった頃の本当の自分を喪失していきますが、抑圧された内面世界では、本当は人を喰らうのではなくて、内実のある人間関係を求めていた、あるいは、人に個性をもった「私」として認めてもらいたかった、という苦悩が後に露わになります。「鬼」となった後も、人間の苦悩は消え去ったのではなく、おおいのようなものによって見えなくしていただけだったのです。「鬼」の精神面では、本来の欲求(人間性)がにせの欲求(無惨の精神性)に置き換えられていたのです。
ここで、先ほど引用したフロムの近代人についての記述をもう一度ひいてみます。
かれは、もし自分が欲し、考え、感ずることを知ることができたならば、自分の意思に従って自由に行動したであろう。しかし、彼はそれ知らないのである。かれは匿名の権威に協調し、自分のものではない自己をとりいれる。このようなことをすればするほど、彼は無力を感じ、ますます同調をしいられる。楽観主義と創意のみせかけにもかかわらず、近代人は深い無力感に打ちひしがれている。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社
この記述にある、「匿名の権威」を「無惨」に、「近代人」を「鬼」に入れ替えると、そのまま「鬼」の記述となることに気がつくはずです。
「鬼」は、力を求めて無惨の価値観である人食や、彼の血にすがればすがるほど、無惨の価値観を自分のものだと思いこむようになり、人間だったころの自分、つまり「私」を忘れていきます。わたしたちはどうでしょうか。孤独の不安から逃れられる代わりに、「匿名の権威(「世間や小集団」)」へ同調を繰り返す結果、「自分のものではないにせの自己(匿名の権威)」が自分だと思いこむようになり、自らの個性、つまり「私」を忘れていきます。
近現代人が典型的に陥りやすい精神状態は、本来の欲求(個人)がにせの欲求(世間・小集団からの評価)に自覚なく置き換えられていくことであり、これはまさに鬼と同じ精神状態にあると言えてしまうのです。
フロムは現代人の胸に抱えた不自然さを、こう鋭く考察しています。
思考や感情や意思について、本来の行為がにせの行為に代置されることは、遂には本来の自己がにせの自己に代置されるところまで進んでいく。本来の自己とは、精神的な活動の創造者である自己である。にせの自己は、実際に他人から期待されている役割を代表し、自己の名のものとにそれをおこなう代理にすぎない。たしかに、ある人間は多くの役割を果たし、主観的には、各々の役割においてかれは「かれ」であると確信することができるであろう。しかしじっさいは、彼らは全ての役割において他人から期待されていると思っているところのものであり、多くの人々は、たとえ大部分のものではないにしても、本来の自己はにせの自己によって、完全におさえられている。
同上:224項
自分では自分で決めた選択の動機が、実は「他人ウケ」のためであること。それが現代人の陥りやすい典型的な特徴ですが、「それは本来の自己がにせの自己に代置され」たものであったわけです。処世術として取り込んだはずの他者の視点が、いつしか、自分の感覚、感情や想い、そして考える力を縮委させてしまい、主人のようにふるまっているということです。
フロムはこう続けます。
自己の喪失とにせの自己の代置は、個人を烈しい不安の状況になげこむ。かれは、本質的には、他人の期待の反映であり、ある程度自己の同一性を失っているので、かれには懐疑がつきまとう。このような同一性の喪失から生まれてくる恐怖を克服するために、かれは順応することを強いられ、他人によって耐えず認められ、承認されることによって、自己の同一性を求めようとする。かれはかれがなにものであるかは知らないが、もし彼が他人の期待通りに行動すれば、少なくとも他人はそれを知ることになるであろう。そしてもし他人が知っているならば、かれらの言葉を借りるならば、かれも知っていることになるであろう。
近代社会において、個人が自動機械になったことは、一般のひとびとの無力感と不安とを増大した。そのために、かれは安定をあたえ、疑いから救ってくれるような新しい権威に、たやすく従属しようとしている。
同上:225項
孤独の不安から逃れようと「私」を放置しなんらかの集団に同調・同化をしていくと、「私」として社会なかで活躍することで実感できる自身の能力の手ごたえを感じられず、無力感と不安を増大させ、それがまた「私」を・・・といった具合に、人は無限ループに閉じこめられます。
この意味で、強力な同調圧力を抱える日本で育った人が、看板にたよらない本当の意味での自信を育みにくいのはしかたないことかもしれません。
SNSで「いいね!」が以上に気になってしまうからくりはここにあります。最近の小中学生が、LINEなどのSNS上で「いいね」を半強制的にに友達からもらえるような遊びに躍起になっている、というニュースをネットでよく見かけますが、わたしは無理もないことだと思っていました。決して少なくない数の子供の身近にいる大人が、子供以上に、そうだからです。大人と子供の違う点は、それを偽装する術を知っているか知らないかの差でしかない。
最近の子どもは、承認欲求が尋常ではない、とよく言われているようですが、そもそも、自分がない人がなぜ「世間」に従うのかといえば、他人からの評価が得られるからです。つまり承認欲求の代理満足がみたされるからです。最近は、「世間」の弊害のほうが目立つようになり、子どもの外的環境は以前にもまして精神的な独立をするように個性を成長させることに肯定的な環境にあります。本当は、他者に個性をもった「私」を認めて欲しいところを、それが日本の環境ではどうも得られず、その代理満足として、SNSを使った表面的な承認で満たしていると考えれば、日本の状況の本質は、変わっていないのではないでhそうか。親の世代とちがうことは、「私」を放置してなんらかの多数派に服従するのはやめましょうというアンチ「世間」の教育を、割とはっきりとうけていることです。
人は「私」を見失えば、自分が何をしたいのかわからなくなり、世界に対して自分らしい関心が動かなくなります。いいかえれば、同調元の価値観にそって人生を「選んで」いくことになります。意思なき人生です。フロムはこの強制的画一化された人間を「自動人形」となずけています。
この「自動人形」化が進んだ結果、行きついた先がナチズムや全体主義です。、わたしたちが「厨二」と馬鹿にしている思春期時代の黒歴史が青空のように感じられるほどの黒歴史を、西洋の先進国の社会適応しているおとなが自覚のないままに自作自演してしまったのです。
『鬼滅の刃』の「鬼」は人間だった頃の自分を忘れていき、代理満足をあたえてくれる無惨の価値観に服従し、人間を欲の対象にしかみれず、傷つけ、むさぼります。「自動人形」となった人間は、自分をわすれていき、代理満足をあたえてくれる同調先の「匿名の権威」に服従し同化していき、そうしない「私」としていきている人の存在が無性に苛立たしいと感じられ、間接的に責任を取らないやりかたで傷つけてしまいます。
「鬼」を「自分をわすれることで安定をてにいれた元人間」と定義すると、それは、フロムが明晰に描写して見せた近代人にも同じ定義があてはまります。そして、その定義はわたしたちの姿とも重なるのです。鬼は、「自由からの逃走」をしているわたしたち現代日本人のメタファーと言えてしまうのです。
埋もれた心がもとめるもの
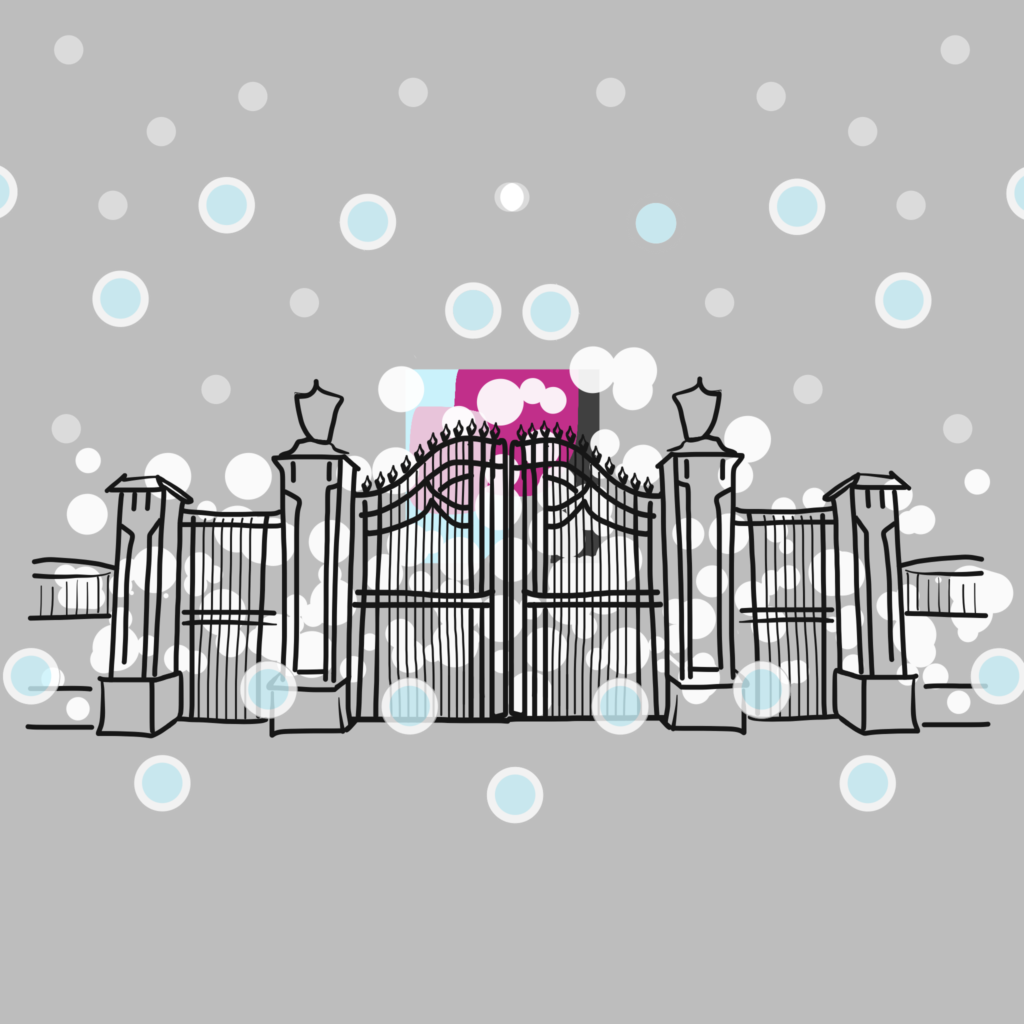
「鬼」は元は人間で心を持った存在として描かれています。わたしは当初「やたらグロテスクな敵キャラだなー」くらいの軽いノリでみていました。しかし、鬼の過去(人間だった時の記憶)か明らかになるにつれて、予期せず揺さぶられるものを感じ、ぐっと物語に惹きつけられたのです。
人を喰らうということは、「人間を自分の欲を満たすための対象にする」ということです。強い「鬼」の欲求はより強く、貪欲になっていきます。しかし、物語をみていくと、それらの欲求の強さは、人間時代の苦悩の大きさに比例し、消費欲や力への欲求は、本当の欲求の代理満足であったことが明るみにでます。
「鬼」の本当の欲求とは何でしょうか。それは、「私(心)」に人が気がついてくれること、気がついて配慮しあう人間関係、他者に心という個性をもった存在として認めてもらうこと、といった「私」として他者と関係を築くなかで得られるタイプの感情経験への欲求です。
「鬼」は、本当は「私」として生きたかった、「私」を放置しないで、同じように「私」を放置していない人との間にあるもの、「内的な繋がり」を感じたかったのです。
かれらは、人間時代に何らかの事情により、自分であることに無力感や不安、寂しさを抱え、鬼舞辻無惨の接近を許してしまいます。それが、「鬼」の不幸の始まりなのですが、これは、2017年におきた座間9人殺害事件の経緯とそっくりであることに気がつかされます。
この事件は衝撃的な事件であったので、大々的に報道されましたが、この事件以外にも、ニュースに出ないだけでSNSを使用した悲しい事件はますます増えています。
被害者はなんらかの事情ににより、自分であることに無力感と不信感、不安、寂しさを抱え、たえられずSNSを利用し、「無惨」よりな人間の接近を許してしまう点で共通しています。そこが悲劇のはじまりです。「無惨」のような人間はもちろん批判されてしかるべき存在ですが、「無惨」よりの人間にとりこまれる余地を作ってしまったその人の周囲の環境のほうが、病んでいるのではないか、病巣があるではないかと考ることもできるのです。
ひとは完璧ではありませんし、生きていく中で、無力感や不安、寂しさをかかえることは誰にでも起こりえます。そういう時期、その人が自分の弱さを見せられるのは、その人の築いた人間関係の中で最も信頼できる人間だけです。そういった人が「無惨」のような人になぜ自ら近づいていかざるおえなかったのか。いいかえれば、なぜそのひとが最もデリケートな悩みを相談できる人間がそのひとの周りにいなかったのか、そのような状況にある人が日本では少なくないというのが問題なのです。周りには、何らかの人が、少なくても、教師や公的機関の人がいたはずなのにです。
デリケートな悩みほど、それを話すには信頼関係を要します。いくら外から「助ける」といわれても、信頼関係を築けてもいないのに、「公的な組織の人間だから信じて悩みを話してよ」というのは、すでに信じて痛い目をみてきている人にとっては、かなり乱暴な話です。相談者にとっては、SNSで出会った人も、支援団体の職員も同じ赤の他人から関係は始まります。この手の信用は、銀行ローンの信用ではないからです。
公的機関で働く人に相談するくらいなら、知らない人にSNSを使って相談したほうがましである、という事実はどういうことを伝えているのか。
もちろん、悩んでいる人を支える支援団体や公的支援は必要です。そのうえで、本当の意味で人を救えるのは、支援団体や役割のまえに、ひとりの人間としていきている人間だけではないかとわたしはつくづく思います。弱者を救うという上から目線の人間ではなく、「正しい」価値判断をいっぽう的に押しつけてくる人間ではなく、耳をかたむけることのできる人間、「私」でいてやっぱりいいんだな、とその態度から感じさせてくれる、実際に公的な役職という属性の前に、「私」として生きている人間です。
世界各地の紛争地を取材しているフリージャーナリスト・学者のカロリン・エムケは、信頼の問題にたいしてこう述べています。
この議論においては、暴力の被害者のほうが、聞き手の信頼に値することを証明せねばならないのではなく、被害の免れた者のほうが、被害者の信頼を勝ち得るために努力をせねばならない。本書冒頭に示した「あなたがこれを言葉にしてくれ?」という問い。または、世界中のあらゆる場所で何度もくり返し口にされる「あなたがこれを書いてくれる?」という問いには、常に希望と同じだけの疑念が含まれている。聞き手が、社会が、話をする相手として信頼に値するだろうかという疑念だ。
カロリン・エムケ 浅井晶子訳 『なぜならそれは言葉にできるから』 みすす書房
エムケは、虐待によって人間全般への信頼と失った人と信頼関係を築く大事なこととして、何らかの傷が生んだ「経験によって作られた人間としての彼ら」のほうも受け容れる覚悟をあげています。つまり、硬直し、時に嘘をつき、沈黙している目の前に実際いるありのままの彼らも、聞き手が受け入れる準備や覚悟をしているかどうか、が聞き手が問われているということです。
『鬼滅の刃』では、虐待とネグレクト(意思の無視)の過去をもつ、カナヲというトラウマをかかえた少女がでてきます。彼女は幸運にも、「無惨」よりの人間ではない胡蝶姉妹に引き取られますが、彼女はそれから十数年たち、処世術をみにつけたものの、明らかにトラウマの後遺症を感じさせるふるまいをとります。幸運にも人情ある人に出会え、十数年かけて関係を築いてようやくここまでこれたのだ、ともいえます。社会的な役割だけでも、生半可な付き合いでも解決ができないこの手の問題のリアルを感じさせられます。
わたしが「鬼」の過去(人間だった時の記憶)が明らかになるにつれて、予期せず揺さぶられるものを感じ、ぐっと物語に惹きつけられたのは、「鬼」となり、破壊性という残念なかたちでの表現となってしまったものの、あれだけの力を秘めていたならば、近くにいた人間が、無惨もしくは「無惨」よりの人間でなかったら、苦悩をのりこえたさきには活躍の可能性があったのではないか、と思うからです。そんな本来力をひえた有望な人間が、下らない代理満足をあてがわれ、あくせく尻をたたかれたうえに、死に際に自分の人生の空っぽさに気がつき、「自分の人生は一体何だったのか」という後悔をする「鬼」に、わたしは同情というか、いたたまれないタイプの親近感を覚えます。
「日本一優しい鬼退治」というキャッチフレーズが『鬼滅の刃』にはつけられているそうですが、人間性を失った鬼とは対照的に、主人公の炭次郎たちが、自分も含め他者の独自性・独立性にしっかり気が付き、その孤独を認めようとする姿勢が垣間見られるところにあるのではないかと思ったりします。「イイヒト」でもできる社交的・表面的なやさしさより、一段深みのある優しさです。
「鬼」と「鬼」が築く利害関係による表面的な関係でもなく、迎合して明るい部分だけしか見せれなくなってしまった表面的な関係でもなく、すぐさま「正しい」答えをおしつけてくる助ける側、助けられる側の上下の関係でもなく、「私」を放置していないひとりの人間とひとりの人間のあいだに生まれる「内的な繋がり」が感じられる人間としての信頼関係、それが、現代にいきるわたしたちの埋もれたこころが求めているものなのではないでしょうか。『鬼滅の刃』はそこに寄り添ってくれていたわけです。
・・・・・・
・・・・
・・
『鬼滅の刃』では、この「内的な繋がりが感じられる関係」を築ける代表格が主人公、竈戸炭次郎です。次回は、かれの魅力の秘密に近づいていきながら「なぜ『鬼滅の刃』は世代をこえて異常なほど大ヒットしたのか?」という謎を別の側面から迫っていきたいと思います。
お付き合いありがとうございました。
参考文献
[放送局] TOKYO MXほか
「劇場版 鬼滅の刃 無限列車編」
[原作] 吾峠呼世晴
[監督] 外崎春雄
[脚本] ufotable
[キャラクターデザイン] 松島晃
[音楽] 梶浦由記、椎名豪
[制作] ufotable
[製作] アニプレックス,集英社、ufotable
[配給] 東宝,アニプレックス
[封切日] 2020年10月16日
[上映時間 ]117分
その他 PG12指定