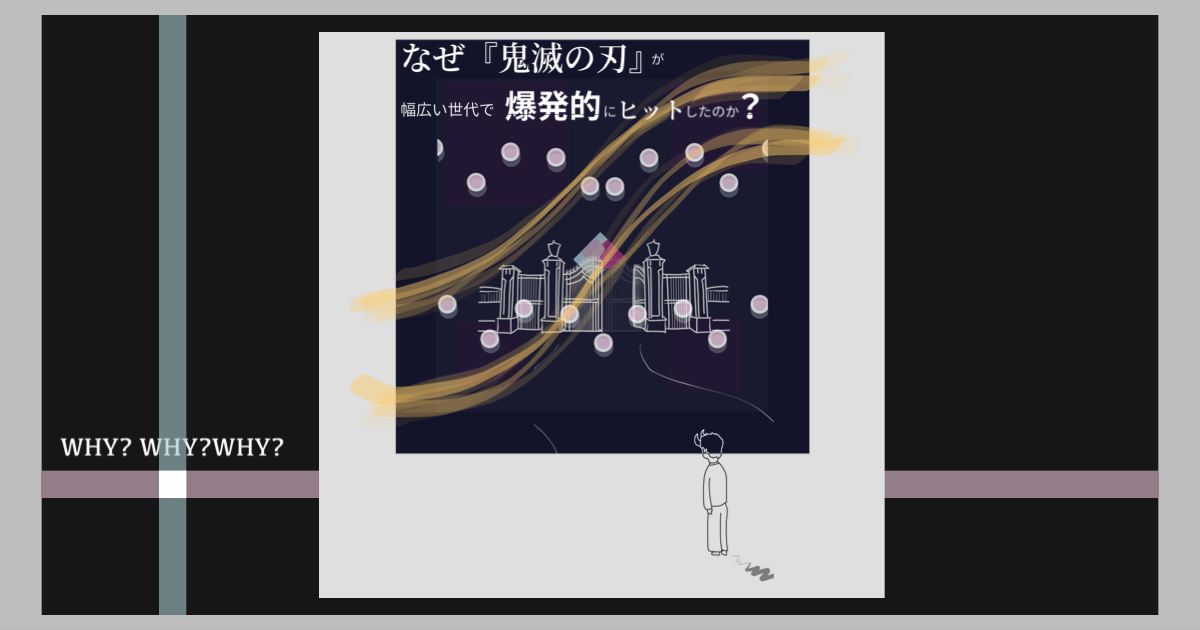こんにちは、matsumoto takuya です。今回も前回にひきつづきシリーズ「なぜ『鬼滅の刃』が幅広い世代で爆発的にヒットしたのか?」をおおくりします。
前回の投稿で、「力」には「能力」と「支配力」という2種類の意味があり、炭次郎には「能力」が無惨には「支配力」があり、ひとは「能力」をえられない場合に、「支配力」に駆られる傾向があるのだというところに行きつきました。わたしたちは炭次郎がもっている力に惹かれ、無惨のほうの力にはお腹いっぱいでうんざりしている。
今回は、『鬼滅の刃』のカナヲや「鬼」をみながら、鬼とおなじように「支配・服従関係」から逃れられない現代人の姿に迫っていき、『鬼滅の刃』という少年漫画原作の物語が、社会人層である20代、30代そして40代にどうしてハマったのかという理由を探っていきたいと思います。
ではそっそくいってみましょう。
目次
『鬼滅』カナヲからみる無力感の原因
ここで先にとりあげた鬼殺隊のカナヲについて、少し踏み込んでみていきたいと思います。
彼女は、幼少の頃からネグレクトと虐待を受けたあげく、親に売られた孤児でした。親にとって彼女は価値のない、生活を傾かせるだけの役にたたない重荷であり、売ることで初めて役にたつ「モノ」であったのです。
スウェーデンの精神学者で世界的にベストセラーとなった『スマホ能』の著者であるアンデシュ・ハンセンは他人を模倣する仕組みついてこう述べています。
ミラーニューロンは他人を模倣することで学習する脳の神経細胞だ。新生児に舌をだしてみせると真似するのは、このミラーニューロンのおかげだと考えられている。ミラーニューロンは動作を習得するときにだけに活躍するのではなく、脳の複数の領域に存在する。そのひとつが体性感覚野で、「他人がどう感じているか」を理解する領域だ。
―――この領域を刺激するのは痛みだけではない。他人の喜びや悲しみ。恐怖もだ。つまり、自分の身体と心の間、そして自分と他者との間にも橋を架けるようなものだ。他人を理解したいという生来の衝動は、心の理論(theory of mind)とよばれる。
アンデシュ・ハンセン『スマホ脳』:久山葉子:発行所 新潮社
まだ客観能力が未発達で、何も知らない全ての子供と同じように、子どもだった彼女は、親が彼女の感情表現や意思表現した時の態度を模倣し学んでいきます。身近な人が、自分の意思表示を悪いものである、という反応をかえせば、良くないものであるという判断をせざるおえなくります。近くの大人が感情表現に反応してくれなかったり、意思表示にたいして喜んでいない反応をしたりしても、そこから子どもは学んでいきます。
このときに、彼女がそのような大人と共にいきていくことを可能にしてくれたと同時に、後の彼女を縛り上げていくものが、近くの大人から学んだ「どうでもいい」という「私」への軽視と不信の態度です。この態度は、無力感をひとのこころに植えつけ、その語の人生に影響をあたえてきます。自己否定的な態度が親や周囲の大人から影響されたことでみにつけてしまった後天的なものであるとはつゆ知らず、それが自分の生来の性格なのだと錯覚するようになるからです。
虐待やネグレクト(意思の無視も含む)が残酷なのは、ひたすらその子供の肉体的であれ、精神的であれ、その人の意思を無視し続けることで、自分が自分自身の感じたこと、思ったことへの態度を歪めてしまうからです。それが、その後の人生を生きる大きすぎる足かせとなってしまう。カナヲは極端なケースですが、自己肯定感の低さはその人だけの責任ではなく、その親だけや、その親のいる社会の門題でもあり、ひいては、わたしたち一人一人の問題なのです。
毒親と子供の関係も、パワハラ・モラハラをする上司と部下の関係も、DVの関係も、基本的には、意思への無配慮を内容にもち、個人に無力感を植え付けます。文化が、意思表示することをけむたがり、相互理解を試みる経験の場がえられず、内向きな閉じた社会の場合、他者の意思を配慮する能力の発達を妨げてしまうことなります。
かれらが大人となったとき、子どもや、弱い立場の人に影響をあたえてしまうことになるのです。
虚しいアクセサリー的人間関係
人に無力感を植えつけるものは、カナヲのケースのように他人を役に立つかで値踏みする態度でもあるのですが、これは、無惨や「鬼」が他の「鬼」を見る態度と同じです。
そういう場合、だれかと一緒にいる理由がその人らしさではなくなります。「世間体が得られるから」、「友達がいる状態をもつことで安心したいから」「役に立つ」から「ウケがいい」からといった不安解消や見栄、アクセサリー的な動機で対人関係を結ぶことになる。そのひとが興味があるのは、その人自身ではなく、その人から得られる世間体、不安解消といった副次的な利益のみとなってしまいます。そこにはそもそも、その人自身を理解したい、配慮したいという、「こころ」がないのです。
これはあくまで私的な領域のはなしで、商売は利害関係がベースであるビジネス関係のはなしではありません。しかし、『鬼滅の刃』の「鬼」たちの関係をみていると、私的な領域までそうなってしまった場合は、やっぱり虚ろで寒々しいものなのだと改めて実感させられます。
「鬼」は人を「鬼」に変える
その人らしさである意思を重要なものとみて配慮できるか、その人らしさである意思を役に立たないうっとうしいものとして無視するのか、それが炭次郎と無惨のちがいです。人間の人間たる部分へ喜べる能力が育っているか、喜べる能力が育っていないのかという視点からみれば、ここでも炭次郎は「力」があり、無惨は「無力」といえます。
「無力」な人間はより弱い立場の人間を自分と同じように「無力」な存在に捻じ曲げ、既存の権力にたいして無批判に従う「人形」のような存在にかえてしまう影響力をもっています
『鬼滅の刃』の世界では、鬼舞辻無惨が人間に彼の血を直接的に混入させることで、劇的に人間を「私」をうしなった「鬼」にかえます。わたしたちの現実の社会では、「私」を失った人たちの空気感そして、権力がともなう閉じられた組織の中での彼らとのやり取りの中で、ゆっくりと自立力を削がれていき、自覚なく決断するための「私」を失っていくのです。能力の成長・発展を妨げられた人間は支配にはしり、権力は人を保身に走らせます。結果として、社会に日和見主義と閉塞感と鬱々とした空気が漂うことになります。
『鬼滅』の鬼からみる現代人の悲哀

自分を見失っていた人間が、死ぬ直前に、「私」として生きられなかったことに気がつき、そう生きようとしなかったことを後悔する、これほどの後悔はないとわたしは思います。
炭次郎は滅び去る直前の鬼に強烈な悲しみをかぎとり、彼らの死の際に同情を示します。彼が感じ取った悲しみは、「鬼」の後悔です。「鬼」がどういうことに後悔していたかというと、それは、人間を食べ足りなかったというものでもなく、もっと人間や下級の鬼を支配したかったというわけでもなく、「私」らしく生きたかったのにそれができなかった、という後悔です。
無惨から「私」らしく生きるための前提条件を奪われ、代理満足である人間への消費欲、支配欲や優越感を得ることに一生を費やしたあげく、まさに命が尽きる那刹に鬼は人間の頃の自分を思い出し、自分の人生はなんだったのかと後悔する。こんな、つらいことはないでしょう。「鬼」は、そのまま人間性を思い出さなかったほうが苦しまなかっただろうに、という思いと、最後は「鬼」ではなく人間として逝けたのがせめてもの救いだったのかもしれないという思いが、同時におとずれたのを覚えている、『鬼滅の刃』ならではの印象的なシーンでした。
炭次郎は、その人間として残り香のような感情をかぎとり、踏みつけにするものではなく、大切にしてあげたいと思ったわけです。それは悲しみではありますが、「鬼」が忘れてしまった、人間だけがもつ感情、人間としての誇りを思い出したからこそ感じることができる感情だったからです。
「鬼」は、炭次郎に自分さえも忘れていた「私」に気が付いてもらえた安堵により、大粒の涙をこぼしながら塵となります。ほんとうの人間の彼は、自分(自意識)にさえ切り離されてしまい、「鬼」となって人生をつぶしている間も、ずっと人知れずに心の奥のほうで、気が付いてくれることをひたすら待っていたのです。
鬼は炭次郎に自分さえも放置してきた「私」に気が付いてもらえ安堵し大粒の涙をこぼしながら塵となります。ほんとうの人間の彼は、自分(意識)にさえ切り離されてしまい、鬼となって不安にかられ力を強迫的に追い求めることに人生をつぶしている間も、ずっと人知れずに心の奥のほうで気が付いてくれることをひたすら待っていたのです。
この「鬼」の後悔は、多かれすくなかれ、ある程度生きた、すべての人にあるのではないかとわたしは思います。巨大な経済メカニズムに左右される会社、その会社という官僚的機構のもとで賃金労働のもと分業の分業ともいえる細分化された仕事内容、代えがきくことがありきの仕事をさせられている状況で、愛想笑いしている学校で、自分を心の底の底にはなんらかの「後悔や無力感」が多少なりとも溜まっていない人がいるとしたら、むしろ逆の意味で怖さを感じます。そして、この後悔や無力感は心の底のほうに、本人さえも気づかないほどの静けさで、澱のようにしんしんとと積もり溜まっていく。
「鬼」は死に際で、自身さえも忘れていた「私」に、炭次郎から人間としての敬意と配慮を示されたことで、「人間性」が息をふきかえします。「だれからも気づいてもらえなかった「私」に気づいてもらえた、しかも配慮してくれる、そういう人が目の前にいるのだ」ということを実際に感じ、最後は人間として浄化するように朽ちていくシーンは心に残ります。この場面は、日本の伝統芸能の能の魂鎮につうじる美しさがあります。
この「鬼」の悲哀と消滅のシーンは、現代、とりわけ日本の抑圧必死の環境の中でなんとか生き抜く社会人層をも惹きつけた秘密の一つではないでしょうか。
炭次郎の他人のなかに個を見る力、この尊重という能力がどういう力なのか、といのがこのシーンからもよくわかります。このちからは、支配力のように人の人間性を壊す働きではなく、ひとの内側に「なにか」を生み出す働きがあるのです。「私」でいて「これでいいのだ」と腹から思える時にかんじる「なにか」です。それは、人間が他者との関係のなかで経験しうる最も豊な感情です。
一番い痛ましく可哀そう存在は、本当に大事なものを犠牲にし、そのことさえも忘れて代理満足の確保に奔走するうちに、唯一無二の人生が終わってしまった、「私」をうしなった「鬼」なのです。たった一瞬のやり取りですが、このシーンには上辺の関係にはない「人間」と「人間」だけができる「対話」とよべうるものが確かにえ描かれていたとわたしは思います。生きている限り、たとえ「私」を失おうとも、死ぬ最後の最後まで、人の心は消えたわけではなく、そのひとの中で気づいてもらえるのを待っている「鬼」の姿と、自分を放置し、忘れてしまいがちな現代人の姿がわたしにはダブって映ります。
卑屈と合理化と鬼の魘夢(えんむ)
無惨タイプの人が上の立場に立つ集団では、下の立場にあるものがどういう態度をとるにいたるのか、ということがわかりやすくみてとれる場面があります。『アニメ『鬼滅の刃』第二十六話 新たなる任務』で無惨が直属の部下である下弦の「鬼」たちを招集し、出来の悪さへの釈明を求めた場面です。
無惨にたいして下弦の「鬼」がとった態度は4つです。意見をいうか、迎合するか、逃走するか、はじめからあきらめなすがままにされるか、です。このうち、意見をいう、迎合する、逃走するという選択肢を選んだ「鬼」は無惨に惨殺され、下弦の「鬼」のうち生き残ったのは、はじめからあきらめなすがままにされる、を選んだ下弦の「鬼」のトップである魘夢(えんむ)という「鬼」でした。かれは、意見をいう、迎合する、逃走する、何らかの意思を示した「鬼」たちが無惨に蹂躙される様子を傍観しながら、「おろかだなぁ」と優越感にひたりながらそうつぶやきます。
一見、魘夢(えんむ)は生き残れたこともあり、一番賢い選択をしたようにうつります。しかし、はたしてかれは「力」があるといえるのでしょうか?実際かれはそれ以外の選択肢がなかったのだという視点からみたとき、彼の意見はもっとも「無力」な人間がとりうる態度ではないのかとも考えられるのです。
オーストリアの精神科医、心理学者のヴィクトール・E・フランクルはアウシュビッツの被体験を綴った著書『夜と霧』のなかで、こう言っています。
・・・人間の命や人格の尊厳などどこ吹く風という周囲の雰囲気、人間を意思など持たない、絶滅政策の単なる対象としてみなし、個の最終目標に先立って肉体的な労働をとことん利用しつくす搾取政策を適用してくる周囲の雰囲気、こうした雰囲気のなかでは、ついにはみずからの自我までもが無価値のものに思えてくるのだ。
強制収容所の人間は、自ら抵抗して自尊心をふるいたたせないかぎり、自分はまだ主体性を持った存在なのだということを忘れてしまう。内面の自由と独自の価値観を備えた精神的な存在であるという自覚などは論外だ。人は自分を群衆のごく一部としか受けとめず、「わたし」という存在は群れのレベルにまで落ちこむ。きちんと考えることも、なにかを欲することもなく、人々はまるで羊の群れのようにあっちへやられ、こっちへやられ、集められたり散らされたりするのだ。
・・・
強制収容所に入れられた人間が集団の中に「消え」ようとするのは、周囲の雰囲気に影響されるからだけでなく、様々な状況で保身を計ろうとするからだ。被収容者はほどなく、意識されなくても五列横隊の真ん中に「消える」ようになるが、「群衆のなか」にまぎれこむ、つまり、けっして目立たない、どんなにささいなことでも親衛隊員の注意をひかないことは、必死の思いでなされることであって、これこそは収容所で身を守るための要諦であった。
『夜と霧』 ヴィクトール・E・フランクル 池田香代子訳 株式会社みすず書房
強制収容所の人間としての権利、つまり、個の表現をはく奪さた被収容者は、このような「はなから諦める」という「鬼」と同じ精神状態に陥るのです。
このように、「無力」な人間が何らかの地位についたとき、下の立場の人間に実質的に「はなからあきらめなすがままにされる」という選択肢以外をとりあげることで、下の立場の人の人間的な成長を妨げ、その人の主体性を奪い、受動的な存在に変えていきます。
受動的な存在になった人間は、「私」という主体を失ったことからくる自身の存在の弱小感をどうにかするために、半分無自覚な状態で、「合理化」という後付けの理由をこしらえて精神面の安定をはかろうとすることが知られています。魘夢(えんむ)のつぶやきは、この「合理化」の典型ではないかと考えられます。かれは、表面のメッキをはがせば、ただ臆病で無力な存在でしかないのです。
悲哀のチャネル
今の日本社会の組織・会社ではたらく場合はどうでしょうか。ヴィクトール・E・フランクルの強制収容所の被収容者についての文章は、仮に、今の日本の組織で働いている人間がもつようになる特徴を言っているのだ、と言われたとしても違和感がありません。
特に「自ら抵抗して自尊心をふるいたたせないかぎり、自分はまだ主体性を持った存在なのだということを忘れてしまう。内面の自由と独自の価値観を備えた精神的な存在であるという自覚などは論外だ。人は自分を群衆のごく一部としか受けとめず、「わたし」という存在は群れのレベルにまで落ちこむ。」という記述は、日本のあるべき社会人像のデフォルトとなってしまっている印象さえ持ちます。
例えば、自分の業務をこなしたあとも会社に長時間いることや、その後のプライベートの時間をさいて先輩や上司の気分次第の飲み会に参加して、どれだけ上席の人の気分を気持ちよくできるか、といったような、どれだけ私的な時間を会社のために使っているのか、ということが暗んに評価されて、その不文律に従うことが処世術てきに出世しやすい慣習と環境があります。そのような習慣で報奨が伴えばおのずと、懐疑的な精神を持っている自分がバカらしくなるのは当然です。環境も慣習も、いいも悪いも人をかえるものです。
かつては、会社が自分の存在意義や正当性を与えてくれ、「守ってくれている」という信仰のようなものが支えとなっていました。これは、自他の区別が未分化な西洋の中世の精神性に似ています。しかし、中世のような絶対的な身分制度も社会基盤、経済基盤などは近代以降の資本主義のもとにはありません。ついで、日本の終身雇用制はとうに崩壊し、経済はより流動的になっています。もう、会社に自分を犠牲にして尽くしても、「守ってもらえる」という幻想を信じていられるのはごくわずかな人たちだけでしょう。
ここから言えることは、個々人を生きずらくさせる閉塞感や自発的な活動を妨げている日本の鬱々とした雰囲気は、既存の組織で働いている上の立ち場に立っている個々の人間の主体的な成熟度・質に影響されているということです。なぜなら、人が集団でなにかをする以上、権力が伴ってくるからです。主体の確立が不十分なものが上に立ち、下の人は上に影響をうけて日和見主義に陥り、その世代はさらに下の世代へ、、、といった具合に劣化の連鎖が起こっている。
日本の閉塞感の問題はつきつめていくと、わたしたち一人一人の個人的な「能力」の質の問題に行きつきます。そして、これは教育によって新しい世代に上から与える方法だけでは実現せず、実際の社会にいる人間が、「私」として生きる以外には本質的には解決できないことです。これは、政治家の質、メディアの質、文化の質にも言えます。これらのいずれかが酷いといわれているなら、それは、その社会の現役である一人一人の質が酷いのだという厳しい現実を見ないわけにはいかなくなります。政治家は国民が選び、メディアのテーマは視聴率が決めるからです。
そんな日本でも、少数派とはいえ、スポーツやビジネスや研究者、アーティストの中で突き抜けたほんの一握りの人たちは、日本で育ちながら、因習にたいして盲従せず、自分の言葉で話す姿勢をしめし、自他の区別を意識している人がたしかにいます。自分が保身から謙遜を超えた卑下をしたり、密かに見下しマウントをとって優越感にひたるよりも、自分が好きだと思ったことの発展のために、好きになってもらうために信念をもって活動をしています。そういう人を見つけると、わたしはそのジャンルにたいして興味がないにもかかわらず、励まされたような気持になり、応援したくなります。
『鬼滅の刃』にハマった20代、30代、40代の社会人層は、「自分はまだ主体性を持った存在なのだということを忘れ」、「強制収容所に入れられた人間が集団の中に「消え」ようとする」ようになりかけている自分の姿と、「私」であったことさえも忘れ、代理満足で自分をごまかし、意思などはじめからなかった「もの」のように無視され続ける「鬼」の悲哀に、同情というチャネルで共感しているのかもしれません。
とはいえ、、、
とはいえ、いやいや、プライベートではそれはありうるけど、社会人としてそれは青臭い甘えだ、という意見があるかもしれません。たしかに、このあたりは検討に値します。無惨と鬼との関係は、私的な関係ではなく、ビジネス関係なんだと見ることもできます。権力が伴ってくる組織で働く際、私たちはこの問題をどうやって考えて整理していけばいいのでしょうか。社会人になることこは精神の自由、つまり「私」をあきらめることなのでしょうか?
話はこの、自由と服従の問題にうつっていきます。
次回の話は、自由と服従の問題にうつっていきます。
お付き合いありがとうございました。
参考文献
[放送局] TOKYO MXほか
「劇場版 鬼滅の刃 無限列車編」
[原作] 吾峠呼世晴
[監督] 外崎春雄
[脚本] ufotable
[キャラクターデザイン] 松島晃
[音楽] 梶浦由記、椎名豪
[制作] ufotable
[製作] アニプレックス,集英社、ufotable
[配給] 東宝,アニプレックス
[封切日] 2020年10月16日
[上映時間 ]117分
その他 PG12指定
「自由からの逃走」
[作者] ERICH FROMM
[訳者] 日高 六郎
[発行者] 渋谷 健太郎
[発行所] 株式会社 東京創元社
「スマホ脳」
[著者] アンデシュ・ハンセン
[訳者]久山葉子
[発行所] 新潮社
「心を開く対話術」
[著者]泉谷 閑示
[出版社] ソフトバンククリエイティブ