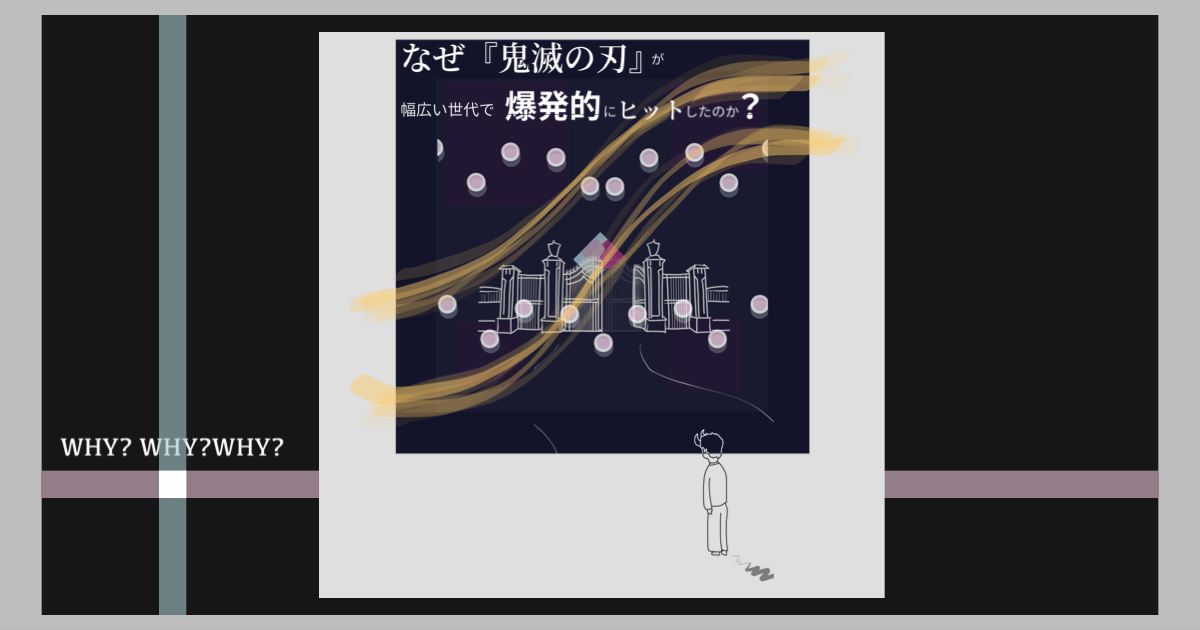こんにちは、matsumoto takuya です。今回も前回にひきつづきシリーズ「なぜ『鬼滅の刃』が幅広い年齢層に爆発的にヒットしたのか?」をおおくりします。
前回の投稿で、現代にいきるわたしたちは、今・ここにある心・身体、つまり生きている「私」となはれてしまっている傾向があり、わたしたちは『鬼滅の刃』の中に、日常で切り離してしまいがちな「生」の部分をみて、こころ惹かれているのではないか、というところまで行き着きました。
それではどうして私たちは日常で「生」の部分を切り離してしまいがちな状態になってしまっているのかという疑問が浮かびます。この理由のほうが、『鬼滅の刃』が大ヒットしたことの理由としてふさわしそうな気がします。
今回は第2回「「鬼」化するワタシ」です。
では、さっそくいってみましょう。
目次
能動にみせかけた受動
一人でいる時とは、だれかに気を配ったりしなくていい状態であり、言い換えれば、あるがままの自分である時です。そして、あるがままの自分とは肉体であり、心・身体です。
わたしたちは、コロナ禍により、一人でいる時間が増えたわけですが、あるあるがままの自分でいる時間が長くなってくると、あることが問題になってきます。コロナ禍により「みんな」と足並みをそろえる圧力が一時的になくなると、かえって何をしていいのか分からない自分に直面するのです。自分自身に「何がしたいの?」と問いかけてもなかなか返答がかえってこない。なぜ、こんなことになるのでしょうか?
近代以降の人々の特徴について述べているのが、次に引用した文章です。
―――真実―すなわち近代人は自分の欲することを知っているとというまぼろしのもとに生きているが、実際に欲すると予想されるものを欲しているに過ぎないという真実ーを漠然ながら理解できる。このことを認めるためには、ひとが本当になにを欲しているかを知るのは多くの人が考えるほど容易なことではないこと、それは人間がだれしも解決しなければならないもっとも困難な問題の一つであることを理解することが必要である。しかし、それがレディ・メイドの目標を、あたかも自分の目標と考えることによって、遮二無二避けようとしている事柄である。---もちろん我々は、それが俳優や催眠術にかかった人間の行動と同じように自発的なものではないことを知っている。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社
注)「近代人」は現代人とほぼ同義です
わたしたちが日常でなにか選択をするとき、もちろん自分で決めています。しかし、その動機をすこしほりさげてみると、「~したい」よいうよりも「ウケがいいから」といったものや、「みんながそうだから」といった理由である場合が意外と多いことに気が付くはずです。「〇〇歳までに~するべき」というのもそうでしょう。
わたしたちの「~したい」の中には、この「ウケがいいから」や「~すべき」というものが偽装するかたちで紛れ込んでいます。フロムのいう「レディ・メイドの目標」とは、「他人からどう見られるか」という他者評価が「~したい」に巧妙に偽装されてできたものです。
近代人(現代も含む)は、自分で何かを選んでいるとき、二種類の動機を内にもっており、多くは「自分の目標」を動機にしているのではなく、「実際に欲すると予想されるもの」、つまり、他人が評価しそうなものを動機にしている傾向が強いのだと、フロムは言っているのです。その場合、その動機をもとにした行為は、能動にみせかけてはいるが、本質的な意味では受動であると指摘しています。
「レディ・メイドの目標を、あたかも自分の目標と考えることによって、遮二無二避け」てきた「自分の目標」を失っている事実、自分で思っていたより自分が「空っぽ」だった事実を、コロナ禍が暴露したわけです
悩みがない人間とは
もし、他人の目線にそって自分の人生を選んでいけば、悩む必要がなくなっていきます。特にしたいことがわからなくても、何らかのみんなが従う「あるべき姿」に従い、みんなにウケがよさそうなものに従うか、みんながやっているもの、もしくはランキングにしたがえばいいからです。現にわたしたちの周りには、「あるべき姿」やランキングを内容にした情報であふれています。
スマホをのぞけば、手っ取り早い「レディ・メイド」の目標や解決方法を最短で知ることができる環境化では、むしろ、自分が悩みをもっていることが「普通」じゃないような気がしてくるほどです。
しかし、わたしたちに個性のあらわれである心というものがあり、人間は完璧な人などいないということを考えれば、「悩めない」という状態は少し不気味です。この悩むことへの態度について、養老孟子氏はこういっています。
しかしそもそも人間、悩むのが当たり前なのです。今では京都大学の教授になった私の後輩が若い頃、解剖学をやろうかどうしようか迷っていた。それで先生に相談した。すると、その先生は一言、「悩むのも才能のうち」と言ったそうです。それで彼はホッとした。そもそも悩めない人間だってたくさんいます。そういう人がバカと呼ばれるわけです。悩むのも当たり前だと思っていれば、少なくともそんな辛い思いをすることはない。
養老孟司『死の壁』:株式会社 新潮社:173項
「悩めない人間 」を「「バカ」と断言しているところは痛快ですが、養老孟司氏が言うように、人は悩みをもっているのが当たり前です。『鬼滅の刃』では、登場人物の苦悩が繊細にえがかれていて、そういう部分を見ているとついつい引き込まれます。ああ、悩みがあるのはわたしだけじゃないのね、とほっとできて、その登場人物に人間味を感じるからです。
現代に生きるわたしたちは、この悩むこと、悩みをもっていることが苦手です。そしてわたしたちの動機が他者評価に染まってしまっている。悩みを持っていることが苦手で、自分の気持ちを放置してでも、多数派の評価しているものに合わたくなる衝動を内にかかえているのです。
デフォルト化したマザコンと閉塞感
どうしてこのような状態にわたしたちが置かれてしまっているのでしょうか。それは、わたしたち人間に個性がある、ということ関係しています。この理由を述べた文章が次に引用した文章です。少し長いですがここには、重要なことが書かれています。
個性化の過程の他の面は、孤独が増大していくことである。第一次的絆は安定性をもたらし、外界との根本的な統一性をあたえてくれる。子どもはその外界から抜け出すにつれて、自分が孤独であること、全ての他人から引き離された存在であることを自覚するようになる。この外界からの分離は、無力と不安との感情を生み出す。外界はこじんてきな存在と比較すれば、圧倒的に強力であって、往々にして脅威と危険に満ちたものである。人間は外界の一構成部分であるかぎり、個人の行動の可能性や責任を知らなくても、外界を恐れる必要はない。人間は個人になると、独りで、外界の全ての恐ろしい圧倒的な面に抵抗するのである。
ここに、個性をなげすてて外界に完全に没入し、個人と無力の感情を克服しようとする衝動が生まれる。しかしそれらの衝動やそれから生まれる新しい絆は、成長の過程でたちきられた第一次的絆と同一のものではない。ちょうど肉体的に母親の胎内に二度と帰ることができないのと同じように、子どもは精神的にも個性化の過程を逆行することはできない。もしあえてそうしようとすれば、それはどうしても服従の性質をおびることになる。しかもそのような服従においては、権威とそれに服従する子どもとのあいだの根本的な矛盾は、けっして除かれない。子どもは意識的には安定と満足とを感じるかもわからないが、無意識的には、自分の払っていく代償が自分自身の強さと統一性の放棄であることを知っている。このようにして、服従の結果はかつてのものとは正反対である。服従は子どもの不安を増大し、同時に敵意と反抗を生みだす。そしてその敵意と反抗は、子どもが依存しているーーー依存するようになったーーーまさにその人に向けられるので、それだけいっそう恐ろしいものになる。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社:29
第一次的絆とは、母親と乳児の関係や、閉鎖部落内で人と人を結びつけ自他の区別を必要としない絆を指します。個性があるとは、人はそれそれ独自であり独立性を持つということです。完全に自分と重なり合う人は現実には一人もいない、自分の選択が正しいということを測れる指標が外にはないし、マニュアルもないということです。ひとは精神的に成長するにつれ、同時に孤独も自覚する。不安を感じるものなのです。
フロムは、自らの個を自覚し、自由なったと同時に孤独を自覚するにいたった人間がとる選択肢は、二つにわかれるとしてこう述べています。
すなわち他人や自然との原始的な一体性からぬけでるといいう意味で、人間は自由となればなるほど、そしてかれがまたますます「個人」となればなるほど、人間に残された道は、愛や生産的な仕事の自発性のなかで外界と結ばれるか、でなければ、自由や個人的自我の統一性を破壊するような絆によって一種の安定感を求めるか、どちらかということである。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社:29項
「他人や自然との原始的な一体性」とは先に挙げた「第一次的絆」のことです。この関係は依存的であり、強い安定はありますが個の抑圧を前提にします。人はそのまま個性を成長させ、自発性によって社会(人間)と結びつくか、依存ベースの「絆」に服従する形で戻っていくかの二通りとなり、前者が挫折された時に後者が選ばれます。フロムは、自発性によって社会とむすびつけない場合に、依存ベースの「絆」に服従する形で戻っていった人間に多くみられる精神状態を、こう解説しています。
かれは、もし自分が欲し、考え、感ずることを知ることができたならば、自分の意思に従って自由に行動したであろう。しかし、彼はそれを知らないのである。かれは匿名の権威に協調し、自分のものではない自己をとりいれる。このようなことをすればするほど、彼は無力を感じ、ますます同調をしいられる。楽観主義と創意のみせかけにもかかわらず、近代人は深い無力感に打ちひしがれている。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社
なんらかの障害によって、ひとの個性化の発展が妨げられ、内面的な強さや関係を作り出していく力が十分発達できない場合、ひとは無力感と孤独の不安に耐えられず、自分の個性を犠牲にしてまで何らかの「匿名の権威」への同調に駆り立てられる。そして、「匿名の権威に協調し、自分のものではない自己をとりいれ」た人間は、自らの人生の選択を自分でしているようにみえるが実際は、自己にとりいれた「匿名の権威」に従い選択するようになるのです。
「匿名の権威」とは、日本では「世間」、「みんな」、「普通」とか言ったときにさす実態はないが個人の選択に影響を与えてくるものです。「レディメイド」の目標が自分の目標ではなく、「能動にみせかけた受動」であるというフロムの指摘は、取り込んだ「匿名の権威」が用意した目標に自分を従わせているからです。親が「世間」に服従するタイプであれば、そのこどもが個性化を妨げられ、自発的に社会とつながっていけない場合、子どもは親のしたがう「世間」の価値観に服従しなおすことになります。通称マザコンです。
ひとりでいる時の無力感、「他人ウケ」や「世間体」以外にしたいことがわからない状態、そして日本社会にただよう息が詰まようなる閉塞感の出どころは、「匿名の権威」に同調することで今・ここに生きている心・身体をもった「私」を放置していまい、「私」がすっかり委縮している状況から副次的にでてきたものだったのです。
「鬼」化するワタシ
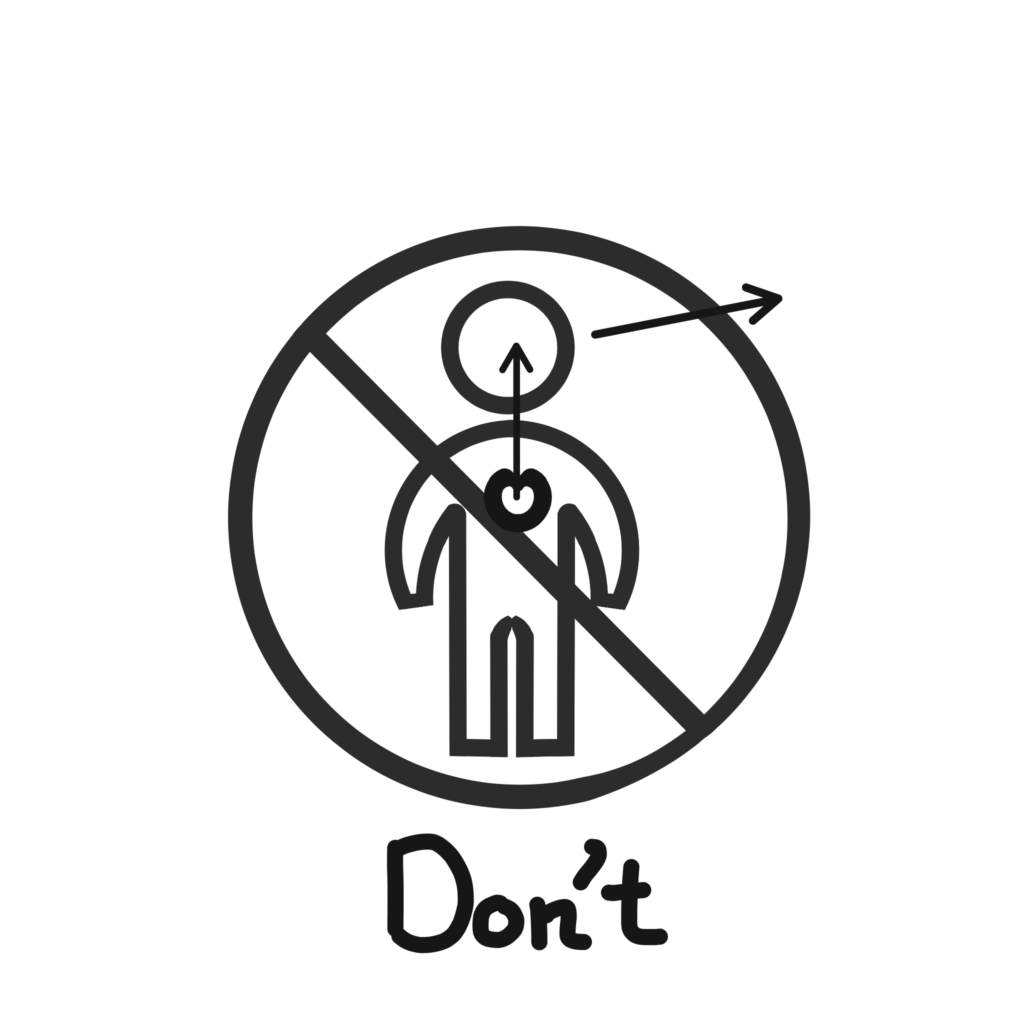
ここであることに気が付きます。「私」を放置しわすれてしまった存在が『鬼滅の刃』の世界にも登場しているのです。それは、「鬼」と呼ばれる存在です。
人間を喰らう存在である「鬼」は、元々は人間でした。かれらは、鬼となることで不死身の肉体を持つ代わりに人間の頃の記憶を失います。人間の頃の価値観を失うかわりに、人を食べたいという消費欲と他を支配できる力への渇望を持つようになりますが、それは自分を「鬼」にした鬼舞辻無惨の価値観です。腕がちぎれてもすぐ再生するので、身体の声である苦しみや痛みに関しておそろしく鈍感です。
いまの日本に生きるわたしたちは、「私」という心・身体という個性が放置されて切り離されてしまっている点、自分の目標の動機が外から用意されてしまっている点、そして、それを自分だと思い込んでいる点でまさに共通しています。そして、心身の声を大事にできず、身体が悲鳴を上げるまで気がつかないか、我慢してしまいます。わたしたちはどうやら「鬼」化しているといえてしまうのです。
その「私」を諦めたことの代償の一つが、フラストレーションです。
早稲田大学名誉教授の池田晴彦氏はこう言っています。
ただ、いくら日本人が不思議な感性をしているといっても、あきらめてばかりいたらフラストレーションがたまる。そこで、いじめてもいい相手を見つけ出して攻撃し、うさ晴らししようとなるわけだ。それが自粛期間中のパチンコ叩きであり、自粛警察であり、コロナ患者や医療従事者への嫌がらせであり、亡くなったった女子プロレスラーの木村はなさんへの誹謗中傷であったわけだ。
池田晴彦 『自粛バカ-リスクゼロ症候群に罹った日本人への処方箋-』宝島社新書
この時に、ストレスをぶつける対象にされれやすいのは多くの人と違うことをするマイノリティなんだけど、実は日本人が一番気に入らないのは、自分が我慢ているのに、楽しそうにしていたり、上手くやっていたりするやつなんだよ。
自由の権利や、多様性を制度としては認めているのに、「私」をお預けされている状態と、その状態をせまる同調圧力は、このようなフラストレーションや無力感をわたしたちの内にため込ませます。そのため込まれて腐敗したストレスの憂さ晴らしとして、自分が窮屈な思いをして服従している同調先に同調しないマイノリティーがやり玉にあげやすく、度を越えてバッシングしてしまう衝動にかられてしまうのです。「悩めない」状態は、このように極端になりやすく、また自身の考えを顧みることが難しくなります。
『鬼滅の刃』は主人公の竈戸炭次郎が、鬼となった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼の侵害にあいながらも大切な人を人間に戻す方法を探していく物語です。この物語は、こうもいいかえれます。心・身体をもった「私」としての生きている主人公たちが、人間としての心・身体をうしない「私」をわすれた存在である「鬼」の侵害に屈せず立ち向かい、大切な人の人間としての性質である「私」を取り戻す戦いの物語である。
日本の環境は、わたしたちに「私」を放置するよう迫る、目にみえない同調圧力をもっています。この圧力は、「多様性のある社会」を掲げているのにもかかわらず、なぜか以前として強力で、わたしたちの内にフラストレーションを潜在的にため込ませます。知らず知らずに「私」が窒息しそうになり「鬼」化していくワタシに、「私」の側にたって戦うストーリーはハマるべくしてハマったといえます。
もちろん、漫画、アニメの技術的な構造や日本古来の物語への相関といったヒット要因がいろいろ考えられるしょうが、社会現象ともよべる爆発的ヒットを可能にした説明ができません。幅広い年齢層に心・身体を持った「私」として生きることへの飢えに近い需要がなければ、少年漫画・アニメの枠内でのヒットで終わっていたはずです。
ところで、どうして今の日本は、多くの人が閉塞感をいだくほど、息苦しい状態にますますなってきているのでしょうか?
最近はスマホの登場で海外の欧米の情報が個人レベルで自由に手に入る環境があり、多様性のもった社会の必要性は周知されています。そして、ご存じの通り日本は個人の自由を前提とした社会制度をとっている民主主義国家です。社会の成熟につれて同調圧力も減り、閉塞感が打破されていてもいいはずです。わたしちを「鬼」化させる日本の環境はいつからはじまったのだろうか?それはどうしてなのか?どのようないきさつで今の環境がつくられてきたのだろうか?という疑問が浮かびます。
次回では、「鬼」化のルーツを、近代史をさかのぼりながら探っていきます。
お付き合いありがとうございました。
参考文献
「構造・神話・労働 クロード・レヴィ=ストロース日本公演集」
[作者] 大橋保夫編 三好郁郎・松本カヨ子・大橋寿美子訳
[発行所]株式会社みすず書房