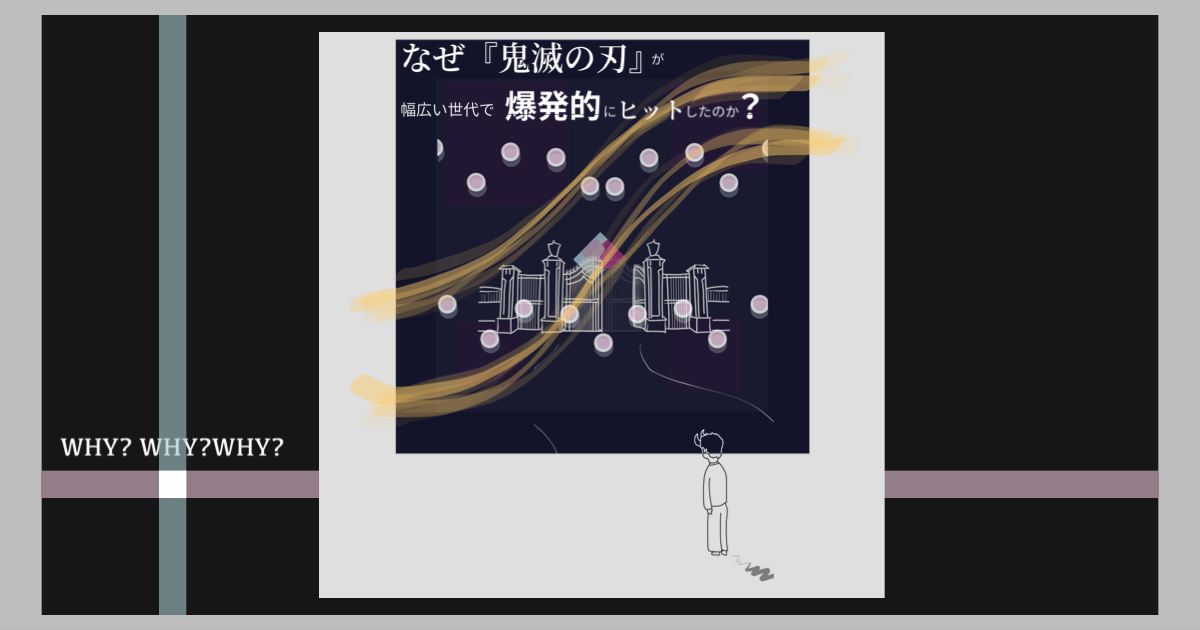こんにちは、matsumoto takuya で。今回も前回にひきつづきシリーズ「なぜ『鬼滅の刃』が幅広い世代で爆発的にヒットしたのか?」をおおくりします。
前回の投稿で、『鬼滅の刃』からみる「普通」の姿の歪みがみえてきました。
今回は、『鬼滅の刃』から現代の現状を浮き彫りにしながら、「なぜ『鬼滅の刃』が幅広い世代で爆発的にヒットしたのか?」のまとめに入っていきたいと思います。
では、さっそくいってみましょう。
目次
「鬼」と自分の商品化
「なぜ『鬼滅の刃』は世代をこえて異常なほど大ヒットしたのか?その9」気になる方はこちらへ
ここでもう一度、現代人がもつ傾向について話を向けていきたいと思います。 自分を見失った人の典型的な人間観について、フロムはこう述べています。
フロム・・・エーリッヒ・フロム。20世紀を代表する社会・心理学者。社会の中の個人の孤独と自由を専門とした
経済的な関係ばかりでない、人間的な関係もまた、この疎外された性格をおびている。それは人間的存在の関係ではなく、物と物との関係である。しかしこの手段と疎外の精神のもっとも重要な、もっとも荒廃した例は、おそらくは人間の自分自身に対する関係であろう。人間はたんに商品を売るばかりではなく、自分自身をも売り、自分自身をあたかも商品のように感じている。
・・・商品と同じように、これらの人間の性質の価値をきめるものは、いや、まさに人間存在そのものをきめるのは、市場である。もしある人間のもっている性質が役に立たなければ、その人間は無価値である。ちょうど、売れない商品が、たとえ使用価値があっても、なんの価値もないのと同じである。このように、自信とか「自我の感情」とかは、たんに他人の自分にたいする考えをさしているのにすぎない。それは市場における人気や成功とは無関係に、自己の価値を確信している自我ではない。もし他人から求められる人間であれば、その人間はひとかどのものであり、もし人気がなければ、かれは無に等しい。自己評価が「人格」の成功に依存しているということが、近代人にとって人気が恐るべき重要さをもってくる理由である。ある実際的なことがらで、うまくいくかどうかというばかりでなく、自尊心を保つことができるかどうか、劣等感の深淵に落ちるかどうかということも、すべて人気にかかっている。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社:136項
自分を見失うということは、自分自身への認識が、数値化できるものや役に立つかといった外からの評価だけに偏ってしまう側面をもちます。その場合、その人は人間を「物」と同じようなドライはものとして捉えるようになり、それはまず、自分の自身への認識からはじまります。第一章で養老孟司氏が、現代人は自分自身を変化する生き物としてでななく、変化しない「情報」として見るようになってしまった、と言っていた文章を紹介しましたが、ここにつながります。
「物」とは売買・交換でき、所有できるものであり、使用し消費できる対象物であり、経済の秩序にふくしているため市場が価値を決定します。売れるか、売れないか、役に立つのかどうかが、そのまま商品の価値になる。自分を「物」と同じように捉えてしまえば、売れるか売れないか、人気のあるなしが、その人の存在についての価値観と一致することになってしまいます。
わたしたちが何かをするときの動機をすこしふかぼりすると、実は他者評価を得ることが目的であることが多い背景には、こういう事情がひそんでいます。タレントという特殊な職業がありますが、タレントが、特殊な仕事であり、時に大金を得られることには理由があります。「私」という主体性が十分に成長し確立できていない場合、下手をすると自分を見失い、自分ではどうしようもない人気に、自分の存在が「いい存在」なのか、「悪い存在なのか」をにぎられてしまうことで、心の平和を失ってしまい、例え人気があったとしても、胸のうちにおおきな「虚ろ」を抱えてしまうリスクを背負っているからです。大人とは違い、子どもの場合は、そもそも精神能力そのものが生理的にも発達途上にあるので、当然、そのリスクは跳ね上がります。
タレントとは違う一般人、つまり、わたしたちが自分を「物」のようにとらえてしまったとき、労働市場、婚活市場といったなんらかの「市場」で売れ残っている場合、その人の内面では「おまえは使用価値のない無価値な存在だ、口答えは無用だ、生産性のない売れない商品に価値はない、お前はなんてダメな奴なんだ」という自責の念が吹き荒れることになります。これは、まるで鬼舞辻無惨が身内の「鬼」にはなつセリフと似ていることに気がつきます。
これは偶然ではありません。無惨と鬼の関係は、まさに純化された「物と物の関係」だからです。かれらの関係は、「私はお前とつきあうことでどのような目にみえる見返りがえられるのか」という利害関係のみで成り立っています。無惨ににとって、彼に同じように役立つのであれば、鬼Aだろうが鬼Bだろうと関係がないのです。無惨がその鬼にやさしくなるのは単純にその鬼が役に立ち自分の支配下にあるからです。無惨にとって鬼とは自分の思い通りにで操作できる対象であり、愛玩の対象であり、つまり、「物」です。彼は、自分の思いどおりに動かせる「おもちゃ」を喜んでいるのであって、その「鬼」を愛しているわけではないのです。
ネット、スマホとSNSの出現により、かつて一枚岩であった「世間」は分散化され無数に分化さてていますが、自分を疎外した場合におこる本質は変わりありません。「私」という判断主体を失えば、ひとは世間体に引っ張られ、お金や世間受けといった外的な測れる指標でしか自身の価値を見出せなくなることに変わりはないからです。
婚活が滅入るわけ
この、「人をモノとしてみる」「人間的存在の関係ではなく、物と物との関係」「自分自身をあたかも商品のように感じている」ということが、今の日本の「世間」に浸透している分かりやす例をあげるとすれば「婚活市場」でしょうか。
交換可能な商品として、自分の人格を情報パッケージ化して売りに出し、相手の人も同じよう人格をパッケージ化した情報を交換して品定めすること婚活市場の中身ですが、家族に関わってくる私的なことに関して「市場」という露骨な言葉が使われていることに、私は違和感を覚えます。結婚が、完全に愛だけではできないのがわたしたちだとしても、「人間的存在の関係ではなく、物と物との関係」をストレートに表現した「婚活市場」という言葉に違和感と不気味さを感じるのです。
婚活そのものは出会いの場の一つとして有効だとは思うのですが、「結婚は絶対的に幸せの条件で、できないは人どこか問題がある」という固定観念のようなものを婚活市場が放ち続けてくる場合は厄介です。結婚という手段が目的となり自分自身を犠牲にしてしまっては本末転倒ですし、「みんなそうしてるのに、あなたはしないのですか?」という圧力がその人の幸せのためになっているかどうかは疑問です。結婚というステータスではなく、中身が肝心なのは言うまでもないことです。
そのうえ結婚が目的化してしまっては「人をモノとしてみる」という態度を実践で強化してしまいます。習慣は人をかえる力があるので、自分のコレクション、珍しいモンスターを探す「モンスターハンター」化してしまいます。
たまたまいい出会いがないだけなのに、「売残り感」「とりのこされた感」でダメ押しの自責をもたらします。 婚活に疲れはてた人が少なくないのは当然といえますし、自分を含め人間を「物」として見ることにうんざりするほうがまともといえます。
愛を交換できる商品であるという価値観があってもいいのではないかという意見もあるかもしれません。もちろんそれも個人の自由です。ちなみに、定義からいうと、愛するのに相手にいくらかかるか要求するなら、それは愛ではなく売春です。
「鬼」は尊厳の意味がわからない
前章で登場してもらったフランスの哲学者スポンビルは、人間存在について労働と対置させながらこう説明しています。
人間の尊厳をなしているものは自分が何の役にたっているのか(彼の有用性)ではなく、その存在そのもの(人間であること)なのです。尊厳をつくるのは労働ではなく、人間であることです。労働はそのために役立つものでしかありません。だからこそ、労働は重要な価値を持つわけですが、それはあくまでも手段としてなのです。
アンドレ・コント・スポンビル小須田健/C・カンタン訳:『資本主義に徳はあるか』:紀伊國屋書店:234項
人間存在の価値は、市場や集団がきめるのでしょうか?市場や集団が「価値なし」、といえばその人はゴミと同じなのでしょうか?そんなことはありません。「人間の尊厳をなしているものは自分が何の役にたっているのか(彼の有用性)ではなく、その存在(人間であること)そのもの」です。同じように、人間の尊厳をなしているものは市場で人気があるかどうか(モノとしての経済的価値)ではなく、その人がただそのひとらしくあること(人間であること)そのものだからです。
これは、個人の領域の価値と経済の領域の価値が混同されてしまっていることから起きる富の圧制とよばれるものです。そして、富による圧制は、人類史ではもっともこころの貧しい集団がおちいる圧制でもあります。
「私」を見失ってしまうと、外からの評価や、それにつながる役立つかどうかによって自分の存在が揺さぶられてしまいます。この人間存在への態度は、自分自身だけでなく他者にもむけられ、こいつは利用できるのか、こいつは金になるのか役に立つのかという視点のみになっていくのです。これはまさに、無惨と鬼たちのさもしい価値観です。モノとモノの関係、利害関係者の世界です。
『鬼滅の刃』の世界で炭次郎たちが、「鬼」のいない世界を目指す理由は、「鬼」が人間を食べるからなのですが、すこし引いた視点でみれば、「鬼」が人間存在の価値を見出せず、人を「モノ」として扱うからでるあると言い換えることができます。
その結果としてうまれる悲惨な様を、もうこれ以上は見たくないと、彼らは自分を鼓舞して戦っているわけです。一人の人間は「モノ」じゃない、そんな安っぽちくはない、人間は、ただその人であるだけで十分に命をかけて守る価値のあるものだ、人間なんだから、という信念のもと活動しているのです。
今の日本では、市場価値や有用性、コスパといった経済の領域の事柄が、私的な領域まで決定するような情報が溢れています。お金はある程度は必要ですが、お金のために肝心の心が貧しくなる事態は避けたいものです。
生産的であることへの強迫観念のルーツ
話はすこし飛びますが、中世末期の西洋で大流行したキリスト教プロテスタントの一派で、カルヴァン派があります。現代人のパーソナリティーに影響を与えたことで有名です。
カルヴァンは中世末期、宗教改革時のキリスト教プロテスタントの指導者のひとりです。彼は宗教改革で有名な同じ指導的立場にあったのルターより、個人の無力さ・無意味さを強調し、道徳的生活の重要性を著しく強調する教えを特徴としていました。また、「予定説」という人間の運命はあらかじめ決まっている、という考えを持っていました。カルバンの教えである個人の無力さ・無意味さの強調と、その死後の救済がわからないという不安がかえって、信者をたえまない苦行の生活や努力に駆り立てたてることになります。
これが近代の資本主義の発展に関わってきたことを社会学者であるマックス・ウェーバーは著書『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(『The protestant Ethic and the Spirit of Capitalism』)で示したことで有名です。
経済が異常なほど崇拝される現代においては、資本主義発展への肯定的側面ばかりに目が行ってしまいますが、そこには代償がありました。フロムは、カルヴァン派の信者(カルヴィニズム)のパーソナリティについてこう分析しています。
このたえがたい不安の状態や、自己の無意味さにについての委縮した感情から、逃れるただ一つの道は、カルヴィニズムできわめて優勢となったまさにその特性だけである。すなわち熱狂的な活動となにかをしようとすうる衝動の発達である。このような意味の活動は強迫的な性質をおびてくる、個人は疑いと無力さを克服するために、活動しなければならない。このような努力や活動は、内面的な強さや自信からうまれてくるものではない。それは、不安からの死に物狂いの逃避である。
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』日高六郎訳 東京創元社:99項
死後の運命があらかじめ決まっているという教えを信じるカルヴァン派のなかで、努力の結果である世俗的成功・失敗が、そのまま自分の存在が善か悪か、救われるのか・救われないのかということのしるしとなる、という強迫的な思考につながっていきます。そのため、かれらの態度は、人類史でかつてなかった態度を人々の性格にうえつけることになりました。それは、「努力や仕事を目的それ自体を考える新しい態度」です。人間が目的ではなく、手段であるはずの仕事の手段として使われる人間がある、つまり、自分自身を人間存在としてではなく、「物」として見る態度です。
「したい」という気持ちが動機ではなく、「すべきである」という教えが動機にある努力や活動は、「内面的な強さや自信からうまれてくるものではな」く、「不安からの死に物狂いの逃避」であるという点が特徴です。
このような自虐的態度の帰結として、個人のうちに無力感をためこませ、徹底した強者賛美と弱者への侮蔑の態度をまねき、西洋では全体主義が芽をだしはじめます。
一見、日本と関係ないように思われますが、かつてのカルバン派の信者が、世俗的な成功・失敗が自分の存在の未来(死後の世界)に左右されると考えたように、現代のわたしたちは、他者からの評価といったものがそのまま自分の存在価値を左右する、と強迫的に考えるようになっている点で似たような不安のタネを抱えてしまっているのです。
「鬼」化と罪悪感
休暇をまとめてドガっととったり、休暇を取ったのに何もしていないで一日を過ごした時に、なぜか、罪悪感を抱いていてしまう、大勢の前で目をみて自分の言葉ではなさなければならないときに恐怖を覚える、という人は割といると思います。
何らかの宗教を信じている人は、その宗教が善悪の見方を示します。個人主義の場合は「私」が様々な価値観に触れ認識を深め成長するなかで倫理観を自ら育みます。「私」という主体の確立をあきらめて「世間」に服従している人の場合、その人は何を基準に善悪の判断をしているのでしょうか?
それは「世間」です。「すべき」や「あるべき姿」といったかたちで「世間」が個人に内側から語りかける時、世間がしめす「あるべき姿」は善であり、それに従わない場合は悪であるという倫理観が不随しているのです。
その場合、「世間」に服従しているひとが、世間の示す「あるべき姿」に従わないことに自覚的であった場合、それは倫理規範を犯したこと、罪を犯したことになります。罪であるなら、それは罰すべきこととなります。
大勢の前で、相手の目をみて自分の言葉で話すときに恐さを感じるのは、自分の言動が「世間」に合致しなければ罰せられる可能性があると思っているからです。この精神的な縛りは、「私」を許さない社会のなかで成長していく過程で、何らかの痛い思いをした実体験として紐づけされ現実感を醸してきます。
別の視点から見てみると、「世間」に服従しているひとにとっては、それに自覚的に従わない人は、罪を犯した人であり、当然のこととして、罰してもよいという結論にいたるでしょう。
ここに、どうして日本で同調圧力が強力なのか、どうして、しごきやイジメにブレーキがかからないのか?といった疑問の答えがあります。自分の語る意見が、善であり、それを犯しているイジメやしごきの対象は悪であるなら、罪を犯した者を罰するのは当然であるという結論にいたるからです。「私」という考える主体がないので、なんの個別の配慮もなくこの結論へ飛ぶのも特徴といえます。
「世間」とは実態がなく、多数の人のなかにわたしたちが勝手に見出している空気感のようなものです。実際問題、「世間」に他人の存在の善悪を決めつける力も妥当性もありません。ここに「私」が気が付けるかどうかが、「私」を確保できるカギとなっています。世間がたとえ「私」に否定的な意見を示そうが、それが「私」の存在を揺るがす力も善悪を決める妥当性もないのだ、ということに気が付くことができれば、程度な緊張とは異質な恐怖感のもとである、「罰せられる可能性」そのものが消えるからです。
「世間」に服従している場合、(自分だと思っている)「世間」の意見が自身の存在にかかわる倫理規範と重なるため、自分の意見に固執しやすくなる傾向があります。日本の討論番組をみていると、意見が対立し終始平行線をたどる場面をよく目にしますが、「私」として表現している人が、日本では珍しいことからしたら、当然のことかもしれません。
休日に特に何もしないで一日過ごした時に感じる罪悪感も「有意義に過ごすべきだ」「生産的であるべきだ」という「世間」から用意された意見に、善悪が含まれていてしまっているかです。
なかでも「働かざる者喰うべからず」というあるべき姿は最強クラスの絶対善が含まれてしまっています。失職して自殺してしまう、もしくは、抑鬱になるほど人を苦しめているものは、経済的な理由というよりは、無力感や、「世間」から問答無用に押される罪人のレッテルである罪悪感なのです。
『鬼滅の刃』では、トップクラスの武力をもつ猗窩座(あかざ)という鬼がいます。すでに無双ともよべるほどの力をもつ猗窩座(あかざ)が、強者賛美・弱者侮蔑と、力への異常なこだわりから抜け出せないのは、「私」を奪われた存在が鬼であるという視点から見れば理解できます。彼も他の鬼を同じように「自己の無意味さにについての委縮した感情」からうまれた不安に苛まれ、その不安からのがれるために、「死に物狂い」でマゾヒスティックな鍛錬に駆らせていたのだと考えられるのです。
たとえ役にたっていなくても、お金につながることをしていなくても、人間存在そのものは罰すべき罪など犯しておらず、悪い存在ではありません。この場合の罪悪感は罪でない前に、誤りです。誤りは、罰すべき罪ではなくて、ただ大目に見て訂正するものです。
このように、「私」を放置して「世間」へ服従することは、ひとを「モノ」のように見るようにしむけ、無力感と不安を増大させ、見当違いの罪悪感でわたしたち監視し、責め立てます。もちろん、人間としての誇りの感情も悪ではありません。もしそれが悪であったら、炭次郎は悪であり、無惨が正義だということになってしまいます。
正義の中身
ここにきて、わたしの頭にこんな疑問が浮かびます。
そもそも正義ってなんなんだろう?という疑問です。
『鬼滅の刃』では正義は鬼を退治する鬼殺隊、悪は鬼舞辻無惨ひきいる「鬼」たちという設定です。鬼は人の気持ちなどおかまいなしで人々を喰い、苦しめるい一方、炭次郎たち鬼殺隊はこの鬼の傍若無人なふるまいに立ち向かいます。ここから正義の大まかな姿が見えてきます。つまり正義とは、一部の人だけが持つ特権のためにその他の人々を苦しめるということを良しとしない価値観のことです。
ひらたくいえば、正義とは平等のことです。そして、その構成要素は、合法性と「正当性」の二つとなっています。合法性とは、法であることはすぐにわかります。では「正当性」と何でしょうか。「正当性」とは、先に引用したスポンビルが使った尊厳や人権と呼ばれるものです。その人が正当性をもつ条件とは、その人が役に立ったか(彼の有用性)ではなく、人間であること(存在そのもの)です。
どうしてこう強調したかというと、日常で使われる正当性という言葉とは、少し意味合いが異なってくるからです。この「正当性」こそが、前節でとりあげた「正常」を構成する二つの要素のうちの、個人の領域に支配される「正常」を言いかえたものだからです。個人の領域が欠けた「正常」が病める点は、まさにこの尊厳、人権、意思、自由といったものが人間らしさであるという「正当性」がおざなりになっている点です。
この意味での「正当性」とは、道理にかなっているという意味です。なんの道理かといえば人間であることであり、モラルや倫理と呼ばれるものです。西洋は人間であることについて多くの失敗と悲惨を経験しながら、人間としての道理に叶っている内容に、尊厳、人権、意思、自由、正義といった内容を導き出して今日の社会の土台としています。本来は、そういう市民が独裁者から自分たちでつかみ取る歴史があってようやく手に入るものを、日本は敗戦によりアメリカから与えられるかたちで手に入れました。そのため、わたしたちにはピンとこないのです。
なぜ、「正当性」がない「正義」を受け容れることが問題なのでしょうか?それは反対に合法性しかない場合、なぜ問題なのか、という点をみていくことで見えてきます。
合法性とは、合法・非合法という区別をもち、市民が委託した権力を代表者が強制力をもって執行し市民に強制するものです。この合法性とは法のことですが、この法は一体なんのために存在しているかといえば、尊厳をもった人間が集団で暮らすための便宜のためです。つまり、法は「人権をもった人間」に生活の場をあたえます。
しかし、法は法に意味を与えることはできません。ここがみそです。法に意味をあたえることができる唯一の存在が尊厳を持った人間です。人間のみが「人間性を持った人間」のためにある法に意味をあたえることができるのです。
たとえば、「正当性」が欠けた「正義」をよしとする人たちが社会で実権を握った場合、彼らが集団からみて役に立たたない人は排除したほうが社会のためだと判断した場合、わたしたちは病人、障がい者、高齢者や失業者をまっとうな人間としてみなす必要がなくなります。多様性など問題外となります。場合によっては、彼らを檻のついた狭い施設に閉じ込めて家畜のよう処分する法律をつくれてしまいます。無惨かおまけの残酷で人間性を失ったな世界です。人々の内面では、そのような人たちを内心で人間以下と蔑み見下すことを「普通」とする人間の住む社会となります。
ナチズムは合法のもとに民主主義的手続きにのっとり行われました。かれらのしたことを他国の人からほぼ永遠に指摘されつづけるドイツ人の若者にとっては今も屈辱的な汚点でしょう。そして、かれらの行為を成立させていたのは、熱狂的な一部のナチ支援者だけではなく、一見「クール」に「どうでもいい」という無関心さで傍観するポーズをとっているが、実際のところは、無力感と無関心に支配された下層中流階級等の多数派でした。
多数派だからといって正しさが保証されているわけではないのです。
個人の領域の「正常」を欠いた「正義」とは、正義の両輪である「正当性」が欠けた歪んだ「正義」です。この「正当性」の欠けた「正義」を内容とする「世間」に同調し服従することは、ある程度の安定と引き換えに代償として自分を捨てさせます。「匿名の権威」に服従することは、自分自身を含めて人間をモノとみなす態度、人間関係を「物」と「物」との支配服従関係へ、人間の人間性への無配慮、排他性、閉じた飼育小屋で鶏がひたすら弱い身内をつつきまわし序列をつくることに奔走している家畜の次元へゆっくりとかえていきます。『鬼滅の刃』の「鬼」と「鬼」の関係へとゆっくりと、しかし確実に進めてしまうのです。 だからこそ、「正当性」が合法性と同様に重要になってくるのです。
ロッキングオンが出版している『SIGHT(サイト)』という現代時事を扱った雑誌があります。すこし古いですが、その『SIGHT(サイト)2011年47号』の表紙をが印象的でした。
正常だからうつになる 弱いんじゃない、まともなんだ
『SIGHT(サイト)2011年47号』表紙より:ロッキングオン
もし「正常」が病んでいるならば、適応できないひとがいても不思議ではありません。その人が人として麻痺しきれない大事なものがあったからこそ、その人がまともだったからこそ、ある日歪んだ「正常」が支配する環境にたいして、まともだから不適応状態に陥る正常な反応をしたといえるからです。
『鬼滅の刃』の異常なほどの大ヒットが照らしだしたもの
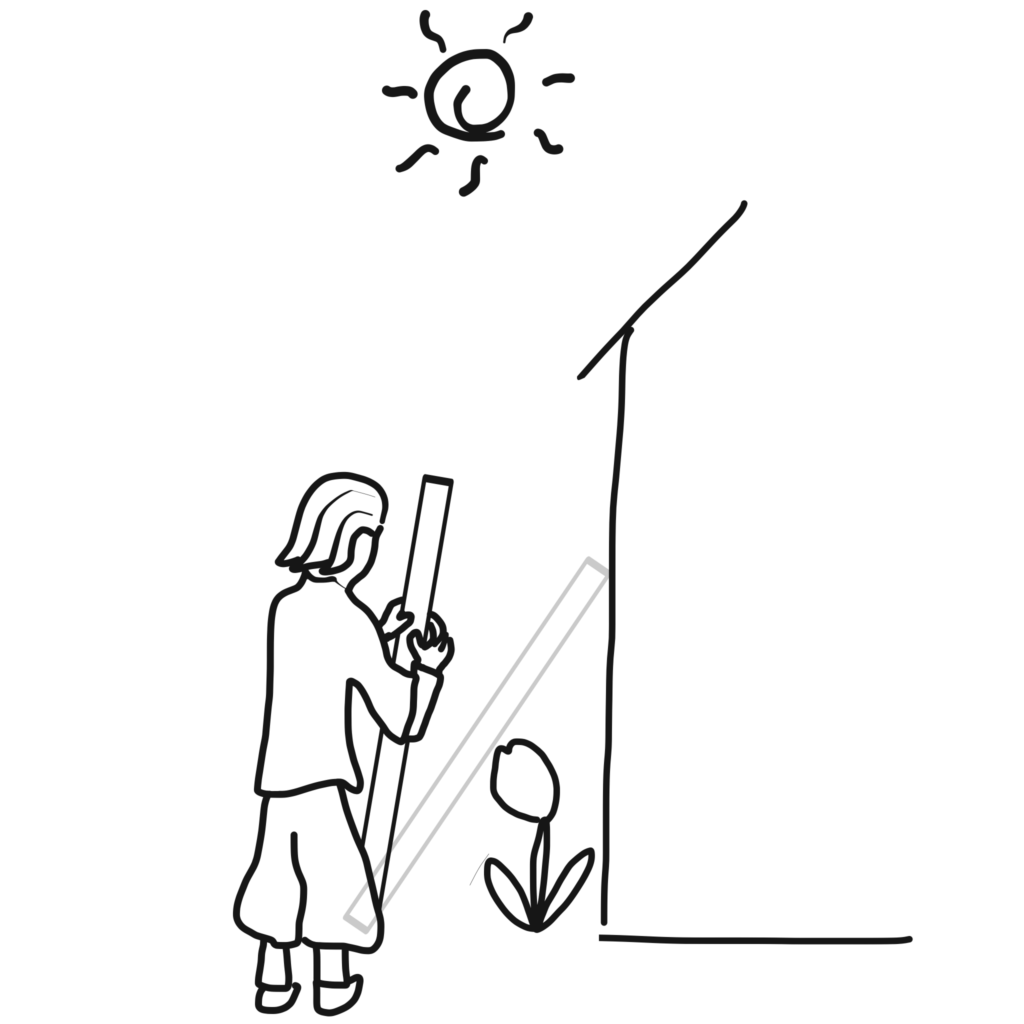
さて、ここまで掘り下げてきて、なぜ、今の日本で幅広い層に『鬼滅の刃』がこうもハマったのかという理由が、おぼろげながらも見えてきたのではないかと思います。
「私」という人間らしさを失うことで、人も同類も「モノ」としかみれないために、支配・服従関係や表面的な関係しか築けず、「私」奪った無惨から与えられる代理満足に奔走させらている存在、それでいて、心の奥底では「人間」として生きれないことからくる無力感や空虚感を人知れずためこむ哀れな存在、それが『鬼滅の刃』の「鬼」です。
これまでみてきたように、現在の日本の環境は、わたしたちを「鬼」のほうへ知らず知らずに押しやります。
意識的には「自分は自由であり、自分で人生を選んでいる」と考えているが、実際は日本の文化的背景からくる同調圧力により、個性を成長・発展することを妨げられ、「私」を放置してでも「世間」といった「匿名の権威」に同調・同化していくうちに「私」からどんどんずれていくワタシ、服従先が用意する「あるべき姿」を耐えずコンプリートしなければ不安を感じてしまう「自動人形」のようなものに成り下がっていくワタシ、自分と同じように服従しないで「私」としていきる人を排除したくなるワタシ、「鬼」化するワタシです。
『鬼滅の刃』が、今の日本で社会現象レベルの大ヒットをしたことからみえてくるものとは、いったいなんなのでしょうか?
『鬼滅の刃』は、登場人物どうしのやり取りが、小説のように内面まで深く表現されています。登場人物がもつ役割の背後にある、その人の感覚や感じ方、思い、考え、そういう内的な世界観が作られるにいたった背景に繊細に丁寧に描かれ、そういった独自の世界観を持った人と人とが出会うことで物語がつくられています。人間であることの誇りと尊厳への感情を臆面もなく表現し、義務や役割だけでなく個性を持った人間が、同じように義務や役割だけでない個性を持った人間に出会うことにより、共感、共鳴し、時に対立しながら成長していくさまが、少年漫画(アニメ)に見事に落としこまれています。
「私」を失った元人間である「鬼」の圧倒的な侵害に屈せず、「私」として生きることに誇りをもって立ち向かい、「鬼」となった大切なひとを人間に戻すための物語に、幅広い世代の多くの人が共感し、心惹かれるのですが、それは、わたしたちの社会と『鬼滅の刃』の世界が、本質的な意味で似ているからです。
表向きには多様性を声高にかかげて半ば個性を成長させておきながら、個人の表現を許さない社会の「ズレ」は個人の孤独感を強調し、社会・経済構は歴史的に著しい流動化と、スマホの普及とコロナ禍にともなう生活様式の激変が孤独感の増大に拍車をかけます。
その「ズレ」により強調された孤独の不安どうにかしたくて、自分を放置してでもいいから「みんな」や「世間」に同調していきます。「あるべき自分」に自分をはめ込んでみたものの、自分も他人も容赦なく追い立てるライフスタイルに疲労と虚しさが忍び寄ります。一生懸命頑張っているのにもかかわらず、人間関係から「内的なつながり」が徐々に感じられなくなっていき、茶番じみた現状にうんざりするも、かといって、「他にこれといってましな選択肢がみつからない」状態。建前の「ワタシ」がどんどんおおきくなっていき、心・身体をもった「私」がどんどん萎んでいく状態です。
特に、「ズレ」を実感する社会人層と学生までの層ではストレスの違いがあるように思えます。社会人層は実際の「ズレ」のストレスが直撃するからです。また、中堅以下は既得権益や権力もありません。今までの価値規範に従うことについての懐疑と、自分をそこまで信じられない懐疑により宙ぶらりんの状態にあります。
これはちょうど、個の目覚めが起こった中世末期から近代の西洋で、既得権にまもられた上流階級と捨てるものもない下層階級の激しい要求の間で板挟みになった下層中流階級の層の苦悩と似ています。
そのような重圧の中、ダメ押しのコロナウイルスのパンデミックによって、「常識」が目にみえて動揺はじめたころに、個の自由が芽生えはじめた大正時代の日本を舞台に、侵害に屈することなく人間であることの誇りと尊厳の感情をもった登場人物が奮闘し、内的な繋がりをかんじさせる人間関係を繊細に扱う物語、「鬼」となった大切なひとを人間に戻す物語である『鬼滅の刃』が世に露出しはじめます。
『鬼滅の刃』は、日本の文化的・社会的環境により、外からみえない隅っこの暗がりに自分で押し込んでしまい、決して短くない時間のなか放置され、忘れさられているあいだも、ひとり心の奥底でみえないように小さくなって待っていた「私」にやっと訪れた援軍のようなものだったのではないかと言えます。
それは、かつての規範がゆっくりと崩壊し、先がどんどん見えなくなっていく日本で、わたしたちが希望を抱くための新しい規範のイメージを切実にもとめているのだ、ともいいかえられます。人間としての誇りと尊厳をもった「私」として、いま・ここにある心・身体という個をもった人間として、「私」として生きる人間が社会のなかで出会い、つながり、生きてくような規範です。
『鬼滅の刃』という「私」の側にたってくれる援軍が、陽の光のようなあたたかさで照らしだしたものとは、いま・ここに生き存在している心・身体のこえ、「私」として生きることを待っている、わたしたちのなかに埋もれた声なき声です。
「私」として生きられるなら生きたいという意識下に秘められたか細い声、しかし同時に切羽詰まった人間らしい切実な想いの高まり、気持ちの発露と内的つながりへの飢え、そして、他者から個性をもった「私」として認められたい気持ち、それらの普段は内にしまい込まれてきた「私」の想を、『鬼滅の刃』は優しく照らしだしたのではないでしょうか。
・・・・・・
・・・
・
次回以降は、続編であるシリーズ「『鬼滅の刃』からみる自分らしさを取り戻す方法」をお送りします。
このシリーズは「『鬼滅の刃』が少し引くほど大ヒットした理由とは?」で考察していいくことでみえてきた、「私」をすかっり失った「鬼」状態に引き込む日本の環境のなかで、自分らしさを取り戻す方法を探っていきたいと思います。
お付き合いありがとうございました。
参考文献
[放送局] TOKYO MXほか
「劇場版 鬼滅の刃 無限列車編」
[原作] 吾峠呼世晴
[監督] 外崎春雄
[脚本] ufotable
[キャラクターデザイン] 松島晃
[音楽] 梶浦由記、椎名豪
[制作] ufotable
[製作] アニプレックス,集英社、ufotable
[配給] 東宝,アニプレックス
[封切日] 2020年10月16日
[上映時間 ]117分
その他 PG12指定
「自由からの逃走」
[作者] ERICH FROMM
[訳者] 日高 六郎
[発行者] 渋谷 健太郎
[発行所] 株式会社 東京創元社
『愛するということ』
[著者]エーリッヒ・フロム:鈴木 昌訳
[出版]紀伊国屋書店
『資本主義に徳はあるか』
[作者]アンドレ・コント・スポンビル:小須田健/C・カンタン訳
[出版社]紀伊國屋書店