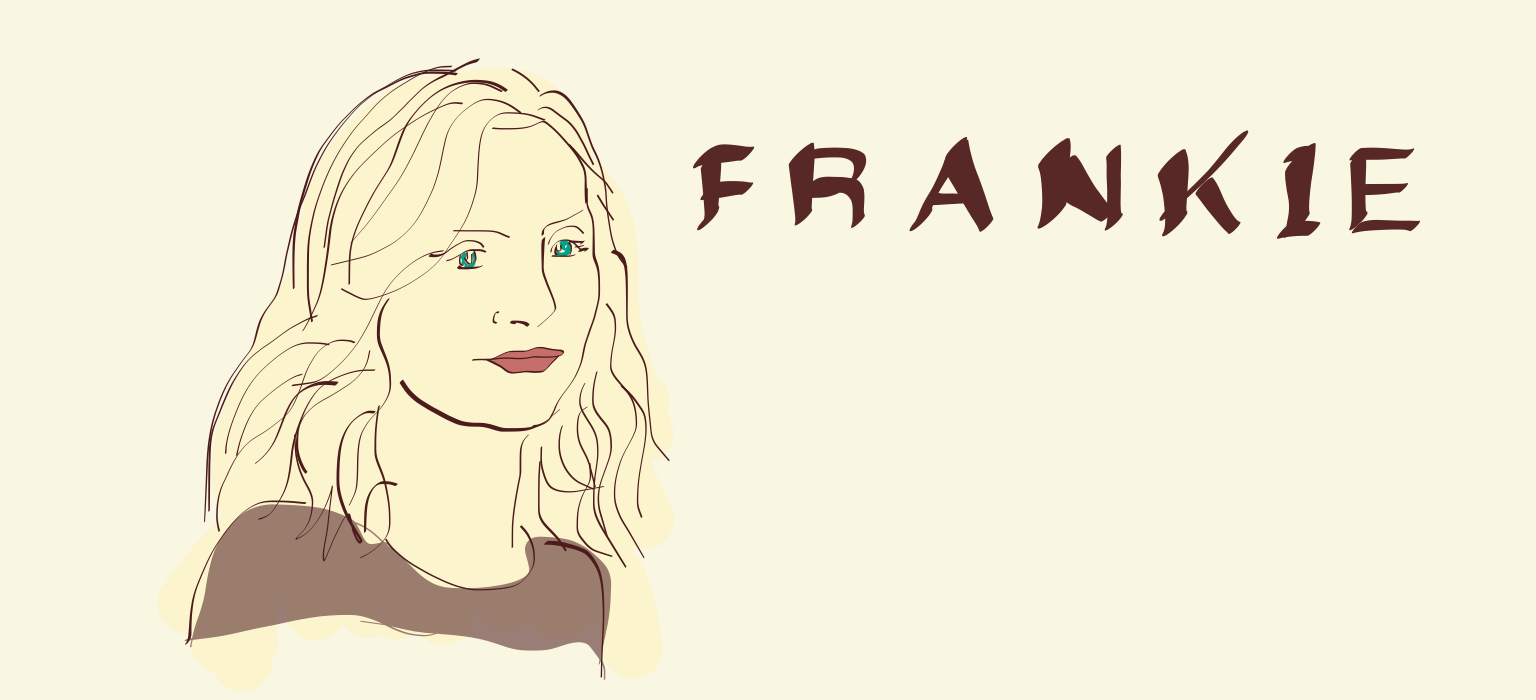目次
cinema review
こんにちは、matsumoto takuya です。今回は、映画「ポルトガル、夏のおわり」をとりあげていきます。
映画「ポルトガル、夏のおわり」は、第72回カンヌ国際映画祭コンペティション部門正式出作品で、主演をフランスの女優イザベル・ユペール、監督は『人生は小説よりも奇なり』を撮ったアイラ・サックスです。公式サイトによると、アイラ・サックスの前作に惚れ込んだイザベル・ユペールが自らラブコールを送り、それを受けた監督がユペールのために書き下ろしたのが本作だそうです。
内容は、個々人の心を尊重することを前提とした文化の中で引き受ける孤独と、その孤独を前提にするからこその苦悩や、愛が語られています。主人公フランキーを中心にした家族の物語なのですが、それぞれの登場人物がお互いに関係の中で影響をあたえながら進んでいく家族劇なのに儚くも美しい世界観の映画です。
映画の舞台は、ポルトガルの世界遺産の街シントラ。この地は、かつてイギリスの詩人バイロン卿が「この世のエデン」と称した地として有名です。エンディングでは儚く繊細な物語とシントラの絶景がシンクロしているような映像は、伝えるためのうまい言葉が見つからないほどいいものでした。世界は美しいんですね。
ところで、わたしは時々、ごまかしの少ない西洋の映画を見るたびに、日本人とはどこか違うなと感じます。家族愛にしても、男女間の愛にしてもです。それはどうしてなんだろう。ここでは、西洋の人間関係と日本人の人間関係の違いついて「映画「ポルトガル、夏のおわり」と関連付けながら少し探っていこうと思います。
以下内容を含みます。
名目と実質
わたしたちは、住む家も、衣服も、都市も、ほとんどが西洋化されています。小さな違いを除けば社会制度もほとんどは西洋のシステムもとにした社会制度の中で暮らしています。なのに、どうしてわたしたち日本人と西洋の人間現関係が違うなどということを言い出すのか、といぶかしく思う方がおられるかもしれません。
しかし、例えば、欧米圏の友人をもったり、その地で生活して人間関係を築いた経験がある人は、それまで感じなかった違和感というか、距離感の取り方の違いを感じるようになった人は少なくないと思います。
役割の前に一人の人間として
映画の中で、フランキー(ユペール演じる)は、よかれと思って家族を思い通りにしようと目論むとても強情なところがある女性です。彼女もそのことに半ば自覚的です。夫は彼女のそんな不完全な部分も含めて妻を愛しているのですが、決して尻に敷かれている様子はなく、彼女から彼への敬意のようなものさえ、愛情表現の中でみてとれます。
また、ユペールの夫の娘(連れ子)の築いた家庭の親子関係もそれに近いものがみられます。中学生の娘は両親の離婚の問題にたいする複雑な想いを抱き苦しんでいるのですが、しっかり母親に想いを伝えます。母親自身も、娘の核心を突く言葉に動揺するのですが、親としてのお決まりの対応ではなく、彼女の言葉で娘に向き合っています。
この二つの例で何が言いたかったのかというと。対等な関係があるということです。ここでは管理する「親」の属性、管理される「子」の属性母親のまえに一人の人間としての関係性が築けているかが重要になっている。パートナーに対して束縛もない。プライベートな領域ではこの、一人の人間として関係を築くことがとても大事にされている。なぜかといえば、愛されるとすれば親や夫や妻という役割ではなく、その人自身だからです。それは言い換えれば、相手の独自性をみとめ独立性を侵さない配慮が重要になっています。
日本だったら、どうでしょうか。大概は子供がこんな態度をとると、「親に迷惑をあまりかけるんじゃないよ」というありがたくないアドバイスを頂戴することが多いと思います。パートナーとの関係では依存が愛と混同されているケースも多いのではないでしょうか。
そもそも「一人の人間」とは何なのかといった疑問がわいてきます。
アイデンティティとは
心理学者で京都大学名誉教授、元文化庁長官であった河合隼雄は著書で、西洋人の人間関係をはアイデンティティを前提といていることを指摘し、そのアイデンティティをこういっています。
”(アイデンティティとは)(筆者が加筆)私はわたしであって、私以外の何者でもない。しかし単にそれだけではなくて、わたしはわたしであって。私以外なにものでもないことを、私がちゃんと感じ、私がそれを自分の心にはっきりと収めることができる。主体的にちゃんと自分のものにできているかどうか、というふうに言っていいと思います”
河合隼雄「心の最終講義」新潮社 262項より引用
つまり、西洋人はわたしという「一人の人間であること」が非常に大事なよりどころになっている。自分のほうをおろそかにしすぎて社会の型に早くはまった人生は、愛することできなくなってしまう問題をはらんでいることを彼らは文化を通して知っています。あとで困るとは、仕事もあるし家もある、一応体裁に必要な家庭もち、食べるものにもこまらないけれども、心がまったく満たされない、やりたいことも自覚できる内省力も育たず退行し、こんなもんかと無気力になってしまうことが多かったということです。
わたしの感覚では、人から見て「成功」していれば、全員が「幸せ」だと思い込めた時代はもう過ぎてしまったような実感があります。どちらか一方が良いという話をいいたいのではなく、個人の領域と社会の領域はセットで必要だと思うのです。
話を映画に戻します。フランキーをはじめ、登場人物は、自分をよりどころにし、自らが見出す愛の程度によって愛する人をうけいれようとしますが、対等に思いを言う分、相手が自分とは違う心をもった他者なのだということ、つまり孤独であることを実感します。わたしをよりどころとして生きるとは、自分が他人と取り換えがきかないことを自覚するということです。そして、その別の言い方が孤独をひきうけることなのです。
孤独と愛
わたしが唯一無二の存在ならら、近くにいる人も個性をもった一人の人間であり唯一無二の存在、つまりは孤独なのだということに気が付けます。しかし、映画をみてもわかるように、彼らは孤独のなかで悩みながら各々が自分にできることをしているのですが、決して孤立しているわけではありません。孤独の重圧のなかで、同じように孤独の重圧を生きている他者を発見することで、同じ孤独の重圧を背負っていけている中で愛おしさのようなものが二つの孤独を引き付けるからです。わたしはこれが、おそらく依存、性欲、支配欲といったものではないもの、つまり愛ののではないか思います。
フランキーと夫ジミー、元夫ミシェルの関係、フランキーと友人アイリーンの関係、フランキーと息子ポールン関係、フランキーの義理の娘シルヴィアとシルヴィアの娘まやとの関係の中にそれがみてとれます。
映画の中で、フランキーの決して快くない目論見のせいで友人アイリーンは振り回され彼氏とは結局別れてしまう展開がありますが、それでも、彼女は病気のフランキーに親身になります。二人の間に、上辺でない友情、愛があったからです。この視点で見ると、西洋人が年齢という属性に縛られず、愛や尊敬をもとに友情を結べるケースをよく見聞きするのもうなずけます。
孤独は孤立とちがい、その重圧と寒さがある一方で他者への関心や尊敬、愛おしさ、といった主体からうまれる自発的な愛によって温かさが用意されているようです。
自他の区別と依存しない関係
話を、今回の問いである、西洋の人間関係と日本人の人間関係の違いについて戻し、まとめたいと思います。その違いは、「私」をよりどころにするがゆえに、私とはちがう他者の存在を認識できていること、いいかえれば孤独を受け入れているところにあります。そしてその孤独の受容が同じように他者が個性を持った存在、つまりは、孤独であることに気が付けることで、自発的な興味や尊敬、共感といった自発的な感情をもとに関係を結べるかどうかにあるとわたしは思います。
言い換えれば、孤独を受け入れられないと、自分であることが不安を解消したいという受動的な動機で、関係がつくられてしまう。安心は得られても、いつ見捨てられるかもしれないという不安があるので、束縛や迎合といった愛とは逆のベクトルの欲望にとらわれてしまうことが少なくない。井戸端会議の内容がほぼ、噂話、悪口であり、かりにいいニュースであっても聞いてないよと思ってしまうのはそのためかもしれません。
このかもしれません、あたりで今回はやめておこうとおもいます。
注)もちろん日本人の中でも素敵な人間関係を築けてらっしゃる方もいらっしゃると思いますよ。
以上、映画「ポルトガル、夏のおわり」レビューでした。おつきあいありがとうございました。
「ポルトガル、夏のおわり」
劇場情報はこちら